テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
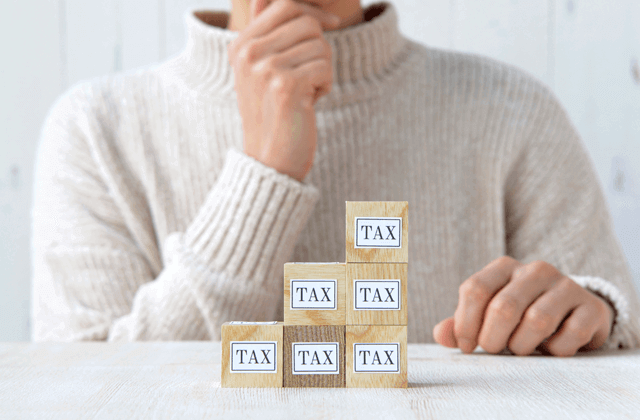
消費税はどこまで上がるのか?
安倍晋三首相は2018年10月15日の臨時閣議で、2019年10月に消費税率を予定通り8%から10%へ引き上げると表明しました。ここ数年延期されていた消費税の引き上げが、ついに実施されます。時期は2019年10月1日から、税率は10%です。細かい内訳としては、消費税率7.8%、地方消費税率が2.2%となっています。またこれと同時に軽減税率制度が実施されます。
軽減税率とは、主に飲食料品(食品表示法に規定する食品※酒税法に規定する酒類を除く)で、外食は含まない)などの税率を8%とする、というものです。日常生活に直結する品目に関しては、低所得者に配慮する必要があるという理由で制定されているようです。
前回消費税が8%に引き上げられたのは2014年の4月でした。消費税は導入以来、少しずつあがっていますが、この先のことはあまり明確に見えてきません。ここでは、今後、どのように変化する可能性があるのか、分析をもとに読み解いてみましょう。
また、所得税や法人税は景気が良いときには自動的に多く入ってきますが、景気が悪化すればたちまち不安定になります。こういった点でもより安定した財源を国が確保するために、消費税を上げる必要があります。
国税庁のホームページに掲載されている税の国際比較によると、税率が最も高いところで25%です。これはデンマーク、スウェーデン、ノルウェーのスカンジナビア3カ国。次いで22%のイタリア、21%のオランダ、ベルギー、20%でフランス、イギリス、オーストリアと続きます。その他、中国は17%、韓国は10%、シンガポールは7%となっています。ちなみにアメリカでは国が定める消費税はなく、セールスタックスが消費税に相当するようですが、これは州ごとにかなりバラバラです。例えば、オレゴン州やモンタナ州では0%、イリノイ州では9.25%とかなりの開きがあります。
北欧が際立って高いイメージですね。福祉大国として有名なスウェーデンでは、教育費は大学まですべて無料、20歳以下は医療費無料です。スウェーデンでは1960年の時点で消費税(のちの付加価値税)が導入されています。この時の税率は4.2%。こういった早い時期から消費税を導入した背景には、1929年の世界恐慌後、1930年代から40年代にかけて形成された社会保障制度で、弱者を救済する仕組みが作られたことがあるようです。つまり、歴史的な積み重ねがあります。
キリスト教的相互扶助の価値観や社会情勢、人口1000万人程度といったコンパクトな国の規模といった、日本と異なる背景はあります。また、消費税率が高く社会保障が充実していることが、そのまま理想的な形であると言い切ることはできません。しかし、早い時期から福祉対策を行ったことは、消費税率が高く設定できた一つの理由とはいえるかもしれません。
やはりある程度の状況の変化を想定して、財政はそれ相応の余裕をもっておかなければ、柔軟な対応ができません。こういったことから考えれば、この先、最低でも17%以上は覚悟しておく必要がありそうです。
軽減税率とは、主に飲食料品(食品表示法に規定する食品※酒税法に規定する酒類を除く)で、外食は含まない)などの税率を8%とする、というものです。日常生活に直結する品目に関しては、低所得者に配慮する必要があるという理由で制定されているようです。
前回消費税が8%に引き上げられたのは2014年の4月でした。消費税は導入以来、少しずつあがっていますが、この先のことはあまり明確に見えてきません。ここでは、今後、どのように変化する可能性があるのか、分析をもとに読み解いてみましょう。
なぜ消費税を上げるのか
消費税は何に使われるのか、と考えると、真っ先に考えられるのは「社会保障費」だと思われます。つまり、少子高齢化対策が主だった目的と言えます。税には他にも所得税や法人税などもあります。なぜ消費税が上げられるのかといえば、社会保障費を現役世代にだけ負担させるのでなく、高齢者を含めた全世代で負担することがふさわしいと考えられるからです。また、所得税や法人税は景気が良いときには自動的に多く入ってきますが、景気が悪化すればたちまち不安定になります。こういった点でもより安定した財源を国が確保するために、消費税を上げる必要があります。
北欧各国の消費税は25%
では、他国の消費税率はどれくらいなのでしょうか。日本で消費税が導入されたのは1989年(平成元年)の竹下内閣のころでしたが、ヨーロッパ諸国ではそれ以前から「付加価値税」として導入されていました。現在では全世界で100カ国以上の国と地域で導入されています。国税庁のホームページに掲載されている税の国際比較によると、税率が最も高いところで25%です。これはデンマーク、スウェーデン、ノルウェーのスカンジナビア3カ国。次いで22%のイタリア、21%のオランダ、ベルギー、20%でフランス、イギリス、オーストリアと続きます。その他、中国は17%、韓国は10%、シンガポールは7%となっています。ちなみにアメリカでは国が定める消費税はなく、セールスタックスが消費税に相当するようですが、これは州ごとにかなりバラバラです。例えば、オレゴン州やモンタナ州では0%、イリノイ州では9.25%とかなりの開きがあります。
北欧が際立って高いイメージですね。福祉大国として有名なスウェーデンでは、教育費は大学まですべて無料、20歳以下は医療費無料です。スウェーデンでは1960年の時点で消費税(のちの付加価値税)が導入されています。この時の税率は4.2%。こういった早い時期から消費税を導入した背景には、1929年の世界恐慌後、1930年代から40年代にかけて形成された社会保障制度で、弱者を救済する仕組みが作られたことがあるようです。つまり、歴史的な積み重ねがあります。
キリスト教的相互扶助の価値観や社会情勢、人口1000万人程度といったコンパクトな国の規模といった、日本と異なる背景はあります。また、消費税率が高く社会保障が充実していることが、そのまま理想的な形であると言い切ることはできません。しかし、早い時期から福祉対策を行ったことは、消費税率が高く設定できた一つの理由とはいえるかもしれません。
2025年の消費税は17%~19%
では、日本では今後消費税はどのくらいの税率になるのでしょうか。第一生命経済研究所の主席エコノミスト熊野英生氏は、日本の財政状況から考えると2025年までに17%~19%ではないか、と示しています。もちろんこれは時の政権の政策や、経済の状況により変化する部分が多くあるでしょう。たとえば、消費税のような安定財源を確保せずとも、所得税や法人税といった自然税収で確保できるのであれば、消費税は13%~14%で済む可能性はあると言われています。しかし、自然税収に任せるのは、リスクが高いことも事実です。これは経済が安定的に成長し、社会情勢に大きな問題が起きないということにかかっています。やはりある程度の状況の変化を想定して、財政はそれ相応の余裕をもっておかなければ、柔軟な対応ができません。こういったことから考えれば、この先、最低でも17%以上は覚悟しておく必要がありそうです。
<参考サイト>
・国税庁:税の国際比較
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page13.htm
・Economic Trends:将来の消費税率はどこまで上がるか
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/macro/2018/kuma181009ET.pdf
・国税庁:税の国際比較
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page13.htm
・Economic Trends:将来の消費税率はどこまで上がるか
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/macro/2018/kuma181009ET.pdf
人気の講義ランキングTOP20
ラマルクの進化論…使えば器官が発達し、それが子に伝わる
長谷川眞理子
島田晴雄先生の体験談から浮かびあがるアメリカと日本
テンミニッツ・アカデミー編集部










