テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
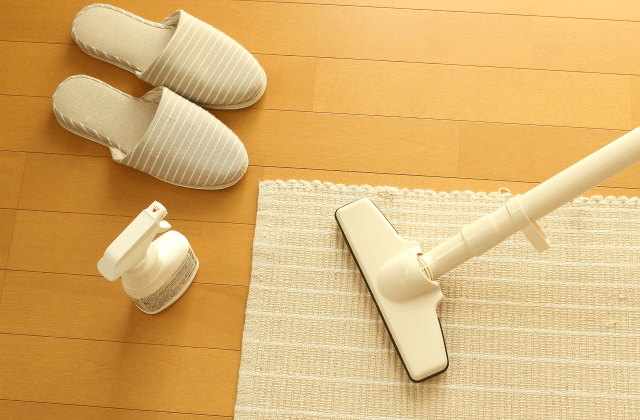
日本人は本当にキレイ好き?世界のお掃除事情
清掃機器の最大手メーカーで“高圧洗浄機の代名詞”ともいえるドイツのケルヒャー社(日本法人:ケルヒャー ジャパン株式会社)が、アメリカ・イギリス・中国・ドイツ・日本・フランス・ブラジル・ポーランド・ロシアの世界9カ国、計9125人を対象に「掃除に関する意識調査」をアンケート形式で実施。調査結果から「世界のお掃除事情」が垣間見えてきました。
「掃除にかける時間」が最長のロシアは9カ国の平均2.10時間を大きく上回る一方、最短の国と判明した日本は平均を大きく下回り、最長国であるロシアと比べると3分の1の時間であることなど、掃除に時間をかけない傾向がみえてきました。
次に「家がキレイであることが重要かどうか?」の問いに対する回答をみてみましょう。世界9カ国中で平均94%が「重要だ」と回答しましたが、この問いにおいても日本は9カ国の中で最も低い74%という結果となっています。この結果に対してケルヒャー社は、「欧米とは異なり、日本は室内での土足文化がないことなど、各国によって清潔さの概念が違うかもしれません」と考察しています。
その他“世界各国のお掃除トリビア”として、「日本人は家電好き。82%の人が家事を楽にするために清掃家電を使う」一方で、ロボット掃除機を使用している家の割合は14%と平均を下回る結果となっています。ちなみに中国が平均の17%を大きく上回る38%と、9カ国中で一番ロボット掃除が普及している結果となっています。
さらに日本は、「掃除を楽にするために家事代行サービスを活用することについてどう思いますか?」の問いに対して、「利用している」がわずか10%という結果も出ています。ちなみに「前向きに検討中」は22%となっていますが、7割近い人は「利用しない」と回答しており、そのうち最も多い34%の人が「金額が高い」ことを利用しない理由に挙げています。
また、「21%のドイツ人が「床に落ちたものを食べてもいいくらいキレイ」だと思って」いたり、「ポーランドでは55%の人が「家族やパートナーが掃除に協力してくれる」と回答」していたり、「ブラジルでは81%の人が家の掃除にほうきやバケツを使う」など、各国で掃除方法に違いや特徴があることがうかがえます。
たとえば日本の学校教育では「掃除の時間」があり、2017年改訂の「学習指導要領」にも「清掃」がキャリア教育の一環として組み込まれています。しかし多くの国では学校で子どもが掃除をすることはありません。同様に禅には「一掃除、二信心」という言葉があり、少なくとも1日に3回は掃除するほど掃除を重視しています。「掃除は、汚れをとるためというより、心を磨くために行う」と、曹洞宗徳雄山建功寺住職の枡野俊明氏は述べており、掃除が文化の影響を強く受け、精神面にも大きな価値観を与えていることがわかります。
他方、「日本人がキレイ好き」といわれる背景には、水が豊富な日本では「水洗い」が手軽であり、衣類の洗濯や入浴・洗髪などこまめで清潔な人が多いといったことがあると思われますが、実はシーツや枕カバーといったリネン類の洗濯は、欧米などに比べて頻度が低いといわれています。そして世界を見渡せば、水自体が貴重で清潔であることや「キレイ」のために簡単に水を使えない国はたくさんあり、それらの国とは環境も価値観も違ってきます。
住環境の違いや気候・風土によっても掃除コストの前提条件が違うため、一概に「掃除にかけた時間」だけを比較しても「キレイ好き」度を決めることは難しいことがわかります。「キレイ」の反対概念を自身や自国になじみのある文化的価値観だけで、「汚い」「不潔」「不浄」などと判断してしまうことは、危うさを孕んでいるのかもしれません。
ただし、特に「心地よい空間を大切にする」といわれるドイツ人は、自分の住まいの整理整頓や行き届いた掃除だけでなく街の景観も「整えられるモノ」の対象になるため、隣人やご近所であっても「汚れた状態」であれば容赦なく注意や警告を受けるといいます。
しかしその大前提に、ドイツ人は「オルドヌング(Ordnung=整理整頓され、秩序ただしいこと)は人生の半分」をモットーに、あらかじめ整理整頓をして掃除のしやすい環境としています。そのため、決めた掃除時間は短くともキレイな環境を維持でき、さらには人生の無駄な時間や体力の消耗を予防することで心豊かな人生の基礎としているといえます。
沖氏は、“怖いドイツの掃除魔”に「掃除は嫌いでも好きでもいいのです。上手になること」と教わり、「目からウロコ」だったといいます。キレイ好きであることが目的なのではなく、まずはスキルや習慣として生活の中に無理なく掃除を取り入れ、人生の質を高めることの大切さを示してくれています。
ちなみに沖氏は「掃除の基本動作4つ」を、【はたく】部屋のホコリを払うことは掃除の基本、【掃く】床に落ちたものは必ず拾い床の汚れはすぐほうきで掃く、【拭く】ホコリをこまめに取って汚れたらサッと拭く、【磨く】頑固な汚れは磨く必要があるがなるべく磨く動作を減らす掃除を心がけることが大切、と述べています。
そして「効率よく掃除する方法」として、自分のライフスタイルや住環境にあわせて「キレイを保つための掃除スケジュール」を持つことも推奨しています。例としては、【毎日やること】汚れを残さないように汚れたらすぐ拭く・使ったものは使ったときに手入れするなど、【週に1度】時間を決めてテキパキと掃除機かけやほうきでの掃き出し・床拭きやダイニング以外の家具やテーブルをサッと拭く・リネン類の交換など、【月に1、2度】窓ガラスは雨上りの午前中に拭く・窓や天井や壁のホコリ払いなど、【3カ月に1度】カーペットの手入れ・カーテンの洗濯など、【1年に1度】家具の裏側の掃除や徹底的な家具磨きなどです。
部屋や家は「部屋が乱れていると心も乱れる」「家は住人の人となりを表す」などとよくいわれますが、ドイツでも「住まいは住む人の心の状態を表す」といわれているそうです。掃除上手になって整理整頓された部屋に暮らすことによって心に余裕が生まれキレイな心が育まれることが、部屋だけでなく人生それ自体が美しく豊かになる、つまり本当のキレイ好きへの王道であり近道なのかもしれません。
各国で異なるお掃除方法や特徴
まず9カ国の「一週間でどれくらいの時間を掃除に費やしますか?」の回答からみていきましょう。費やす時間が多い順に、1)ロシア3.05時間、2)ポーランド2.40時間、3)ブラジル2.25時間、4)中国2.19時間、5)ドイツ2.17時間、6)アメリカ1.43時間、7)フランス1.38時間、8)イギリス1.25時間、9)日本1.09時間という結果でした。「掃除にかける時間」が最長のロシアは9カ国の平均2.10時間を大きく上回る一方、最短の国と判明した日本は平均を大きく下回り、最長国であるロシアと比べると3分の1の時間であることなど、掃除に時間をかけない傾向がみえてきました。
次に「家がキレイであることが重要かどうか?」の問いに対する回答をみてみましょう。世界9カ国中で平均94%が「重要だ」と回答しましたが、この問いにおいても日本は9カ国の中で最も低い74%という結果となっています。この結果に対してケルヒャー社は、「欧米とは異なり、日本は室内での土足文化がないことなど、各国によって清潔さの概念が違うかもしれません」と考察しています。
その他“世界各国のお掃除トリビア”として、「日本人は家電好き。82%の人が家事を楽にするために清掃家電を使う」一方で、ロボット掃除機を使用している家の割合は14%と平均を下回る結果となっています。ちなみに中国が平均の17%を大きく上回る38%と、9カ国中で一番ロボット掃除が普及している結果となっています。
さらに日本は、「掃除を楽にするために家事代行サービスを活用することについてどう思いますか?」の問いに対して、「利用している」がわずか10%という結果も出ています。ちなみに「前向きに検討中」は22%となっていますが、7割近い人は「利用しない」と回答しており、そのうち最も多い34%の人が「金額が高い」ことを利用しない理由に挙げています。
また、「21%のドイツ人が「床に落ちたものを食べてもいいくらいキレイ」だと思って」いたり、「ポーランドでは55%の人が「家族やパートナーが掃除に協力してくれる」と回答」していたり、「ブラジルでは81%の人が家の掃除にほうきやバケツを使う」など、各国で掃除方法に違いや特徴があることがうかがえます。
「キレイ」の価値観も多様。では日本人は?
ところで、そもそも「キレイ」の捉え方や求め方は、環境や文化、地域や国によってもさまざまです。住まいの掃除だけをとってみても、部屋の広さや家の大きさ、集合住宅か戸建てか、家族構成や庭の有無、気候や風土の違いなどによって、掃除に必要な時間は変わってきます。たとえば日本の学校教育では「掃除の時間」があり、2017年改訂の「学習指導要領」にも「清掃」がキャリア教育の一環として組み込まれています。しかし多くの国では学校で子どもが掃除をすることはありません。同様に禅には「一掃除、二信心」という言葉があり、少なくとも1日に3回は掃除するほど掃除を重視しています。「掃除は、汚れをとるためというより、心を磨くために行う」と、曹洞宗徳雄山建功寺住職の枡野俊明氏は述べており、掃除が文化の影響を強く受け、精神面にも大きな価値観を与えていることがわかります。
他方、「日本人がキレイ好き」といわれる背景には、水が豊富な日本では「水洗い」が手軽であり、衣類の洗濯や入浴・洗髪などこまめで清潔な人が多いといったことがあると思われますが、実はシーツや枕カバーといったリネン類の洗濯は、欧米などに比べて頻度が低いといわれています。そして世界を見渡せば、水自体が貴重で清潔であることや「キレイ」のために簡単に水を使えない国はたくさんあり、それらの国とは環境も価値観も違ってきます。
住環境の違いや気候・風土によっても掃除コストの前提条件が違うため、一概に「掃除にかけた時間」だけを比較しても「キレイ好き」度を決めることは難しいことがわかります。「キレイ」の反対概念を自身や自国になじみのある文化的価値観だけで、「汚い」「不潔」「不浄」などと判断してしまうことは、危うさを孕んでいるのかもしれません。
世界一のキレイ好き!?ドイツ流掃除と美意識
さらに「キレイ好き」であっても、「掃除に時間をかけることをよしとしない」といった価値観や美意識もあるでしょう。たとえば「世界一キレイ好きな国」とも称えられるドイツであっても、掃除ばかりして神経質にこだわる人は“プツツトイフエル(Putzteufel=掃除魔)”と呼ばれて良い印象を持たれないと、ドイツでの生活を生かしたハウスクリーニング会社「フラオ グルッペ」代表で生活評論家でもある沖幸子氏は述べています。ただし、特に「心地よい空間を大切にする」といわれるドイツ人は、自分の住まいの整理整頓や行き届いた掃除だけでなく街の景観も「整えられるモノ」の対象になるため、隣人やご近所であっても「汚れた状態」であれば容赦なく注意や警告を受けるといいます。
しかしその大前提に、ドイツ人は「オルドヌング(Ordnung=整理整頓され、秩序ただしいこと)は人生の半分」をモットーに、あらかじめ整理整頓をして掃除のしやすい環境としています。そのため、決めた掃除時間は短くともキレイな環境を維持でき、さらには人生の無駄な時間や体力の消耗を予防することで心豊かな人生の基礎としているといえます。
沖氏は、“怖いドイツの掃除魔”に「掃除は嫌いでも好きでもいいのです。上手になること」と教わり、「目からウロコ」だったといいます。キレイ好きであることが目的なのではなく、まずはスキルや習慣として生活の中に無理なく掃除を取り入れ、人生の質を高めることの大切さを示してくれています。
ちなみに沖氏は「掃除の基本動作4つ」を、【はたく】部屋のホコリを払うことは掃除の基本、【掃く】床に落ちたものは必ず拾い床の汚れはすぐほうきで掃く、【拭く】ホコリをこまめに取って汚れたらサッと拭く、【磨く】頑固な汚れは磨く必要があるがなるべく磨く動作を減らす掃除を心がけることが大切、と述べています。
そして「効率よく掃除する方法」として、自分のライフスタイルや住環境にあわせて「キレイを保つための掃除スケジュール」を持つことも推奨しています。例としては、【毎日やること】汚れを残さないように汚れたらすぐ拭く・使ったものは使ったときに手入れするなど、【週に1度】時間を決めてテキパキと掃除機かけやほうきでの掃き出し・床拭きやダイニング以外の家具やテーブルをサッと拭く・リネン類の交換など、【月に1、2度】窓ガラスは雨上りの午前中に拭く・窓や天井や壁のホコリ払いなど、【3カ月に1度】カーペットの手入れ・カーテンの洗濯など、【1年に1度】家具の裏側の掃除や徹底的な家具磨きなどです。
部屋や家は「部屋が乱れていると心も乱れる」「家は住人の人となりを表す」などとよくいわれますが、ドイツでも「住まいは住む人の心の状態を表す」といわれているそうです。掃除上手になって整理整頓された部屋に暮らすことによって心に余裕が生まれキレイな心が育まれることが、部屋だけでなく人生それ自体が美しく豊かになる、つまり本当のキレイ好きへの王道であり近道なのかもしれません。
<参考文献・参考サイト>
・「すっきり生きる禅の知恵」、『ゆうゆう』(2018年6月号、枡野俊明著、主婦の友社)
・『ドイツ流掃除の賢人』(沖幸子著、知恵の森文庫)
・日本人は本当にキレイ好き!?各国で異なるお掃除事情
https://www.atpress.ne.jp/news/169652
・新学習指導要領(本文、解説、資料等):文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm
・「すっきり生きる禅の知恵」、『ゆうゆう』(2018年6月号、枡野俊明著、主婦の友社)
・『ドイツ流掃除の賢人』(沖幸子著、知恵の森文庫)
・日本人は本当にキレイ好き!?各国で異なるお掃除事情
https://www.atpress.ne.jp/news/169652
・新学習指導要領(本文、解説、資料等):文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm
人気の講義ランキングTOP20
適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物
長谷川眞理子










