テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
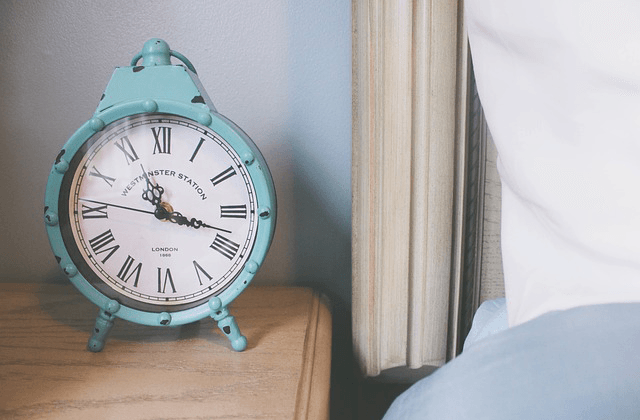
人の睡眠と覚醒のリズムは24時間サイクルではない
目覚まし時計をいくつも使っても、朝すっきりと起きられない。夜は夜でなかなか寝付けない。こんな悩みを持つ方は少なからずいるでしょう。でも、こうした睡眠と覚醒のリズムのコントロールに苦労するというのは、ヒトが背負った宿命のようなものなのです。
ここで少々やっかいなのは、この睡眠と覚醒のサイクルは25~26時間であるということ。日常生活を営むうえで必要な1日24時間というサイクルにはぴったり当てはまらないのです。この事実は、時計のない空間で、「自由に寝て起きて」を繰り返すという実験の結果、分かりました。つまり、私たちは睡眠にかかわる身体のリズムを、少々無理して1日24時間の枠に当てはめなければいけないということ。社会生活などおかまいなしに気ままに生きている人でない限り、このようなズレを我慢しなければいけないのは、致し方のないことなのです。
それは適度な運動や規則正しい食事時間を心がけること。そして、他の人と交流をすること、すなわち昼間の時間帯に他人と同調する生活を送ることです。好き勝手に食べたい時に食べ、外の光も浴びずに部屋に引きこもってゲームばかりしている。これでは不眠や睡眠障害を改善できません。ごく健康的できちんとした社会生活を送ることが、よい睡眠を得る第一歩となるのです。
早起きすると昼間どうしても眠くなってしまうという場合は、適度な昼寝も効果的です。ただし、昼寝をするのなら15時くらいまでにすること。長さも1時間以内、できれば30分以内にとどめておけば、夜の睡眠を妨げるようなことにはなりません。
就寝前のコーヒーなどによるカフェイン摂取や熱すぎるお風呂も避けましょう。カフェインは覚醒系の働きを活発にしますし、42度以上の熱いお風呂は交感神経を緊張させ、安眠を妨げてしまうからです。
安定した睡眠を手に入れたいのなら、睡眠と覚醒のリズムを念頭に、生活習慣を見直すことから始めましょう。ほんの少し、日常的な行為に意識を向けることで、睡眠の質はよくなります。「8時間は眠らないといけない」などと睡眠時間の長さにとらわれずに、自分にあった方法で質のよい眠りを手にしてください。
人の睡眠と覚醒のリズムは24時間サイクルではない
私たちの脳には、睡眠と覚醒のリズムを調節する機能が備わっています。大きく分けると、3種類の調節を行っており、1つは眠る時間(夜)になったら眠りを促す機能。もう1つは疲れたなと思ったら眠るという機能。そして、最後に危険を察知し不安を感じたら眠らないという機能です。これらの3つの機能のバランスをとることで、私たちの睡眠と覚醒のリズムは成り立っています。ここで少々やっかいなのは、この睡眠と覚醒のサイクルは25~26時間であるということ。日常生活を営むうえで必要な1日24時間というサイクルにはぴったり当てはまらないのです。この事実は、時計のない空間で、「自由に寝て起きて」を繰り返すという実験の結果、分かりました。つまり、私たちは睡眠にかかわる身体のリズムを、少々無理して1日24時間の枠に当てはめなければいけないということ。社会生活などおかまいなしに気ままに生きている人でない限り、このようなズレを我慢しなければいけないのは、致し方のないことなのです。
よい睡眠を得るために「きちんとした社会生活」を意識する
だからといって、毎日辛い思いに耐えなければいけないわけではありません。毎日の行動に少し注意を払うことで、この睡眠・覚醒リズムを24時間に当てはめやすくすることができるのです。それは適度な運動や規則正しい食事時間を心がけること。そして、他の人と交流をすること、すなわち昼間の時間帯に他人と同調する生活を送ることです。好き勝手に食べたい時に食べ、外の光も浴びずに部屋に引きこもってゲームばかりしている。これでは不眠や睡眠障害を改善できません。ごく健康的できちんとした社会生活を送ることが、よい睡眠を得る第一歩となるのです。
早起きはOK、早寝は逆効果
また、睡眠改善のためには「早寝」よりも「早起き」を意識する、というのもちょっとしたコツです。睡眠時間を確保したいという場合、どうしても「早く寝よう」と思いがちです。しかし、いつもの就寝時間を無理に早めると、かえって寝つきが悪く夜中に何度も目覚めることになりかねません。無理に早寝をするより、早起きをして昼間の活動性を上げる方が、夜適切な時間に眠くなり、ぐっすりと良い睡眠がとれるようになるのです。早起きすると昼間どうしても眠くなってしまうという場合は、適度な昼寝も効果的です。ただし、昼寝をするのなら15時くらいまでにすること。長さも1時間以内、できれば30分以内にとどめておけば、夜の睡眠を妨げるようなことにはなりません。
就寝前のコーヒーなどによるカフェイン摂取や熱すぎるお風呂も避けましょう。カフェインは覚醒系の働きを活発にしますし、42度以上の熱いお風呂は交感神経を緊張させ、安眠を妨げてしまうからです。
寝酒よりも規則正しい生活を
勘違いしやすいのは「寝酒」の効果です。ごく少量(日本酒なら1合程度)ならある程度のリラックス効果を及ぼすとは言えます。しかし、アルコールを分解するときに体は熱を発するため、その結果として体の深部体温は上がっていきます。体温上昇は「起きろ」というサインとなるため、寝酒は睡眠を妨げたり眠りを浅くしてしまうのです。さらには、飲酒量の増加、睡眠時無呼吸症候群といったリスクにも気をつけなければいけません。安定した睡眠を手に入れたいのなら、睡眠と覚醒のリズムを念頭に、生活習慣を見直すことから始めましょう。ほんの少し、日常的な行為に意識を向けることで、睡眠の質はよくなります。「8時間は眠らないといけない」などと睡眠時間の長さにとらわれずに、自分にあった方法で質のよい眠りを手にしてください。
人気の講義ランキングTOP20










