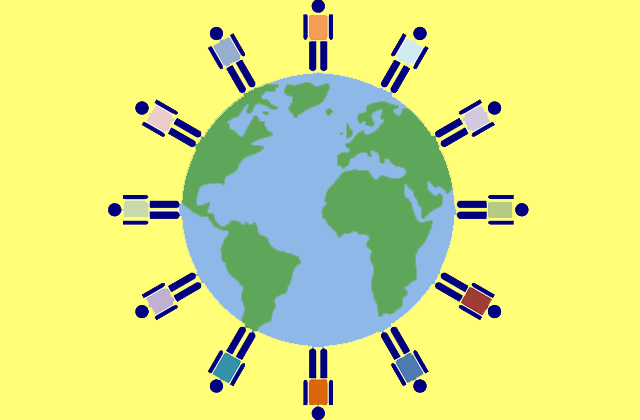
世界の人口「減少」ランキング 日本は何位?
国連によると世界の人口は約76億人(2017年時点)とされています。2005年からの12年間で10億人増加したとのこと。単純計算で年間8300万人ずつ増加していることになります。今後も世界人口は増えていくことが予測されています。その一方で、日本も含めて人口が減少している地域も多くあります。ここでは2017年に人口が減少した国を取り上げて理由を見たのち、これからの日本の人口がどうなるのかといった点まで見てみましょう。
1位:プエルトリコ -2.4
2位:リトアニア -1.4
3位:ナウル -1.3
4位:クロアチア -1.2
5位:ラトビア -0.9
5位:シリアアラブ共和国 -0.9
6位:ブルガリア -0.7
7位:ルーマニア -0.6
8位:セルビア -0.5
9位:アンドラ -0.4
9位:ウクライナ -0.4
10位:ボスニア・ヘルツェゴビナ -0.3
10位:ハンガリー -0.3
11位:ポルトガル -0.2
11位:ヴァージン諸島(アメリカ領) -0.2
11位:ギリシャ -0.2
11位:日本 -0.2
12位:イタリア -0.1
12位:アルバニア -0.1
12位:モルドバ -0.1
2015年は高齢者1人に対して現役世帯2.3人という比率でしたが、2065年にはこの比率は1.3になります。2053年に日本の総人口は1億人を割り、2065年(約46年後)の日本の人口は8,808万人となることが想定されています。2016年での総人口は1億2,670万6千人なので、およそ50年で4,000万人減り、現在の3分の2になります。このまま進めば、2100年頃までには約6,000万人程度と現在の半分になることが予想されています。
世界の人口「減少」ランキング
世界銀行が発表している国や地域別の人口増加率を見ると、数値がマイナスの地域、つまり人口が減少している地域は20ヶ所あります。以下、人口増加率が低い順に一覧です(数値はいずれも2017年の人口増加率)。1位:プエルトリコ -2.4
2位:リトアニア -1.4
3位:ナウル -1.3
4位:クロアチア -1.2
5位:ラトビア -0.9
5位:シリアアラブ共和国 -0.9
6位:ブルガリア -0.7
7位:ルーマニア -0.6
8位:セルビア -0.5
9位:アンドラ -0.4
9位:ウクライナ -0.4
10位:ボスニア・ヘルツェゴビナ -0.3
10位:ハンガリー -0.3
11位:ポルトガル -0.2
11位:ヴァージン諸島(アメリカ領) -0.2
11位:ギリシャ -0.2
11位:日本 -0.2
12位:イタリア -0.1
12位:アルバニア -0.1
12位:モルドバ -0.1
アメリカへの人口流出
1位は、カリブ海北東部に位置する島で構成されるプエルトリコ(アメリカ自治領)です。2015年に財政破綻したのち、2017年9月に襲来したハリケーン「イルマ」と「マリア」によってインフラが被害を受けて断続的に停電が起きるなど、日常生活を営むのも困難な状況にあります。住民は主にアメリカ本国に流出しています。もともと人口は減少傾向でしたが、ここ数年でさらに減少に拍車がかかっているようです。東欧から西欧への人口流出
2位のリトアニア、5位のラトビアは、旧バルト三国(残るはエストニア)です。リトアニアは1990年代頭に約370万人だった人口が2016年には約290万人と22%近く減少しています。こういった東欧の国々が多く入っている点については、1990年代初めまでに起こった社会主義体制の崩壊後、産業をうまく育っていないことが関連しているようです。若者の雇用機会が少なく、比較的豊かな西欧への移住が進む現実を表しています。「国まるごと移住」はうまく行かず
3位のナウルは、かつてリン鉱石資源で栄えた太平洋の小さな島国です。現在は資源が枯渇しています。もともと人口1万人程度の小さな島国なので、移民の状況によって大きく人口増加率が変動するようです。一時期は資源採掘の責任を認めたオーストラリア領内への全国民の移住まで提案されましたが、ナウル国民は自分たちのアイデンティティを守るという理由で拒否しています。日本の移住は国内で起こる
ここまで見たとおり、人口が減少している国の多くは、経済的な問題で雇用が創出できないといった問題を抱えています。一方、人口減少率11位の日本は、そこまで経済状態が悪いわけではありません。また、他国への人口流出も起きていません。最も大きな理由は、国内での出生率の低下と高齢化です。また地方から都市へ若年層が移動し、地方が高齢化する問題が起こっています。この人の動きが、国家の枠組みを越えて起きているのがヨーロッパの状況とも言えるでしょう。ともあれ、日本は移民をあまり多く受けいれていないこともあり、国内での動きがそのまま人口問題に反映しています。日本の人口は約50年で3分の2に
総務省の発表している資料を見ると、2025年に「団塊の世代」は75歳以上となります。平均寿命は今後伸びることが予想されており、2065年には女性の平均寿命は90年を超えると見込まれています。一方、出生数は減少を続けています。2016年の出生数は97万6,978人で、統計開始以来、初めて100万人を切っており、この先、2065年には56万人になると推計されています。2015年は高齢者1人に対して現役世帯2.3人という比率でしたが、2065年にはこの比率は1.3になります。2053年に日本の総人口は1億人を割り、2065年(約46年後)の日本の人口は8,808万人となることが想定されています。2016年での総人口は1億2,670万6千人なので、およそ50年で4,000万人減り、現在の3分の2になります。このまま進めば、2100年頃までには約6,000万人程度と現在の半分になることが予想されています。
<参考サイト>
・World Population Prospects Key findings & advance tables 2017 REVISION | United Nations
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
・Population growth (annual %) | THE WORLD BANK
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?end=2017&most_recent_value_desc=false&start=2017&view=chart
・希望のない最小の島国ナウルの全人口をオーストラリアに移住させる計画はなぜ頓挫したか|Newsweek
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/08/post-5669.php
・平成29年版高齢社会白書(全体版) 第1章 高齢化の状況(第1節 1)|内閣府
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/zenbun/s1_1_1.html
・口推計(平成29年10月1日現在)|総務省統計局
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2017np/index.html
・出生数・出生率の推移|内閣府
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/data/shusshou.html
・World Population Prospects Key findings & advance tables 2017 REVISION | United Nations
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
・Population growth (annual %) | THE WORLD BANK
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?end=2017&most_recent_value_desc=false&start=2017&view=chart
・希望のない最小の島国ナウルの全人口をオーストラリアに移住させる計画はなぜ頓挫したか|Newsweek
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/08/post-5669.php
・平成29年版高齢社会白書(全体版) 第1章 高齢化の状況(第1節 1)|内閣府
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/zenbun/s1_1_1.html
・口推計(平成29年10月1日現在)|総務省統計局
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2017np/index.html
・出生数・出生率の推移|内閣府
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/data/shusshou.html
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子







