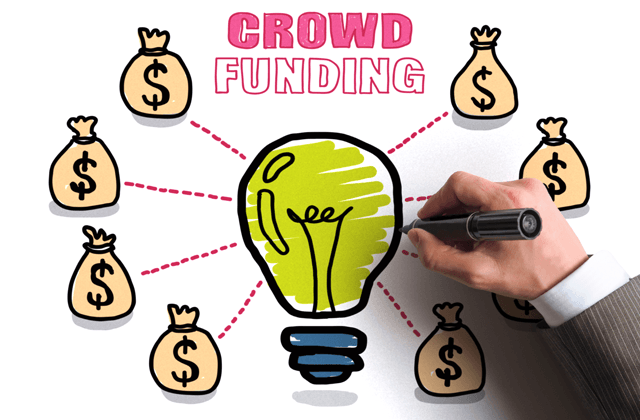
今時の資金調達「クラウドファンディング」とは?
インターネットで資金調達する仕組みであるクラウドファンディングは、「クラウド[crowd]」(群衆)と「ファンディング[funding]」(資金調達)を組み合わせた造語です。日本では2011年の東日本大震災を契機に広く知られるようになりました。
クラウドファンディングと一口に言っても種類はさまざまで、その中身をきちんと理解している人はそう多くありません。クラウドファンディングとは何か、デメリットも含め、できるだけわかりやすく解説します。
投資型が配当という形でリターンを受け取れるのに対して、「融資型」は利子という形でリターンを受け取ります。「購入型」はモノやサービス、あるいは権利という形でリターンを受け取ります。
必ずどれか一つのタイプに当てはまるわけではなく、組み合わせることも可能です。
「Readyfor Charity」は国内最大規模です。「All or Nothing」を採用しており、募集期間中に目標金額を超えた場合のみ、プロジェクト成立となります。目標達成できなかった場合は資金を受け取ることができません。その場合はもちろん、手数料もかかりません。手数料はクラウドファンディング経験者向けのシンプルプランが設定額の12パーセント、未経験者向けのフルサポートプランは17パーセントとなっています。
「All or Nothing」の逆が「All in」です。目標金額以上の支援が集まったかどうかに関わらず、プロジェクトは成立します。
映画やアートに特化したクラウドファンディングもあります。例えば「MotionGalley」です。ここからカンヌ国際映画祭への出品作品も誕生しています。支援者は映画のチケットやDVDをリターンとして受け取ることができます。
大手新聞社の朝日新聞も「A-port」という寄付型・購入型のクラウドファンディングを運営しています。
「投資型」は、未上場企業の株に投資できる「株式投資型」なら「エメラダ・エクイティ」や「FUNDINNO」、特定の事業に投資を行って分配金という形でリターンが受け取る「ファンド型投資」なら「セキュリテ」がよく知られています。
ファンドのジャンルは多岐に渡ります。例えば「セキュリテ」には、熊本県にある南阿蘇水力発電株式会社の小水力発電事業を支援する「南阿蘇水力発電 熊本地震復興支援ファンド」、株式会社富樫縫製の腰痛軽減や姿勢矯正、農業や漁業・介護関係者の作業負担を軽減する「サポートスーツファンド」などが掲載されています。
プロジェクトの起案者にもリスクはあります。例えば、起案したプロジェクトがウェブ上から消えないため、失敗した場合に傷痕を残すことになります。
とは言え、需要はどんどん高まっています。それだけメリットを感じている人が多いということです。矢野経済研究所は、年々拡大する国内クラウドファンディングの新規プロジェクト支援額の推移を示したうえで、「今後さらに国内クラウドファンディング市場は拡大する見込みである」と結論づけています。
市場の拡大、年数の経過とともにデメリットも軽減されていくことでしょう。お金の集め方と使い方が変化していくということは経済や産業の構造そのものを変える可能性があるということです。クラウドファンディングの動向にはこれからも目が離せません。
クラウドファンディングと一口に言っても種類はさまざまで、その中身をきちんと理解している人はそう多くありません。クラウドファンディングとは何か、デメリットも含め、できるだけわかりやすく解説します。
4つのタイプ
クラウドファンディングには大きく4つのタイプがあります。「寄付型」「投資型」「融資型」「購入型」です。「寄付型」はその名の通り、支援者へのリターンはありません。「投資型」は支援したプロジェクトの利益からリターンがあります。投資型はさらにファンド型、株式型に分類されます。投資型が配当という形でリターンを受け取れるのに対して、「融資型」は利子という形でリターンを受け取ります。「購入型」はモノやサービス、あるいは権利という形でリターンを受け取ります。
必ずどれか一つのタイプに当てはまるわけではなく、組み合わせることも可能です。
「All or Nothing」と「All in」
「寄付型」の利用者は認定NPO、自治体、学校など、公益的な活動を行う個人や組織です。例えば、「Readyfor Charity」では「誰もが食事に困らない社会の実現を。より多くの方に食を届けたい」(認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋)、「半世紀にわたる歴博の挑戦!正倉院に残された古代の文書を後世へ」(国立歴史民俗博物館)といった起案者のメッセージのもと、プロジェクトが成立しています。「Readyfor Charity」は国内最大規模です。「All or Nothing」を採用しており、募集期間中に目標金額を超えた場合のみ、プロジェクト成立となります。目標達成できなかった場合は資金を受け取ることができません。その場合はもちろん、手数料もかかりません。手数料はクラウドファンディング経験者向けのシンプルプランが設定額の12パーセント、未経験者向けのフルサポートプランは17パーセントとなっています。
「All or Nothing」の逆が「All in」です。目標金額以上の支援が集まったかどうかに関わらず、プロジェクトは成立します。
購入型でリップや映画チケット
「Readyfor Charity」は「購入型」としてもよく知られており、例えば、ネパールの女性たちの生活を支えるために地域でとれる自然素材を使ったリップバームづくりを実現するプロジェクトでは、3千円の出資者には感謝の手紙、8千円の出資者には発売前のリップバーム、1万円の出資者にはネパール産の毛織布の小銭入れとリップバームが届くなど、最大50万円までたくさんコースなどが用意され、無事にプロジェクトは成立しています。映画やアートに特化したクラウドファンディングもあります。例えば「MotionGalley」です。ここからカンヌ国際映画祭への出品作品も誕生しています。支援者は映画のチケットやDVDをリターンとして受け取ることができます。
大手新聞社の朝日新聞も「A-port」という寄付型・購入型のクラウドファンディングを運営しています。
将来性を見込んで投資する
「融資型」は支援の側面の強い「寄付型」「購入型」とは印象がガラリと変わります。言い換えれば、投資商品です。創立後の年数が浅いなど銀行の融資対象にならない企業などがその対象です。有名どころでは「maneo」、不動産案件に特化した「OwnersBook」、海外案件に特化した「クラウドクレジット」などがあります。「投資型」は、未上場企業の株に投資できる「株式投資型」なら「エメラダ・エクイティ」や「FUNDINNO」、特定の事業に投資を行って分配金という形でリターンが受け取る「ファンド型投資」なら「セキュリテ」がよく知られています。
ファンドのジャンルは多岐に渡ります。例えば「セキュリテ」には、熊本県にある南阿蘇水力発電株式会社の小水力発電事業を支援する「南阿蘇水力発電 熊本地震復興支援ファンド」、株式会社富樫縫製の腰痛軽減や姿勢矯正、農業や漁業・介護関係者の作業負担を軽減する「サポートスーツファンド」などが掲載されています。
デメリットと未来展望
クラウドファンディングのデメリットは、何と言っても出資したプロジェクトが成立するかどうかわからないということです。また、成立したとしても事業が失敗する事もあります。プロジェクトの起案者にもリスクはあります。例えば、起案したプロジェクトがウェブ上から消えないため、失敗した場合に傷痕を残すことになります。
とは言え、需要はどんどん高まっています。それだけメリットを感じている人が多いということです。矢野経済研究所は、年々拡大する国内クラウドファンディングの新規プロジェクト支援額の推移を示したうえで、「今後さらに国内クラウドファンディング市場は拡大する見込みである」と結論づけています。
市場の拡大、年数の経過とともにデメリットも軽減されていくことでしょう。お金の集め方と使い方が変化していくということは経済や産業の構造そのものを変える可能性があるということです。クラウドファンディングの動向にはこれからも目が離せません。
<参考サイト>
・2017年度の国内クラウドファンディング市場規模は新規プロジェクト支援ベースで前年度比127.5%増の1,700億円│矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2036
・2017年度の国内クラウドファンディング市場規模は新規プロジェクト支援ベースで前年度比127.5%増の1,700億円│矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2036
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子
毛繕いを代行!?脳の大型化が可能にしたメンタライジング
長谷川眞理子







