テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
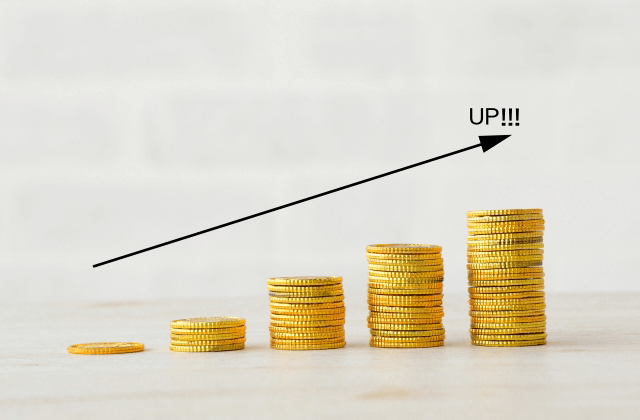
コロナ禍で「貯金が増えた」理由とは?
コロナ前と後では、働き方も生活も大きく変わり、お金の使い方も一変したことでしょう。運輸、観光のように景況が非常にきびしい業界や、他にも雇用を絞り込む企業も少なくありませんが、一方で貯金は増えているという調査結果も出ています。それはいったいなぜなのでしょうか?
要因は様々でしょうが、考えられるのは特別定額給付金を始めとして臨時収入が1つ。そしてある程度生活に余裕がある層にとって何よりも大きいのは、観光やレジャーなど娯楽への出費の機会が制限されているということでしょう。60代の裕福な世帯が旅行を控えたことで貯金が増えた、それの裏返しで冒頭に挙げた運輸、観光業界は苦しんでいる、という構図になるわけです。
auじぶん銀行が行った「コロナ禍におけるお金への意識アンケート」でも、特別定額給付金を何に使ったか、使う予定か、という質問に対して貯金と答えたのは42.7%。支出については「増えた(18.2%)」「とても増えた(2.2%)」と回答した人よりも「減った(30.6%)」「とても減った(5.2%)」と答えた人の方が多いことからも、財布のひもが堅くなっていることがわかります。
コロナを過去の話として語れるようになるのはまだまだ先になるかもしれませんが、ここで変わった消費スタイルが元に戻ることはないかもしれません。財やサービスを提供する側も、“ニューノーマル”を踏まえた商品を売ることが肝になってくることは間違いないでしょう。
60代は503万円から905万円へ貯金が大幅増
クレジットカードのメディアを運営しているリーディングテック株式会社が行った「貯金実態調査2020」によると、貯金額の平均は昨年度の317万円から389万円へアップ。貯金額の中央値は昨年度の100万円から200万円へと変わりました。内訳で見ると100万円未満という回答が43.5%から33.8%へ減り、1000万円以上と答えた層は7.3%から11.5%へと増加しました。100万円未満の回答の詳細を見ても、5万円未満の層は10.2%から6.4%と減っているように、回答者全体で貯金をする傾向が強まっていることが見てとれます。年齢別の貯金額の平均値では、横ばいの20代と微減の50代を除き増加。特に60代は503万円から905万円へと大きく伸ばしています。要因は様々でしょうが、考えられるのは特別定額給付金を始めとして臨時収入が1つ。そしてある程度生活に余裕がある層にとって何よりも大きいのは、観光やレジャーなど娯楽への出費の機会が制限されているということでしょう。60代の裕福な世帯が旅行を控えたことで貯金が増えた、それの裏返しで冒頭に挙げた運輸、観光業界は苦しんでいる、という構図になるわけです。
収入は増え、支出は絞り気味な傾向あり
総務省統計局の家計調査報告を見てみると、2020年4~6月期での消費支出は1世帯あたり前年同期比9.7%減少の264546円。それに対し実収入は1世帯あたり684172円で前年同期比10.1%増(1世帯はともに2人以上の世帯。前年同期比は名目)。実収入が前年より増え支出が絞られているので、貯金が増えるのもうなずける数値でしょう。コロナ前と比べ、より先行きが見えづらい時代に入りつつあることで、できるだけ手元の貯金を確保しておきたい、というマインドになることも理解できます。麻生太郎副総理兼財務相が特別定額給付金について、「(10万円を給付した)その分だけ(個人の)貯金が増えた」と口にして物議をかもしましたが、一面においては正しいとも言えそうです。もちろん10万円をすべて消費に回す義務はないですし、ましてやすぐにすべて使う必要もないのですが。auじぶん銀行が行った「コロナ禍におけるお金への意識アンケート」でも、特別定額給付金を何に使ったか、使う予定か、という質問に対して貯金と答えたのは42.7%。支出については「増えた(18.2%)」「とても増えた(2.2%)」と回答した人よりも「減った(30.6%)」「とても減った(5.2%)」と答えた人の方が多いことからも、財布のひもが堅くなっていることがわかります。
コロナを過去の話として語れるようになるのはまだまだ先になるかもしれませんが、ここで変わった消費スタイルが元に戻ることはないかもしれません。財やサービスを提供する側も、“ニューノーマル”を踏まえた商品を売ることが肝になってくることは間違いないでしょう。
<参考サイト>
・コロナ後の貯金平均は72万円増加し389万円。貯金実態調査2020
https://wiseloan-cash.com/savings2020/
・統計局ホームページ/家計調査報告 ―月・四半期・年―
https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.html#shihanki
・麻生氏「10万円給付分だけ貯金増えた」 効果を疑問視:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASNBS63T7NBSTIPE00Y.html
・ビジネスパーソンのコロナ禍におけるお金への意識調査3人に1人が給与減で、「節約」「貯金を取り崩す」でやりくり。特別定額給付金の使い道は「貯金」「食費」等堅実派が多数。|auじぶん銀行のプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000026860.html
・コロナ後の貯金平均は72万円増加し389万円。貯金実態調査2020
https://wiseloan-cash.com/savings2020/
・統計局ホームページ/家計調査報告 ―月・四半期・年―
https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/index.html#shihanki
・麻生氏「10万円給付分だけ貯金増えた」 効果を疑問視:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASNBS63T7NBSTIPE00Y.html
・ビジネスパーソンのコロナ禍におけるお金への意識調査3人に1人が給与減で、「節約」「貯金を取り崩す」でやりくり。特別定額給付金の使い道は「貯金」「食費」等堅実派が多数。|auじぶん銀行のプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000026860.html
人気の講義ランキングTOP20










