テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
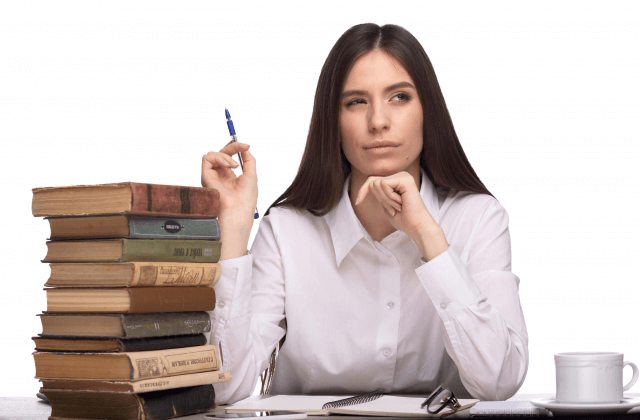
知的に見える話し方とは?
コミュニケーションの主軸ともいえる「話す」において、話す内容はもちろん大切ですが、場合によってはそれ以上に「話し方」が重要となってきます。
なぜなら、「話し方」が下手で話す内容が聴き手に伝わらない以上、たとえいくら話し手が豊かで価値ある話す内容(情報)を持っていたとしても、少なくとも聴き手もしくは話し手と聴き手のコミュニティにとって、意味を成さないからです。
そして、オンラインでのコミュニケーションが増えるなどますます「話し方」の価値が上がる昨今において、技術として「知的に見える話し方」が役立つ場面が増えています。
具体的には、1)背筋を伸ばす、2)肩の力を抜く、3)あごを引く――。つまり、「姿勢」を正してみください。姿勢を正すことによって姿勢が悪いときよりも、“自信がある様子=知的な見た目”となります。また、話す際に大切な発声もよくなります。
一方、聴き手が「自分の話しに何を求めているのか」といった、心持ちとしての「姿勢」を整えることも大切です。聴き手の目的に応じることができなければ、“知的な話”とはなり得ません。
とはいえ後者は、自身の能力や知識の有無、状況や相手との相性などによって、難しい場合も多々あります。そんな場合こそ、まずは前者である体の「姿勢」を正してみてください。そのうえで、心身の「姿勢」と整えてみてください。
話す内容は同じであったとしても、例えば冒頭で最も重要な結論から述べるのか、それとも順を追って説明しつつ締めできっちりとまとめて印象をつけるのか、はたまた中盤に盛り上がりを持ってきて聴き手を飽きさせないようにするのか――、話し方の「構成」によって聴き手の印象は大きく変わります。
上述した“心持ちとしての姿勢”とも関わってきますが、できるかぎり聴き手の状況や真意をくみ取って、話し方を構成してみてください。
例えば、聴き手が急いでいるのであれば結論を先に話すことが親切であり、聴き手にとってもより知的な話し方と見えてくるはずです。
しかし、聴き手が意見を交換しながらゆっくりと話し合いたいと思っているのであれば、あなたの持っている知識を相手の持っている知識と交換しあいつつ話し合いの時間を楽しむことが、知的な話し方と見えてくるでしょう。
一例を挙げれば、「了解しました」→「承知しました」、「すみません」→「恐れ入ります」、「ごめんなさい」→「申し訳ございません」――など、同じ意味でも使う言葉を換える、つまり「言い換え」を試みるだけで、ぐっと印象が変わり、知的に見える話し方となります。
ちなみに、言い換えをよりよく行うためには、語彙が豊富であるほど有利です。そのためにはやはり日頃から、いろいろな語彙に触れて吸収しておく必要があります。
なお、語彙の具体例に、専門用語があります。専門用語を効果的に話の中に取り組むことができれば、聴き手に大いに知的な印象を残すことができます。ただし、繰り返しになりますが「話すことの基本は相手に伝わること」ですから、語彙をむやみに乱用したり、安易に専門用語を使ったりすることが、知的に見える話し方ということではありません。
ですから、「知的」に気を取られるあまり、自身の知識を披露するだけのような話し方は避ける必要があります。聴き手に話しを伝えるためには、相手に応じた「例え」を適宜用いることができると、ぐっと伝わりやすくなります。
豊かな語彙や専門用語で意識付けを行い、そのうえで語彙の背景や専門用語の意味などを相手に応じた例え話で説明することができれば、より知的に見える話し方となるでしょう。
話す内容、話す人、話す機会・・・様々なファクターによって、知的に見える話し方は変わってきます。ということは、誰であってもどんな場合であっても、状況に応じて工夫できるという側面があるともいえます。今回紹介した話し方も一例にすぎませんが、機会があれば試してみても損はありません。ぜひ一考してみてください。
なぜなら、「話し方」が下手で話す内容が聴き手に伝わらない以上、たとえいくら話し手が豊かで価値ある話す内容(情報)を持っていたとしても、少なくとも聴き手もしくは話し手と聴き手のコミュニティにとって、意味を成さないからです。
そして、オンラインでのコミュニケーションが増えるなどますます「話し方」の価値が上がる昨今において、技術として「知的に見える話し方」が役立つ場面が増えています。
「姿勢」を整える
知的に“見える”話し方ですから、まずは聴き手の視覚を大いに利用しましょう。具体的には、1)背筋を伸ばす、2)肩の力を抜く、3)あごを引く――。つまり、「姿勢」を正してみください。姿勢を正すことによって姿勢が悪いときよりも、“自信がある様子=知的な見た目”となります。また、話す際に大切な発声もよくなります。
一方、聴き手が「自分の話しに何を求めているのか」といった、心持ちとしての「姿勢」を整えることも大切です。聴き手の目的に応じることができなければ、“知的な話”とはなり得ません。
とはいえ後者は、自身の能力や知識の有無、状況や相手との相性などによって、難しい場合も多々あります。そんな場合こそ、まずは前者である体の「姿勢」を正してみてください。そのうえで、心身の「姿勢」と整えてみてください。
「構成」に気を配る
次に、話し方の「構成」にも気を配ってみましょう。話す内容は同じであったとしても、例えば冒頭で最も重要な結論から述べるのか、それとも順を追って説明しつつ締めできっちりとまとめて印象をつけるのか、はたまた中盤に盛り上がりを持ってきて聴き手を飽きさせないようにするのか――、話し方の「構成」によって聴き手の印象は大きく変わります。
上述した“心持ちとしての姿勢”とも関わってきますが、できるかぎり聴き手の状況や真意をくみ取って、話し方を構成してみてください。
例えば、聴き手が急いでいるのであれば結論を先に話すことが親切であり、聴き手にとってもより知的な話し方と見えてくるはずです。
しかし、聴き手が意見を交換しながらゆっくりと話し合いたいと思っているのであれば、あなたの持っている知識を相手の持っている知識と交換しあいつつ話し合いの時間を楽しむことが、知的な話し方と見えてくるでしょう。
「言い換え」を試みる
さらに、話し方で知的に“見せる”ためには、話す言葉にも気を配ってほしいと思います。一例を挙げれば、「了解しました」→「承知しました」、「すみません」→「恐れ入ります」、「ごめんなさい」→「申し訳ございません」――など、同じ意味でも使う言葉を換える、つまり「言い換え」を試みるだけで、ぐっと印象が変わり、知的に見える話し方となります。
ちなみに、言い換えをよりよく行うためには、語彙が豊富であるほど有利です。そのためにはやはり日頃から、いろいろな語彙に触れて吸収しておく必要があります。
なお、語彙の具体例に、専門用語があります。専門用語を効果的に話の中に取り組むことができれば、聴き手に大いに知的な印象を残すことができます。ただし、繰り返しになりますが「話すことの基本は相手に伝わること」ですから、語彙をむやみに乱用したり、安易に専門用語を使ったりすることが、知的に見える話し方ということではありません。
「例え」を用いる
ところで、“見える”であっても「知的」が求められる話し方とはいえ、大前提として“話し方”である以上、あくまでも聴き手に話しが伝わらなければ、字義通り、話になりません。ですから、「知的」に気を取られるあまり、自身の知識を披露するだけのような話し方は避ける必要があります。聴き手に話しを伝えるためには、相手に応じた「例え」を適宜用いることができると、ぐっと伝わりやすくなります。
豊かな語彙や専門用語で意識付けを行い、そのうえで語彙の背景や専門用語の意味などを相手に応じた例え話で説明することができれば、より知的に見える話し方となるでしょう。
話す内容、話す人、話す機会・・・様々なファクターによって、知的に見える話し方は変わってきます。ということは、誰であってもどんな場合であっても、状況に応じて工夫できるという側面があるともいえます。今回紹介した話し方も一例にすぎませんが、機会があれば試してみても損はありません。ぜひ一考してみてください。
<参考文献>
・『「言葉にできる人」の話し方』(齋藤孝著、小学館)
・『「きちんとしている」と言われる「話し方」の教科書』(矢野香著、プレジデント社)
・「身だしなみと姿勢」『マナーと常識事典』(『現代用語の基礎知識』2007年版別冊付録、自由国民社)
・『「言葉にできる人」の話し方』(齋藤孝著、小学館)
・『「きちんとしている」と言われる「話し方」の教科書』(矢野香著、プレジデント社)
・「身だしなみと姿勢」『マナーと常識事典』(『現代用語の基礎知識』2007年版別冊付録、自由国民社)
人気の講義ランキングTOP20










