テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
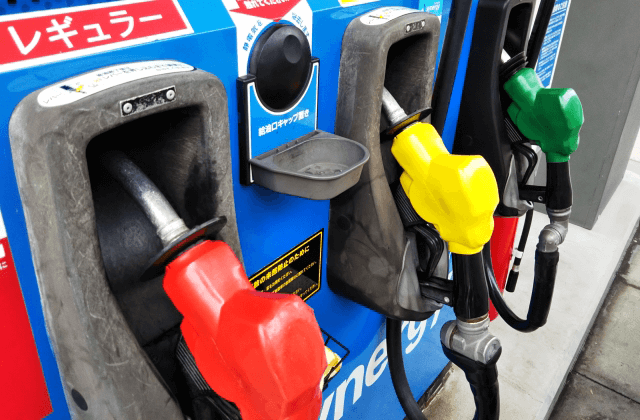
電動化が進むとガソリンスタンドは無くなるの?
温暖化対策の一環として経済産業省は、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定しています。この政策では車の電動化が推し進められ、2035年までに新車として販売される乗用車は全て電動車となるとされています。つまり、車向けのガソリン需要は大きく減ることになります。こうなると、この先十数年後にはガソリンスタンドは不要となるかもしれません。状況を整理してみましょう。
ガソリンスタンドが減った理由としては、ハイブリッド化などによる車の燃費向上がまず挙げられます。また、2010年に公布された消防法改正も関連しているようです。この改正では、設置して40年から50年経過した地下タンクの油漏れや腐食などへの対策をとることが義務付けられました。これにより、古い給油所では1000万円前後の経費が掛かることになったとのこと。こうして個人経営の給油所などを中心に閉店や廃業の動きが起こりました。こういったガソリンをめぐる環境の大きな変化がここ10年ほどの間に起こっていることが、ガソリンスタンド減少の理由です。さらにこの先、電動車が増えれば需要がさらに細ることは言うまでもありません。
つまりハイブリッド化などによるガソリン需要の減少と法改正が、ガソリンスタンド減少の大きな要因です。すでに自宅からガソリンスタンドまでが遠い、「給油難民」が出始めているようです。特に地方で多いようですが、これは都市部のユーザーにとっても無関係ではありません。旅行やビジネスで地方に出かけた際は、計画的な給油を想定しておかないと苦労することが想定されます。
日産リーフの62kWhバッテリーを搭載したタイプだと、一度の充電で理論上458km走ることができます(WLTCモードでの航続距離)。この日産リーフの場合、一般的な急速充電設備で充電するのに必要な時間は60分です。急速充電とは街にある一般的な充電器のことです。また急速充電でもより一度に多く充電できる大容量タイプであったとしても、一般的な車種で空に近い状態の電池を80%まで充電するのには、15分から30分程度が必要とされています。
つまり、5分程度で終了するガソリンの給油よりも格段に長い時間がかかり、スタンドの回転は悪くなります。もちろん複数設置するにはコストがかさみます。また、現在の充電スタンドはコンビニやスーパー、ファミレスの駐車場などにも設置されています。このように何かのついでに駐車した時に充電する方がはるかに効率的です。つまり、電気はガソリンとは異なり、わざわざそのためにスタンドに出向いて補給する必要があまりありません。ガソリンスタンドが充電スタンドのみに転換しても、これまでのガソリン補給と同様に集客できるようにはならないのです。
「給油難民」が今後は増えてくる
ガソリンスタンドは年々減少しています。ガソリンスタンド数は1994年がピークで、この時には全国に6万店強ありました。しかし、ここから25年連続で減少し、2020年3月末時点での数は3万店弱。およそ半分になっています。さらに2020年以降はコロナ禍などによる影響もあり減少が加速しているようです。また、ここ数年ではガソリンスタンドからコンビニエンスストアなどへの経営転換や多角化も見られるとのことです。ガソリンスタンドが減った理由としては、ハイブリッド化などによる車の燃費向上がまず挙げられます。また、2010年に公布された消防法改正も関連しているようです。この改正では、設置して40年から50年経過した地下タンクの油漏れや腐食などへの対策をとることが義務付けられました。これにより、古い給油所では1000万円前後の経費が掛かることになったとのこと。こうして個人経営の給油所などを中心に閉店や廃業の動きが起こりました。こういったガソリンをめぐる環境の大きな変化がここ10年ほどの間に起こっていることが、ガソリンスタンド減少の理由です。さらにこの先、電動車が増えれば需要がさらに細ることは言うまでもありません。
つまりハイブリッド化などによるガソリン需要の減少と法改正が、ガソリンスタンド減少の大きな要因です。すでに自宅からガソリンスタンドまでが遠い、「給油難民」が出始めているようです。特に地方で多いようですが、これは都市部のユーザーにとっても無関係ではありません。旅行やビジネスで地方に出かけた際は、計画的な給油を想定しておかないと苦労することが想定されます。
ガソリンスタンドは充電スタンドには転換しにくい
電動車が増えれば、必要なのは充電スタンドです。そうと分かれば、今のガソリンスタンドに充電設備を設置し、そのまま充電スタンドに置き換われば問題はないようにも思われます。しかし、ここには充電にかかる時間の問題と、さまざまな場所で可能であるという自由さの問題が関係しています。日産リーフの62kWhバッテリーを搭載したタイプだと、一度の充電で理論上458km走ることができます(WLTCモードでの航続距離)。この日産リーフの場合、一般的な急速充電設備で充電するのに必要な時間は60分です。急速充電とは街にある一般的な充電器のことです。また急速充電でもより一度に多く充電できる大容量タイプであったとしても、一般的な車種で空に近い状態の電池を80%まで充電するのには、15分から30分程度が必要とされています。
つまり、5分程度で終了するガソリンの給油よりも格段に長い時間がかかり、スタンドの回転は悪くなります。もちろん複数設置するにはコストがかさみます。また、現在の充電スタンドはコンビニやスーパー、ファミレスの駐車場などにも設置されています。このように何かのついでに駐車した時に充電する方がはるかに効率的です。つまり、電気はガソリンとは異なり、わざわざそのためにスタンドに出向いて補給する必要があまりありません。ガソリンスタンドが充電スタンドのみに転換しても、これまでのガソリン補給と同様に集客できるようにはならないのです。
業態転換は必須
ガソリンスタンドが減っていくとガソリン車は不便になり、より電動車の需要が伸びます。またこのことでガソリンスタンドの需要は減ります。この循環から考えると、ガソリンスタンドはさらに減少していくと思われます。この先、都市部のガソリンスタンドであれば土地を生かしてビルを建てるなど不動産経営にシフトすることは考えられます。また郊外や地方の場合、ガソリンスタンドから総合的な「サービスステーション」として、つまり車の充電からメンテナンス、清掃や点検までを行う場所として生き残る道はありうるかもしれません。<参考サイト>
2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略|経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/index.html
[Q] 急速充電と普通充電の違いは? 急速充電の大容量/中容量とは?|JAF
https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-construction/subcategory-eco-car/faq045
電気自動車、日産リーフ。充電方法|NISSAN
https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/leaf/charge/charge.html
2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略|経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/index.html
[Q] 急速充電と普通充電の違いは? 急速充電の大容量/中容量とは?|JAF
https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-construction/subcategory-eco-car/faq045
電気自動車、日産リーフ。充電方法|NISSAN
https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/leaf/charge/charge.html
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
昭和陸軍の派閥抗争には三つの要因があった
中西輝政










