テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
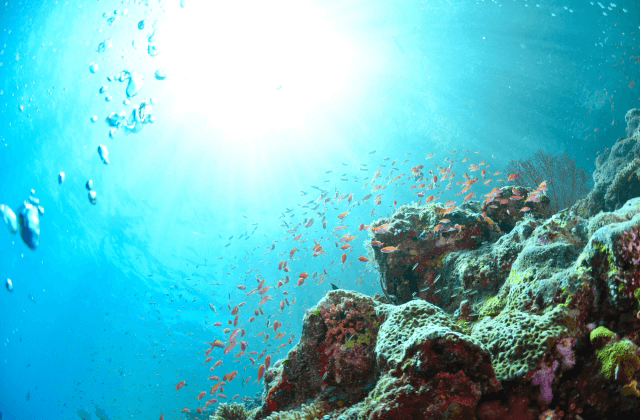
全長180キロ!世界最大の「植物」とは
2022年6月1日付けの科学雑誌『Royal Society B: Biological Sciences(英国王立協会紀要B:生物科学)』にて、オーストラリアのシャーク湾で発見された全長180キロの世界最大の「植物」が発表されました。
世界最大の「植物」は海草の一種で、名前は「ポシドニア・オーストラリス」といいます。規模と成長速度から約4500年前に誕生したと推定されており、そして今なお成長し続けています。
海草藻場に何種類の植物が生育しているかを知るためには、海草藻場中の植物のDNAを調べる必要があります。そこで研究チームは、2012年と2019年にシャーク湾全域から計10カ所を選び、「ポシドニア・オーストラリス」の試料144点を採取し、全サンプルから合計1万8021件の遺伝子マーカーを解析しました。
その結果、「ポシドニア・オーストラリス」の遺伝子マーカーはすべてが同じで単一の種類であること、1本の「ポシドニア・オーストラリス」が180平方キロに広がるリボン状の海草藻場になっていることが発見されたのです。
しかし、こうした有性生殖とは別に、多くの植物と異なる「ポシドニア・オーストラリス」の大きな特徴に、染色体の数が通常の植物の2倍であることが挙げられます(専門家は「倍数体」と呼びます)。
一般的に有性生殖(オスとメスの交配)の植物は両親から半分ずつ染色体をもらい、2本対になった「二倍体」の形をとります。ところが、「ポシドニア・オーストラリス」のような倍数体は、両親から全ゲノムを受け継ぎ複製(クローン)によって成長していきます。そのため、受け取る染色体数が有性生殖の2倍となります。
また、倍数体の植物は、繁殖能力を持たない(不稔)であることが多くなります。事実、「ポシドニア・オーストラリス」も開花するもののほとんど結実しないそうです。そして、極限環境でもしばしば生息し、さらに環境が許す限り成長(クローンによって無限に増殖)していくと考えられています。ただし、クローン増殖は遺伝的多様性に乏しく、環境変化に対して脆弱になりやすい傾向があります。
ちなみに、「ポシドニア・オーストラリス」は、地中に向かって茎を伸ばすことによって(地下茎の伸長によって)増殖していきます。そして、伸ばされた茎から根や芽が出て成長し、新たなクローンが生み出されます。そのようにして、4500年かけて勢力を拡大していきました。
現在はエビ漁などの漁業と製塩が行われ、またジュゴン・バンドウイルカ・ジンベイザメなどが生息し、湾奥のハメリンプールでは“生きた化石”と称されるストロマトライトが現生するなど、生物多様性に富んだ環境です。また、1991年にユネスコ(UNESCO)の世界自然遺産に登録されています。
しかしながら、シャーク湾は、(1)海水中の栄養レベルが低い、(2)海草のストレスとなる水中の光量が多い、(3)温帯と熱帯の境界に位置するため、極端な気候変動や海洋熱波、サイクロンといった異常気象にさらされる、(4)干潟の塩分濃度が高い(ハメリンプールなど塩分濃度が通常の2倍になる場所もある)、(5)年間の海水温変動が大きい(冬の17度~夏の30度まで幅がある)――など、植物の生存環境としては厳しいものとなっています。
ここでまた疑問が出てきます。環境変化に対して脆弱なクローン増殖の「ポシドニア・オーストラリス」が、なぜシャーク湾のよう変化の激しい厳しい生存環境で、これほど大規模にクローン増殖できたのでしょうか。
この疑問に対して研究チームは、「それぞれのクローンの細胞にわずかな体細胞の突然変異(子孫に受け継がれない程度の小さな遺伝的変化)が起き、それぞれの場所ごとの環境変化に適応しているのではないか」という仮説を提起しています。
つまり、「ポシドニア・オーストラリス」は、シャーク湾という過酷な環境で長期的に生存しつつ広大に成長するために、極限環境に強い倍数体の特性を生かしつつ、局所的な多様性を生むという生存戦略によって、生き残り成長し続けているといえるのではないでしょうか。
他にも比較すると、日本で2番目に大きい湖である霞ヶ浦の面積が約168平方キロ、日本で15番目に大きい島である利尻島の面積が約182平方キロと同じくらいの大きさです。さらに市町村では、茨城県桜川市(180.1平方キロ)とほぼ同じ大きさとなります。
他方、4500年前の時間の長さを人類史に照らし合わせてみると、メソポタミアではシュメール都市国家、エジプトはピラミッド時代ともいわれる古王国時代、中国では三皇五帝の神話時代、またインダス文明・エーゲ文明・初期ミノア文明など、各地の古代文明が栄えた頃でした。そして、日本は縄文時代後期にあたります。
活発に光合成を行って酸素を放出し、さまざまな生物の安全な生息地であり、かつ水質を浄化し、さらに海底の砂を安定させるはたらきももつ藻場(海草藻場を含む)は、生態系で重要な役割を担っています。しかしながら、開発や環境変化によって、減少や機能低下の一途をたどっています。連綿と生き続けてきた貴重な植物たちの環境を守ることが、今日的かつ長期的な重要課題となっています。
世界最大の「植物」は海草の一種で、名前は「ポシドニア・オーストラリス」といいます。規模と成長速度から約4500年前に誕生したと推定されており、そして今なお成長し続けています。
世界最大の「植物」はどうして発見されたの?
世界最大の「植物」はどうして発見されたのでしょうか。事の起こりは、西オーストラリア大学とフリンダース大学の研究チームが、シャーク湾の海草藻場(かいそうもば:海底で海草が群落状に生育している場所)の遺伝的多様性を調査する取り組みから始まりました。海草藻場に何種類の植物が生育しているかを知るためには、海草藻場中の植物のDNAを調べる必要があります。そこで研究チームは、2012年と2019年にシャーク湾全域から計10カ所を選び、「ポシドニア・オーストラリス」の試料144点を採取し、全サンプルから合計1万8021件の遺伝子マーカーを解析しました。
その結果、「ポシドニア・オーストラリス」の遺伝子マーカーはすべてが同じで単一の種類であること、1本の「ポシドニア・オーストラリス」が180平方キロに広がるリボン状の海草藻場になっていることが発見されたのです。
世界最大の「植物」はどんな植物?
ポシドニア属に属する「ポシドニア・オーストラリス」は、前述したように海草の一種です。つまり、海藻(藻類)ではなく、種子植物です。海草はもともと陸上の草だったと考えられており、海中で花を咲かせて種子を作ります。しかし、こうした有性生殖とは別に、多くの植物と異なる「ポシドニア・オーストラリス」の大きな特徴に、染色体の数が通常の植物の2倍であることが挙げられます(専門家は「倍数体」と呼びます)。
一般的に有性生殖(オスとメスの交配)の植物は両親から半分ずつ染色体をもらい、2本対になった「二倍体」の形をとります。ところが、「ポシドニア・オーストラリス」のような倍数体は、両親から全ゲノムを受け継ぎ複製(クローン)によって成長していきます。そのため、受け取る染色体数が有性生殖の2倍となります。
また、倍数体の植物は、繁殖能力を持たない(不稔)であることが多くなります。事実、「ポシドニア・オーストラリス」も開花するもののほとんど結実しないそうです。そして、極限環境でもしばしば生息し、さらに環境が許す限り成長(クローンによって無限に増殖)していくと考えられています。ただし、クローン増殖は遺伝的多様性に乏しく、環境変化に対して脆弱になりやすい傾向があります。
ちなみに、「ポシドニア・オーストラリス」は、地中に向かって茎を伸ばすことによって(地下茎の伸長によって)増殖していきます。そして、伸ばされた茎から根や芽が出て成長し、新たなクローンが生み出されます。そのようにして、4500年かけて勢力を拡大していきました。
過酷なシャーク湾での生存戦略とは?
「ポシドニア・オーストラリス」が発見されたシャーク湾は、オーストラリア西海岸中央部にある湾です。最終氷期後に海面が上昇した8500年前頃に形成されたとされ、半島と島に囲まれ二つの湾入に分かれた湾には、水深2メートル程度の浅海が広がっています。現在はエビ漁などの漁業と製塩が行われ、またジュゴン・バンドウイルカ・ジンベイザメなどが生息し、湾奥のハメリンプールでは“生きた化石”と称されるストロマトライトが現生するなど、生物多様性に富んだ環境です。また、1991年にユネスコ(UNESCO)の世界自然遺産に登録されています。
しかしながら、シャーク湾は、(1)海水中の栄養レベルが低い、(2)海草のストレスとなる水中の光量が多い、(3)温帯と熱帯の境界に位置するため、極端な気候変動や海洋熱波、サイクロンといった異常気象にさらされる、(4)干潟の塩分濃度が高い(ハメリンプールなど塩分濃度が通常の2倍になる場所もある)、(5)年間の海水温変動が大きい(冬の17度~夏の30度まで幅がある)――など、植物の生存環境としては厳しいものとなっています。
ここでまた疑問が出てきます。環境変化に対して脆弱なクローン増殖の「ポシドニア・オーストラリス」が、なぜシャーク湾のよう変化の激しい厳しい生存環境で、これほど大規模にクローン増殖できたのでしょうか。
この疑問に対して研究チームは、「それぞれのクローンの細胞にわずかな体細胞の突然変異(子孫に受け継がれない程度の小さな遺伝的変化)が起き、それぞれの場所ごとの環境変化に適応しているのではないか」という仮説を提起しています。
つまり、「ポシドニア・オーストラリス」は、シャーク湾という過酷な環境で長期的に生存しつつ広大に成長するために、極限環境に強い倍数体の特性を生かしつつ、局所的な多様性を生むという生存戦略によって、生き残り成長し続けているといえるのではないでしょうか。
180平方キロのサイズと4500年前の人類史
ところで、180平方キロの大きさをイメージすることはできるでしょうか。180平方キロは、東京ドーム約3850個分に相当しますが、東京ドームが多すぎて、かえってイメージしづらいかもしれません。他にも比較すると、日本で2番目に大きい湖である霞ヶ浦の面積が約168平方キロ、日本で15番目に大きい島である利尻島の面積が約182平方キロと同じくらいの大きさです。さらに市町村では、茨城県桜川市(180.1平方キロ)とほぼ同じ大きさとなります。
他方、4500年前の時間の長さを人類史に照らし合わせてみると、メソポタミアではシュメール都市国家、エジプトはピラミッド時代ともいわれる古王国時代、中国では三皇五帝の神話時代、またインダス文明・エーゲ文明・初期ミノア文明など、各地の古代文明が栄えた頃でした。そして、日本は縄文時代後期にあたります。
活発に光合成を行って酸素を放出し、さまざまな生物の安全な生息地であり、かつ水質を浄化し、さらに海底の砂を安定させるはたらきももつ藻場(海草藻場を含む)は、生態系で重要な役割を担っています。しかしながら、開発や環境変化によって、減少や機能低下の一途をたどっています。連綿と生き続けてきた貴重な植物たちの環境を守ることが、今日的かつ長期的な重要課題となっています。
<参考文献・参考サイト>
・『デジタル大辞泉』(小学館)
・『日本大百科全書』(小学館)
・180キロ以上に広がる世界最大の植物が発見される│Newsweek
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/06/180-6_1.php
・世界最大の植物、豪シャーク湾で発見 4500年かけ180キロにわたり拡大か│BBC NEWS
https://www.bbc.com/japanese/61658354
・海草藻場│水産庁
https://www.mozukukyo.org/uploads/e897bbe5a0b4e38391e383b3e38395e383ace38383e38388.pdf
・藻場の働きと現状│水産庁
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/tamenteki/kaisetu/moba/moba_genjou/
・『デジタル大辞泉』(小学館)
・『日本大百科全書』(小学館)
・180キロ以上に広がる世界最大の植物が発見される│Newsweek
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/06/180-6_1.php
・世界最大の植物、豪シャーク湾で発見 4500年かけ180キロにわたり拡大か│BBC NEWS
https://www.bbc.com/japanese/61658354
・海草藻場│水産庁
https://www.mozukukyo.org/uploads/e897bbe5a0b4e38391e383b3e38395e383ace38383e38388.pdf
・藻場の働きと現状│水産庁
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/tamenteki/kaisetu/moba/moba_genjou/
人気の講義ランキングTOP20
高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?
テンミニッツ・アカデミー編集部










