テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
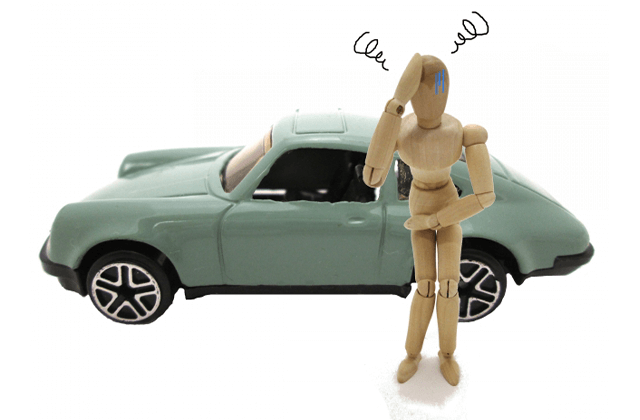
人はなぜ乗り物に酔うのか?原因と対策
旅行や遠出など楽しいイベントがあると心躍りますが、乗り物酔いしやすい人にとっては車での移動は気が重い…という人もいるでしょう。そもそもなぜ乗り物酔いが起こってしまうのか、予防する方法や気を付けるべきポイントは何なのかを調べてみました。
私たちの耳には三半規管や耳石器という器官があり、平衡感覚をつかさどる役割を果たしています。乗り物に乗る時は通常時と異なり、不規則な上下左右の揺れや急停車の繰り返しにより、これらの器官から通常よりも多くの情報が脳に伝えられます。ちなみに、乗り物に乗っている時には移動速度も早くなるため、目から得られる情報もいつもより多くなりますよね。つまり、乗り物に乗ることで脳には目、耳からの情報量がいきなり増えてしまうため、処理できなくなり、自律神経の働きを低下させてしまうのです。
自律神経は血圧や呼吸、胃腸の働きをコントロールしているので、これらの働きが低下すると顔面蒼白や眠気、あくび、そして吐き気や嘔吐の症状が引き起こされます。これが、乗り物酔いが起こるメカニズムとなっているのです。
乗り物に乗る前にできる予防法としては、体調を万全に整えておくことが第一にあげられます。体調不良や寝不足は自律神経の働きを乱す原因になりますし、空腹や満腹の状態も乗り物酔いを引き起こしやすくしてしまいます。
乗り物に乗る時には、脳への情報量が増えすぎないように気を付けましょう。三半規管や耳石器を刺激しないために揺れが激しいタイヤの近くの席は避ける、速いスピードで移り変わる景色を追いかけると目が疲れてしまうので遠くの景色を見るようにするといったことも予防になります。また、乗り物に揺られながらスマホの画面や本を見続けるのも、眼球が不規則な動きになってしまうため、乗り物酔いの原因になることも。負担を減らすためにも、乗り物に酔いやすい人は避けた方が良いでしょう。
また、乗り物酔いしたくないと思いすぎてプレッシャーを感じていると、それが乗り物酔いの原因になることもあります。不安な場合には酔い止めをあらかじめ飲んでおくだけでなく、しめつけの少ないゆったりした服装を選んだり、おしゃべりをして気を紛らすといった、リラックスできるようにしておくのも効果的です。
渋滞に巻き込まれているなど、乗り物から降りるのが難しい場合には座席を倒すなどリラックスできる状況を作るのが良いでしょう。目をつむって深く深呼吸するだけでも脳を休ませることができます。また、腕の内側、手首のしわからひじ側へ指3本分の場所にある内関など、乗り物酔いに効くツボもあるので、自分でツボを押してみるのも良いでしょう。
乗り物酔いのメカニズムがわかることで、とるべき対策もお分かりいただけたのではないでしょうか。まずは乗る前に体調を整えるところから、ぜひ実践してみてください。
乗り物酔いのメカニズム
乗り物酔いには、目や耳、脳が大きく関係していて、自律神経の働きが乱れることによって引き起こされます。私たちの耳には三半規管や耳石器という器官があり、平衡感覚をつかさどる役割を果たしています。乗り物に乗る時は通常時と異なり、不規則な上下左右の揺れや急停車の繰り返しにより、これらの器官から通常よりも多くの情報が脳に伝えられます。ちなみに、乗り物に乗っている時には移動速度も早くなるため、目から得られる情報もいつもより多くなりますよね。つまり、乗り物に乗ることで脳には目、耳からの情報量がいきなり増えてしまうため、処理できなくなり、自律神経の働きを低下させてしまうのです。
自律神経は血圧や呼吸、胃腸の働きをコントロールしているので、これらの働きが低下すると顔面蒼白や眠気、あくび、そして吐き気や嘔吐の症状が引き起こされます。これが、乗り物酔いが起こるメカニズムとなっているのです。
酔わないための予防法
乗り物酔いを起こさないためには、乗る前と乗っている時に対策をとることが大切です。乗り物に乗る前にできる予防法としては、体調を万全に整えておくことが第一にあげられます。体調不良や寝不足は自律神経の働きを乱す原因になりますし、空腹や満腹の状態も乗り物酔いを引き起こしやすくしてしまいます。
乗り物に乗る時には、脳への情報量が増えすぎないように気を付けましょう。三半規管や耳石器を刺激しないために揺れが激しいタイヤの近くの席は避ける、速いスピードで移り変わる景色を追いかけると目が疲れてしまうので遠くの景色を見るようにするといったことも予防になります。また、乗り物に揺られながらスマホの画面や本を見続けるのも、眼球が不規則な動きになってしまうため、乗り物酔いの原因になることも。負担を減らすためにも、乗り物に酔いやすい人は避けた方が良いでしょう。
また、乗り物酔いしたくないと思いすぎてプレッシャーを感じていると、それが乗り物酔いの原因になることもあります。不安な場合には酔い止めをあらかじめ飲んでおくだけでなく、しめつけの少ないゆったりした服装を選んだり、おしゃべりをして気を紛らすといった、リラックスできるようにしておくのも効果的です。
乗り物酔いしてしまったときには
対策をしていてもその時の体調や乗り物の揺れ具合によって乗り物酔いしてしまうことはありますよね。その場合、一番良いのは乗り物から降りて休憩することです。脳が混乱する原因を取り除くこともできますし、外の空気を吸うことでリラックスできます。渋滞に巻き込まれているなど、乗り物から降りるのが難しい場合には座席を倒すなどリラックスできる状況を作るのが良いでしょう。目をつむって深く深呼吸するだけでも脳を休ませることができます。また、腕の内側、手首のしわからひじ側へ指3本分の場所にある内関など、乗り物酔いに効くツボもあるので、自分でツボを押してみるのも良いでしょう。
乗り物酔いのメカニズムがわかることで、とるべき対策もお分かりいただけたのではないでしょうか。まずは乗る前に体調を整えるところから、ぜひ実践してみてください。
人気の講義ランキングTOP20










