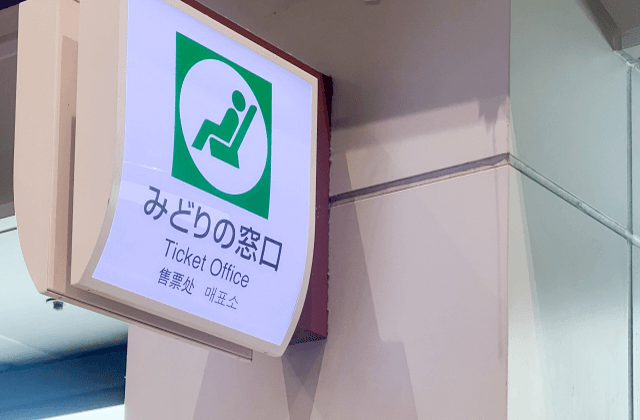
「みどりの窓口」はなぜ「緑」なのか
JRの駅に設置されている「みどりの窓口」では、どんな業務を行っているのでしょうか。なんとなく、「遠方に出かけるときに利用する窓口」というイメージがありますが、具体的には主に次のような業務を担当しています。
・鉄道乗車券の発売、変更および払い戻し
・レンタカー券の発売、変更および払い戻し
・宿泊券の発売、変更および払い戻し
レンタカー券や宿泊券は基本的にJRの利用とセットで取り扱っている商品で、このほかにも航空券や旅行のパック商品などの受け渡しができます。このようにいろいろな業務を行っているみどりの窓口ですが、なんといってもJRグループが発売しているすべての乗車券を購入できるので、ほとんどの場合は鉄道乗車券の購入で訪れることになります。このため、旅行や出張のときに利用することが多くなり、「遠方に出かけるときに利用する窓口」というイメージにつながりやすいのですね。
この窓口が「みどり」と名づけられた理由は、通常の切符の券面が赤や青であることに対して、みどりの窓口で発券した切符は券面が緑だから。これは、「マルス端末」という機械で発券した切符の特徴です。マルス端末とは「Multi Access seat Reservation System」の略称で、JRグループ内で共通して使用されている、座席予約のためのコンピューターシステム。つまり、マルス端末の導入がみどりの窓口のはじまりというわけです。
1・利用者が指定券の発売を各駅の窓口で申し込む。
2・窓口の担当者が管理センターに電話で問い合わせる。
3・管理センターの担当者が台帳で空席を照会する。
4・空席がある場合、窓口の担当者が切符に車両や座席を手書きで書いて利用者に渡す。
5・管理センターの担当者が台帳に発売完了のチェックをつける。
こうしてやっと、座席指定券が買えたのです。この方法では手間がかかるうえに、聞き取りミスやキャンセルのチェック忘れなどによって同じ席の切符を重複して発売してしまうこともありました。また、1964(昭和44年)年には新幹線が開通したこともあり、窓口の業務負担はさらに増していました。このためマルス端末が導入され、みどりの窓口が開設されたのです。すでに60年近い歴史があるのですね。
実は、JRグループ内で東海地方を担当するJR東海は、みどりの窓口という名称を使っていません。このため、東海地方に住む方たちにはあまりなじみがない呼び方なのです。JR東海でもマルス端末は使用していますが、みどりの窓口の役割を果たす窓口は「JR全線きっぷうりば」という名称になっています。JR東海がこのようにしている主な理由は、現在はみどりの窓口に限らず駅の窓口ならどこでも座席指定券が購入できるからなのだとか。また、JR全線きっぷうりばという名称のほうが、どんな業務を行っているのかわかりやすいという理由もあるそうです。
そしてもうひとつ、他のJRグループと見分けがつきやすいという理由もあります。JRグループは現在、北海道・東北・東日本・東海・西日本・四国・九州の6つの旅客鉄道と1つの貨物鉄道の7グループに分かれていますが、もともとは国営の日本国有鉄道というひとつのグループでした。これが1987(昭和62)年に民営化されて、7つに分かれた経緯があります。JR東海は東日本と西日本の間に位置しているので、たとえば東京駅は東海と東日本、新大阪駅は東海と西日本のように、ふたつのグループの窓口があります。そこでJR東海は、他のJRと見分けやすいように窓口の名前を変えているのです。
しかし最近は、JRグループ全体でみどりの窓口を減らす方向に動いています。大きな要因は、ネットでの乗車券購入が普及して有人窓口の利用客が大きく減少しているから。また、座席指定券や特急券を購入できる高性能の自動券売機「みどりの券売機」が導入されたことも理由のひとつです。JR西日本では高性能自動券売機の導入を進めて、みどりの窓口を順次終了する方針を発表しています。乗車券の発売方法も、時代に合わせて日々変化しているのですね。
・鉄道乗車券の発売、変更および払い戻し
・レンタカー券の発売、変更および払い戻し
・宿泊券の発売、変更および払い戻し
レンタカー券や宿泊券は基本的にJRの利用とセットで取り扱っている商品で、このほかにも航空券や旅行のパック商品などの受け渡しができます。このようにいろいろな業務を行っているみどりの窓口ですが、なんといってもJRグループが発売しているすべての乗車券を購入できるので、ほとんどの場合は鉄道乗車券の購入で訪れることになります。このため、旅行や出張のときに利用することが多くなり、「遠方に出かけるときに利用する窓口」というイメージにつながりやすいのですね。
この窓口が「みどり」と名づけられた理由は、通常の切符の券面が赤や青であることに対して、みどりの窓口で発券した切符は券面が緑だから。これは、「マルス端末」という機械で発券した切符の特徴です。マルス端末とは「Multi Access seat Reservation System」の略称で、JRグループ内で共通して使用されている、座席予約のためのコンピューターシステム。つまり、マルス端末の導入がみどりの窓口のはじまりというわけです。
「みどりの窓口」はいつからある?
マルス端末の本格的な導入は、1965(昭和45)年のこと。この年からみどりの窓口が各駅に設置されるようになりました。それ以前の座席指定券は、なんと指定席管理センターの台帳を使って手作業で発売されていました。発売の手順は次のようになります。1・利用者が指定券の発売を各駅の窓口で申し込む。
2・窓口の担当者が管理センターに電話で問い合わせる。
3・管理センターの担当者が台帳で空席を照会する。
4・空席がある場合、窓口の担当者が切符に車両や座席を手書きで書いて利用者に渡す。
5・管理センターの担当者が台帳に発売完了のチェックをつける。
こうしてやっと、座席指定券が買えたのです。この方法では手間がかかるうえに、聞き取りミスやキャンセルのチェック忘れなどによって同じ席の切符を重複して発売してしまうこともありました。また、1964(昭和44年)年には新幹線が開通したこともあり、窓口の業務負担はさらに増していました。このためマルス端末が導入され、みどりの窓口が開設されたのです。すでに60年近い歴史があるのですね。
消えていく「みどりの窓口」
マルス端末の登場でJRの座席指定券はよりスピーディに、より正確に購入できるようになりました。しかし、なかには「みどりの窓口ってなに?」とか「聞いたことはあるけど見たことはない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、JRグループ内で東海地方を担当するJR東海は、みどりの窓口という名称を使っていません。このため、東海地方に住む方たちにはあまりなじみがない呼び方なのです。JR東海でもマルス端末は使用していますが、みどりの窓口の役割を果たす窓口は「JR全線きっぷうりば」という名称になっています。JR東海がこのようにしている主な理由は、現在はみどりの窓口に限らず駅の窓口ならどこでも座席指定券が購入できるからなのだとか。また、JR全線きっぷうりばという名称のほうが、どんな業務を行っているのかわかりやすいという理由もあるそうです。
そしてもうひとつ、他のJRグループと見分けがつきやすいという理由もあります。JRグループは現在、北海道・東北・東日本・東海・西日本・四国・九州の6つの旅客鉄道と1つの貨物鉄道の7グループに分かれていますが、もともとは国営の日本国有鉄道というひとつのグループでした。これが1987(昭和62)年に民営化されて、7つに分かれた経緯があります。JR東海は東日本と西日本の間に位置しているので、たとえば東京駅は東海と東日本、新大阪駅は東海と西日本のように、ふたつのグループの窓口があります。そこでJR東海は、他のJRと見分けやすいように窓口の名前を変えているのです。
しかし最近は、JRグループ全体でみどりの窓口を減らす方向に動いています。大きな要因は、ネットでの乗車券購入が普及して有人窓口の利用客が大きく減少しているから。また、座席指定券や特急券を購入できる高性能の自動券売機「みどりの券売機」が導入されたことも理由のひとつです。JR西日本では高性能自動券売機の導入を進めて、みどりの窓口を順次終了する方針を発表しています。乗車券の発売方法も、時代に合わせて日々変化しているのですね。
<参考サイト>
・東洋経済オンライン なぜJR東海の駅に「みどりの窓口」はないのか
https://toyokeizai.net/articles/-/114181
・Oggi.jp 知ったら話したくなる!「みどりの窓口」はなぜ「みどり」? ない駅もある?
https://oggi.jp/6402173
・CHANTO WEB JRの「みどりの窓口」って何ができる場所か説明できますか?
https://chanto.jp.net/articles/-/93692?display=b
・ねとらぼ みどりの窓口って、なんで「みどり」なの?
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1812/20/news016.html
・東洋経済オンライン なぜJR東海の駅に「みどりの窓口」はないのか
https://toyokeizai.net/articles/-/114181
・Oggi.jp 知ったら話したくなる!「みどりの窓口」はなぜ「みどり」? ない駅もある?
https://oggi.jp/6402173
・CHANTO WEB JRの「みどりの窓口」って何ができる場所か説明できますか?
https://chanto.jp.net/articles/-/93692?display=b
・ねとらぼ みどりの窓口って、なんで「みどり」なの?
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1812/20/news016.html
人気の講義ランキングTOP20
欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い
長谷川眞理子







