テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
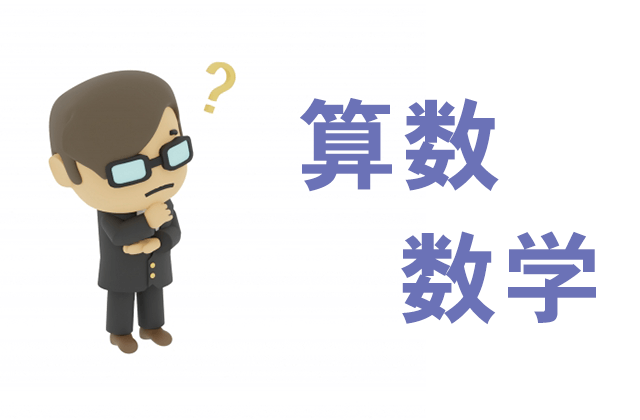
算数と数学の違いってなに?
算数と数学と聞いて、あなたは何を思い浮かべるでしょうか。義務教育に関わったことのある多くの人は、「小学校の教科として算数、中学校からの教科としての数学」を思い浮かべるのではないでしょうか。
算数と数学の違いを教科としてみてみると、一番の違いは「目標」にあります。では、どのような違いがあるのでしょうか。
各教科の目標や取り扱い内容や基本的指導事項などが示されている「学習指導要領」(※)から、算数と数学の違いをみていきましょう(※学習指導要領:小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校について、その教育課程の基準として文部科学大臣が公示する)。
「小学校学習指導要領」(第2章 各教科 第3節 算数)
第1 目標
算数的活動を通して、数量や図形についての基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け、日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考え、表現する能力を育てるとともに、算数的活動の楽しさや数理的な処理のよさに気付き、進んで生活や学習に活用しようとする態度を育てる。
以上から算数は、足し算・引き算・掛け算・割り算を使った基本的な計算方法、図形の面積・体積の求め方、物の重さや長さの量り方など、日常生活に必要な基礎・基本となる数量や図形の扱い方を学ぶ教科といえます。
つまり算数の目標は、「正しい答えを導き出すための数理的な知識や技能を身につける」ことにあるとうかがえます。
「中学校学習指導要領」(第2章 各教科 第3節 数学)
第1 目標
数学的活動を通して、数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則についての理解を深め、数学的な表現や処理の仕方を習得し、事象を数理的に考察し表現する能力を高めるとともに、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、それらを活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる。
以上から、数学は、数量や図形などの概念や原理・法則についての理解を深めることによって、自然界や人間界だけにとどまらず哲学的な現象にいたるまで数理的に考察し、表現する能力を高めことを学ぶ教科といえます。
つまり数学の目標は、「答えに至るまでの過程で数理的な概念理解を深めながら研究する」ことにあるとうかがえます。
算数と数学において、一つひとつの単元や内容を理解することは非常に重要です。そのため、やり方の暗記をしただけでは、数理的能力は身に付きません。もしも算数や数学でわからなくなったときは、意味の理解ができた単元や内容まで戻って、自身の躓きを正確に把握してください。そのうえで、反復学習と見直しをすることによって数理的能力を涵養し、身に付けることができます。
明治時代に来日し、日本の数学教育や工学教育に貢献したイギリスの応用数学者・工学教育者のペリー(Perry, John)は、1901年の講演で「数学は自己のためということから離れて、物事を考える重要性を学ぶ」と述べたといわれています。
算数における数理的に「正しい答えを導き出す」スキルは日常生活や数学の基礎として重要です。さらに、算数の積み重ねによるスキルを生かし、今度は日常生活や自己さえも離れて数理的に「答えに至るまでの過程」を研究して積み重ねていくことが、数学の理解を深めることにつながっています。
また、数学は全ての理科系教科の基礎であるため、翻って日常生活を豊かにするなど、実世界と概念世界を超えて連環しているといえます。ぜひ算数と数学の違いを理解したうえで、算数と数学の理解を深めてみてください。
算数と数学の違いを教科としてみてみると、一番の違いは「目標」にあります。では、どのような違いがあるのでしょうか。
各教科の目標や取り扱い内容や基本的指導事項などが示されている「学習指導要領」(※)から、算数と数学の違いをみていきましょう(※学習指導要領:小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校について、その教育課程の基準として文部科学大臣が公示する)。
算数の目的は「正しい答えを導き出す」こと
まず、算数の目標は、「小学校学習指導要領」に以下のように示されいます。「小学校学習指導要領」(第2章 各教科 第3節 算数)
第1 目標
算数的活動を通して、数量や図形についての基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け、日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考え、表現する能力を育てるとともに、算数的活動の楽しさや数理的な処理のよさに気付き、進んで生活や学習に活用しようとする態度を育てる。
以上から算数は、足し算・引き算・掛け算・割り算を使った基本的な計算方法、図形の面積・体積の求め方、物の重さや長さの量り方など、日常生活に必要な基礎・基本となる数量や図形の扱い方を学ぶ教科といえます。
つまり算数の目標は、「正しい答えを導き出すための数理的な知識や技能を身につける」ことにあるとうかがえます。
数学の目的は「答えに至るまでの過程」にあり
一方、数学の目標は、「中学校学習指導要領」に以下のように示されています。「中学校学習指導要領」(第2章 各教科 第3節 数学)
第1 目標
数学的活動を通して、数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則についての理解を深め、数学的な表現や処理の仕方を習得し、事象を数理的に考察し表現する能力を高めるとともに、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、それらを活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる。
以上から、数学は、数量や図形などの概念や原理・法則についての理解を深めることによって、自然界や人間界だけにとどまらず哲学的な現象にいたるまで数理的に考察し、表現する能力を高めことを学ぶ教科といえます。
つまり数学の目標は、「答えに至るまでの過程で数理的な概念理解を深めながら研究する」ことにあるとうかがえます。
積み重なり連環する算数と数学
算数と数学は小学校と中学校の9年間、さらに高校の3年間を加えると12年間にわたって、積み重ねていく教科です。したがって、小学校の段階で算数が理解できないと、中学校以降の数学も当然ながら理解できません。算数と数学において、一つひとつの単元や内容を理解することは非常に重要です。そのため、やり方の暗記をしただけでは、数理的能力は身に付きません。もしも算数や数学でわからなくなったときは、意味の理解ができた単元や内容まで戻って、自身の躓きを正確に把握してください。そのうえで、反復学習と見直しをすることによって数理的能力を涵養し、身に付けることができます。
明治時代に来日し、日本の数学教育や工学教育に貢献したイギリスの応用数学者・工学教育者のペリー(Perry, John)は、1901年の講演で「数学は自己のためということから離れて、物事を考える重要性を学ぶ」と述べたといわれています。
算数における数理的に「正しい答えを導き出す」スキルは日常生活や数学の基礎として重要です。さらに、算数の積み重ねによるスキルを生かし、今度は日常生活や自己さえも離れて数理的に「答えに至るまでの過程」を研究して積み重ねていくことが、数学の理解を深めることにつながっています。
また、数学は全ての理科系教科の基礎であるため、翻って日常生活を豊かにするなど、実世界と概念世界を超えて連環しているといえます。ぜひ算数と数学の違いを理解したうえで、算数と数学の理解を深めてみてください。
<参考文献・参考サイト>
・『デジタル大辞泉』(小学館)
・『法律用語辞典 第5版』(有斐閣)
・『岩波 世界人名大辞典』(岩波書店)
・『算数・数学間違い探し』(芳沢光雄著、講談社+α新書)
・第2章 各教科 第3節 算数
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/san.htm
・第2章 各教科 第3節 数学
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/su.htm
・算数と数学の違いはずばり!考え方にあった!
https://www.eikoh.co.jp/koukoujuken/column/c2024/
・算数と数学の違いは「考え方」?違いやそれぞれの特徴について解説
https://www.edic.jp/column/article/16.html
・『デジタル大辞泉』(小学館)
・『法律用語辞典 第5版』(有斐閣)
・『岩波 世界人名大辞典』(岩波書店)
・『算数・数学間違い探し』(芳沢光雄著、講談社+α新書)
・第2章 各教科 第3節 算数
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/san.htm
・第2章 各教科 第3節 数学
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/su.htm
・算数と数学の違いはずばり!考え方にあった!
https://www.eikoh.co.jp/koukoujuken/column/c2024/
・算数と数学の違いは「考え方」?違いやそれぞれの特徴について解説
https://www.edic.jp/column/article/16.html
人気の講義ランキングTOP20










