テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
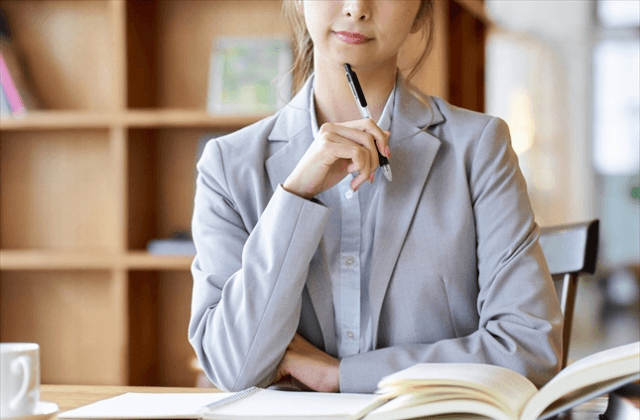
『世にもあいまいなことばの秘密』で考える言葉の宿命
「ここではきものをぬいでください」……これをどう読めばいいでしょうか。言葉はなんとも不思議なもので、不確かで曖昧な面を持ち合わせています。意図したとおりに伝わらないことも多く、小さな誤解が大きな混乱を招くこともしばしばです。また、同じ言葉でも話す人や聞く人、そのときの状況によって意味が変わることがあります。
でも、私たちは人と話すときも、ものを考えるときも、言葉を使います。抽象的な思考や胸の内に秘めた感情は、言葉にすることで他者と共有できるようになります。普段なにげなく使っている言葉ですが、改めて考えると結構すごいものですよね。
今回ご紹介する『世にもあいまいなことばの秘密』(川添愛著、ちくまプリマー新書)は、そんな言葉の特徴でもある「曖昧さ」に焦点を当てた本です。言葉のすれ違いに関する多くの事例が紹介されており、言葉の複雑さや面白さが存分に楽しめる作品となっています。時おり挿入される練習問題を解きながら、言葉をさまざまな角度から眺めていくことで、読者は言葉に対する鋭敏な感覚を磨くことができるでしょう。
実際、平仮名だけで文を書くと単語の切れ目が分かりにくくなります。有名な例として「ここではきものをぬいでください」というものがあります。これは単語を区切る場所によって、「ここで履き物をぬいでください」と、「ここでは着物をぬいでください」の二通りに解釈することができます。「ここで履き物を脱いでください」のように漢字を使って書くと、単語の切れ目がわかりやすく誤解も生じにくくなります。
ただし、漢字を用いてもまぎらわしい例があります。本書で紹介されているのは「この先生きのこるには」というものです。川添愛さんが実際に見かけた文で、最初は意味がわからなく戸惑ってしまったそうです。というのも、川添さんはこれを「この先生(せんせい)きのこるには」と読んでしまい、「『きのこる』ってどういう意味だろう」と思ってしまったんですね。実際には、「この先(さき)生きのこるには」と読むのが正解でした。「この先、生きのこるには」のように読点が入っていないと、このような誤解が起きてしまうのです。
解釈1:勉強をしない、大学生というもの
解釈2:大学生のうち、勉強しない人たち
このように解釈が分かれる理由は、「勉強しない」という修飾語と「大学生」という修飾される名詞との関係が二通り考えられるからです。解釈1では、「大学生」というものは「勉強しない」ものだと、カテゴリー全体の性質・特徴を述べていると考えています。「白い、雪」と同じ構造ですね。言語学ではこのような修飾関係を「非限定的修飾」といいます。
一方、解釈2では、大学生にもいろいろいる中で、その中でも「勉強しない」特定の人たちのことを指していると考えます。「赤い、花」と同じ構造です。これは「限定的修飾」と呼ばれます。
言葉に触れるときには、このような複数の解釈があるかもしれないと注意する必要があります。そうしないと、「大学生のうち、勉強しない人たち」についての言及に対して、「大学生がみんな勉強していないなんて決めつけだ!」と反発してしまうといったすれ違いが起こってしまうからです。
本書ではさまざまな言葉の曖昧さについて紹介されます。これらの事例を通じて読者は言葉を多面的に見ることができるようになり、トラブルも事前に回避できるようになります。
ですが、川添さんは本書の締めくくりで「曖昧さは悪いものではない」と述べています。というのも、もし言葉から曖昧さがなくなったら大変なことになるからです。チェコの劇作家ヴァーツラフ・ハヴェルの『通達』という戯曲には、曖昧さを完全になくした人工言語プティデペというものが登場します。正確で円滑なコミュニケーションを目指して開発されたはずのこの人工言語が、逆に大混乱を招く様子が戯曲では描かれています。
川添さんは、曖昧さは言葉について回る宿命のようなものだと言います。この宿命から逃れられないのであれば、曖昧さを悪いものとみなすのではなく、そこに楽しみを見いだしたほうがいいでしょう。言葉のすれ違いを防ぐことは難しいかもしれませんが、言葉に曖昧さがあるからこそ、掛詞や駄洒落のような言葉遊びを楽しめるのです。このややこしくも面白い、言葉の不思議な世界を本書で楽しんでみてはいかがでしょうか。
でも、私たちは人と話すときも、ものを考えるときも、言葉を使います。抽象的な思考や胸の内に秘めた感情は、言葉にすることで他者と共有できるようになります。普段なにげなく使っている言葉ですが、改めて考えると結構すごいものですよね。
今回ご紹介する『世にもあいまいなことばの秘密』(川添愛著、ちくまプリマー新書)は、そんな言葉の特徴でもある「曖昧さ」に焦点を当てた本です。言葉のすれ違いに関する多くの事例が紹介されており、言葉の複雑さや面白さが存分に楽しめる作品となっています。時おり挿入される練習問題を解きながら、言葉をさまざまな角度から眺めていくことで、読者は言葉に対する鋭敏な感覚を磨くことができるでしょう。
単語の切れ目を考える…「この先生きのこるには」って?
日本語の文章を読むときには、どこが「単語の切れ目」なのかを考えることが大事です。外国人の日本語学習者にとって、日本語の文はどこで区切ればいいかわからないという悩みはありがちなものです。たとえば、英語では単語と単語の間にスペースが入るため「単語の切れ目」が一目でわかりますが、日本語にそのような明確な区切りは存在しません。では、日本人はどのようにして単語の切れ目を識別しているのでしょうか。実は、平仮名、片仮名、漢字の使い分けが大きなヒントになっているのです。実際、平仮名だけで文を書くと単語の切れ目が分かりにくくなります。有名な例として「ここではきものをぬいでください」というものがあります。これは単語を区切る場所によって、「ここで履き物をぬいでください」と、「ここでは着物をぬいでください」の二通りに解釈することができます。「ここで履き物を脱いでください」のように漢字を使って書くと、単語の切れ目がわかりやすく誤解も生じにくくなります。
ただし、漢字を用いてもまぎらわしい例があります。本書で紹介されているのは「この先生きのこるには」というものです。川添愛さんが実際に見かけた文で、最初は意味がわからなく戸惑ってしまったそうです。というのも、川添さんはこれを「この先生(せんせい)きのこるには」と読んでしまい、「『きのこる』ってどういう意味だろう」と思ってしまったんですね。実際には、「この先(さき)生きのこるには」と読むのが正解でした。「この先、生きのこるには」のように読点が入っていないと、このような誤解が起きてしまうのです。
「勉強しない大学生」――修飾関係による曖昧さ
言葉のすれ違いは修飾語の修飾関係によっても起こります。本書で紹介されている、「勉強しない大学生」という例を考えてみましょう。この表現には、二通りの解釈がありえます。解釈1:勉強をしない、大学生というもの
解釈2:大学生のうち、勉強しない人たち
このように解釈が分かれる理由は、「勉強しない」という修飾語と「大学生」という修飾される名詞との関係が二通り考えられるからです。解釈1では、「大学生」というものは「勉強しない」ものだと、カテゴリー全体の性質・特徴を述べていると考えています。「白い、雪」と同じ構造ですね。言語学ではこのような修飾関係を「非限定的修飾」といいます。
一方、解釈2では、大学生にもいろいろいる中で、その中でも「勉強しない」特定の人たちのことを指していると考えます。「赤い、花」と同じ構造です。これは「限定的修飾」と呼ばれます。
言葉に触れるときには、このような複数の解釈があるかもしれないと注意する必要があります。そうしないと、「大学生のうち、勉強しない人たち」についての言及に対して、「大学生がみんな勉強していないなんて決めつけだ!」と反発してしまうといったすれ違いが起こってしまうからです。
曖昧さは言葉について回る宿命のようなもの
著者の川添さんは、自然言語処理を専門とする言語学者でありながら、『数の女王』(東京書籍)『聖者のかけら』(新潮文庫)などの小説を手掛ける作家としても活躍されています。論文、エッセー、小説と幅広いジャンルで文章を書いてきた著者だからこそ、言葉に対して面白い視点を提供してくれるのでしょう。本書ではさまざまな言葉の曖昧さについて紹介されます。これらの事例を通じて読者は言葉を多面的に見ることができるようになり、トラブルも事前に回避できるようになります。
ですが、川添さんは本書の締めくくりで「曖昧さは悪いものではない」と述べています。というのも、もし言葉から曖昧さがなくなったら大変なことになるからです。チェコの劇作家ヴァーツラフ・ハヴェルの『通達』という戯曲には、曖昧さを完全になくした人工言語プティデペというものが登場します。正確で円滑なコミュニケーションを目指して開発されたはずのこの人工言語が、逆に大混乱を招く様子が戯曲では描かれています。
川添さんは、曖昧さは言葉について回る宿命のようなものだと言います。この宿命から逃れられないのであれば、曖昧さを悪いものとみなすのではなく、そこに楽しみを見いだしたほうがいいでしょう。言葉のすれ違いを防ぐことは難しいかもしれませんが、言葉に曖昧さがあるからこそ、掛詞や駄洒落のような言葉遊びを楽しめるのです。このややこしくも面白い、言葉の不思議な世界を本書で楽しんでみてはいかがでしょうか。
<参考文献>
『世にもあいまいなことばの秘密』(川添愛著、ちくまプリマー新書)
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480684684/
<参考サイト>
川添愛さんのツイッター(現X)
https://x.com/zoeai?s=20
『世にもあいまいなことばの秘密』(川添愛著、ちくまプリマー新書)
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480684684/
<参考サイト>
川添愛さんのツイッター(現X)
https://x.com/zoeai?s=20
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子










