テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
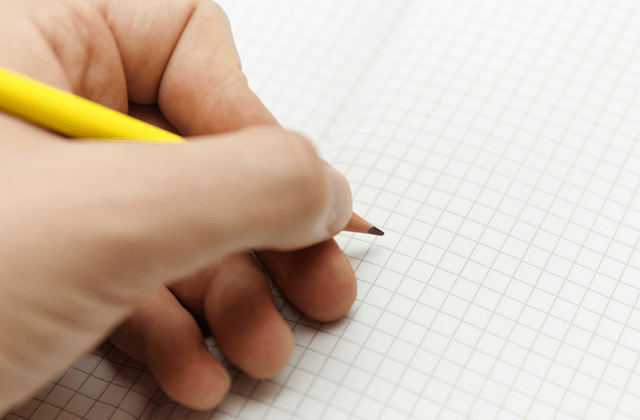
右利きにはわからない?左利きの悩み・ストレス
左利きの人が親や教師から矯正されていたのは、一昔前の話。最近はダイバーシティの最も身近な例として尊重されることが増えています。文具メーカーのゼブラ株式会社が全国の左利き104名にウェブアンケートを実施したところ、左利きの利点としては「個性的と思われる」「センス良さそうに見える」「頭が良さそうに見える」など、イメージの高さがわかりました。
そうは言っても左利きの人の割合は、全人口のほぼ10~13%ぐらい。世の中にある道具のほとんどは、右利きであることを前提に開発されているため、左利きの人たちは思わぬ場面でさまざまな「困ったこと」に遭遇しています。
身近な道具で理不尽さを感じるのは、ゼンマイ仕掛けのおもちゃ。ドアノブなどもそうなのですが、成長すると左手で持って右に回すのはかなり苦労するものです。日常生活でよく使うハサミも、基本的には右利きに合わせて作られているため、左利きの子はとても扱いづらく感じるでしょう。
また、食事で困るのは、左隣に右利きの人がいると、互いのひじがぶつかってしまう点。かき混ぜる方向なども逆なので、手を添えられるとかえってストレスです。一人でキッチンに立つようになると、計量カップやミルクパンなど、片側にしかそそぎ口のないものは、ほぼ100パーセント、右利き優先のデザイン。今は減りましたが、蛇口式の水道もゼンマイと同じく、ひねるのにコツが必要です。
ノートや用紙を斜めにすると少しは書きやすくなるのに、叱られたり邪魔にされたりとトラブルのもと。リングとじのノートやバインダーでは、右側に書き込むのが一苦労ですし、左側が問題で右側が答えの欄だと、自分の手で問題欄が見えなくなってしまいます。
二人がけの机の右側に座らされることになれば、しょっちゅうぶつかり合いです。細かいところでは定規を使うにも、左から右に目盛りが並んでいるので、左利きにはとても不便。
学年が進むにつれ、理科の実験、調理実習など、新しいことに出会うたびに道具の問題と向き合わなければなりません。スポーツの場面では、利き手のおかげでヒーロー・ヒロインになれる可能性が高いのですが、不便さを打ち消してくれるかどうかは別の話です。
日常の数々な不便を自分なりの工夫で乗り越えていくことから、左利き特有の「スマートな感じ」や「器用でクール」なイメージが芽生えてくるのかもしれません。生まれつきの左利きが右脳優位の発想で多数派を驚かせていくのは、彼らが日常で出会う苦労や、それに対応するための試行錯誤、創意工夫などを考えると、不思議なことではないのかもしれませんね。
そうは言っても左利きの人の割合は、全人口のほぼ10~13%ぐらい。世の中にある道具のほとんどは、右利きであることを前提に開発されているため、左利きの人たちは思わぬ場面でさまざまな「困ったこと」に遭遇しています。
まだ学校に上がらない子どもたちは?
「右も左もわからない」というように、文字を覚える前の子どもにとって左右どちらが利き手でも、本人のストレスにはなりません。しかし、そうした子どもたちが一番困るのは、自分の使いやすい側の手を禁じられてしまうことです。利き手を決めているのは脳であり、子どもの好みやクセではありません。その頃に矯正されて両手を使えるようになった人は、おとなになってからも左右の判断がしづらくなる「左右オンチ」に悩む傾向が高いようです。身近な道具で理不尽さを感じるのは、ゼンマイ仕掛けのおもちゃ。ドアノブなどもそうなのですが、成長すると左手で持って右に回すのはかなり苦労するものです。日常生活でよく使うハサミも、基本的には右利きに合わせて作られているため、左利きの子はとても扱いづらく感じるでしょう。
また、食事で困るのは、左隣に右利きの人がいると、互いのひじがぶつかってしまう点。かき混ぜる方向なども逆なので、手を添えられるとかえってストレスです。一人でキッチンに立つようになると、計量カップやミルクパンなど、片側にしかそそぎ口のないものは、ほぼ100パーセント、右利き優先のデザイン。今は減りましたが、蛇口式の水道もゼンマイと同じく、ひねるのにコツが必要です。
学校で出会う左利きゆえのトラブル
小学校に上がるようになると、右利き用の道具ばかりの環境に飛び込むことになります。文字を書くのは、最初のうちは相当なストレスを感じるとのこと。右利きが字を書くのは、基本「引っ張る」動きですが、左利きは「押して」字を書くので、右利きの人たちのように速くはなかなか書けないそうです。また、書いた上を手でこすることになるため、左手の小指から手首にかけての側面は、いつも真っ黒になります。ノートや用紙を斜めにすると少しは書きやすくなるのに、叱られたり邪魔にされたりとトラブルのもと。リングとじのノートやバインダーでは、右側に書き込むのが一苦労ですし、左側が問題で右側が答えの欄だと、自分の手で問題欄が見えなくなってしまいます。
二人がけの机の右側に座らされることになれば、しょっちゅうぶつかり合いです。細かいところでは定規を使うにも、左から右に目盛りが並んでいるので、左利きにはとても不便。
学年が進むにつれ、理科の実験、調理実習など、新しいことに出会うたびに道具の問題と向き合わなければなりません。スポーツの場面では、利き手のおかげでヒーロー・ヒロインになれる可能性が高いのですが、不便さを打ち消してくれるかどうかは別の話です。
なるか、一発逆転!?
缶切りや皮むき、ハサミにカッター、包丁と、右利き仕様の刃物を使いながら成長した子どもたちは、自動改札、自販機、リモコン操作の不便さに慣れ、ものによっては右手を使うなど、器用に適応して大人になっていきます。日常の数々な不便を自分なりの工夫で乗り越えていくことから、左利き特有の「スマートな感じ」や「器用でクール」なイメージが芽生えてくるのかもしれません。生まれつきの左利きが右脳優位の発想で多数派を驚かせていくのは、彼らが日常で出会う苦労や、それに対応するための試行錯誤、創意工夫などを考えると、不思議なことではないのかもしれませんね。
<参考サイト>
・ゼブラ:左利きの悩みの実態について調査実施
http://www.zebra.co.jp/press/news/2016/0411.html
・ゼブラ:左利きの悩みの実態について調査実施
http://www.zebra.co.jp/press/news/2016/0411.html
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










