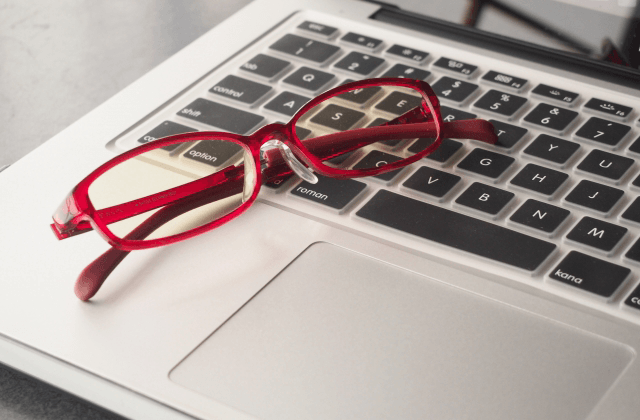
「ブルーライトが目に悪い」は本当か?
「ブルーライトは目に悪い」は本当?
最近よく見かけるようになった、ブルーライトをカットする眼鏡。スマートフォンやタブレット、パソコンによる疲れ目を緩和するのに効果があるとして、お世話になっている人も多いでしょう。しかし、ブルーライトは本当に目に悪いものなのでしょうか。筑波大学眼科教授の大鹿哲郎氏が、この疑問に答えてくれました。そもそも、なぜブルーライトは目に悪いというイメージを持たれるのでしょうか。ブルーライトは文字通り「青い光」を意味しますが、目に見える光(可視光)の中で、青は波長が短い光です。そして波長は短い方が、強いエネルギーを持つとされます。赤外線よりも、紫外線の方が人体に与える影響は大きいですよね。あれと同じです。
ブルーライトは、エネルギーの強い光だから、目に与える影響も強そう、ということから、ブルーライト=「目に悪い」というイメージが出来上がった、と考えられます。
実は日常生活に不可欠だったブルーライト
しかし、大鹿教授によれば、ブルーライトは日常生活になくてはならないものです。ブルーライトを感じるのは、網膜にある細胞です。この網膜の細胞がブルーライトを感知すると、脳にその信号が伝わり、信号を受け取った脳はメラトニンという物質を出します。このメラトニンは、体内時計を司っているとても重要な物質です。これがうまく働かないと、一日の体内リズムが狂ってしまいます。つまりブルーライトは、目に悪いどころか、人間の体内時計をきちんと機能させるためのものなのです。
ブルーライトは携帯端末だけでなく、太陽光にも含まれます。朝起きてカーテンを開けると、自然のブルーライトが目に入ります。私たち人間の体は、こうやって「朝が来た」ことを知ります。まさにブルーライトによって、体が起きるのです。
逆に言えば、体が眠りに入ろうとする時に、スマートフォン等を使ってブルーライトを浴びてしまうと、体は「あれ?朝?」と勘違いをしてしまい、体内時計が狂ってしまいます。ブルーライトが「目に悪い」とすれば、それは就寝前にスマートフォンやパソコンを見ることで、眠りが浅くなったり寝付きが悪くなったりするからです。
つまり、ブルーライト=「目に悪い」というより、ブルーライトを浴びるタイミングに問題があった、ということです。大鹿教授が強調するように、朝起きた時にはブルーライトが必要ですが、夜寝る前にはあまり必要ないのです。
大切なのは、うまく付き合うこと
大鹿教授によれば、ブルーライトによって目が疲れやすくなったり、障害を起こしたりするはっきりした因果関係は、まだ解明されていないそうです。つまり現時点では、ブルーライト=「目に悪い」という医学的証拠はない、ということです。ブルーライトカットの眼鏡も、まったく無意味というわけではないにせよ、目が疲れる原因はブルーライトに限りません。だから、眼鏡を変えれば疲れ目が劇的に良くなるわけでもありません。
また、もし外国旅行に行って時差ボケを起こしたら、外に行って日光を浴びれば、ブルーライトによって体内時計がリセットされ、時差ボケを解消することができます。
このように、ブルーライトは人間が健康的に生活していくために不可欠なもので、むやみに怖がる必要はありません。体が必要とするときはブルーライトを浴び、必要ないときはあまり目に入れないようにすればよいのです。
ブルーライト=「目に悪い」というのは、思い込みだったようです。うまく付き合っていくことが大切ですね。
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子
毛繕いを代行!?脳の大型化が可能にしたメンタライジング
長谷川眞理子







