●皆が自分の感じる方向へ進める時代になった
浅見 私は、これからの時代に必要なことは、それぞれの人の「感じる力」だと思っています。というのは、これだけたくさんの情報があふれている社会になると、一つの事柄について、メディアを見てもネットを開いても賛否両論で、それぞれの立場に立つと、きっとどれもが全て正しい意見だと思うのです。ただ、一つの事柄に対して、国や政府がいいと言っているからといって必ずしもいいかどうかは分からないし、自分の信頼する人がネットでいいと言っていても、それも必ずしも自分に当てはまるとは限りません。
では何を基準に選んでいけばいいのか、というときに大事なのが、一人一人の感じる力や感性だと思うのです。
同じ事柄でも、あなたにとっては当てはまるし、いいサンプルかもしれないけれども、私にとっては違う、という場合があります。また、逆もあります。私にとってはすごくいいけれども、あなたにとっては違うかもしれない。それをジャッジするものが何かというと、昔は、やはり国の定めたルールや、この会社に入れば絶対に一生安泰だとか、こういう生き方をすれば一生幸せというマニュアルがあったと思います。しかし、そのマニュアルが、今どんどん崩れています。崩れているというより、本当にやっと普通の社会になってきたのではないかと私は思っています。
どういうことかというと、今は、女性でも外に働きに行く人もいれば、男性でも家にいる人もいて、それから、例えば、草食男子が出てきたら、肉食女子も出てきたというように、あらゆるジャンルに多様性が生まれ、選択肢がいろいろと増えてきました。それは、新しい価値観が出てきたのではなく、もともとあったと思うのです。ただ、昔は、草食男子であっても、男性たるものこうあるべきだ、というものがあるために、自分の本音が出せず、女性も、自分は本当はこういうことをしたいのに、それは女性の幸せではない、といわれたために言えなかっただけなのです。“皆違っていていい”というか、自分の好きなように、自分がワクワク感じる方向に、ようやく進める時代になったのだと思います。
●新たな基準は「感じる力」=「直感」
浅見 ですから、自由な時代ですし、選択肢が増えたことで、今度は逆に言うと王道とマニュアルがなくなったわけです。では何を基準にしたらいいかというと、それが、そ...











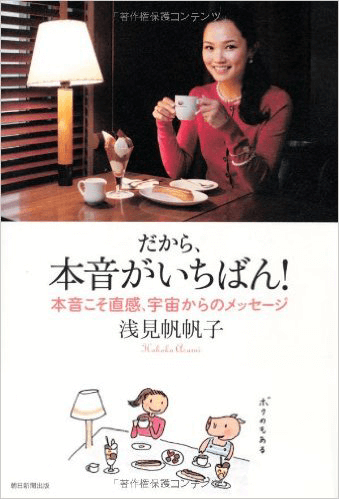

(浅見帆帆子著、朝日新聞出版)