●「人間大事」の哲学は、お客さまも社員も同様に敬う
―― 松下幸之助シリーズの最後になるかもしれないこの本『ひとことの力:松下幸之助の言葉』(東洋経済新報社)を読ませていただいて、大変感銘を受けました。特に「一人も解雇するな、1円も給料を下げるな」というあたりからお話を聞かせていただければと思います。
江口 松下幸之助という人は、経営をやっていくときに、商売のための商売や経営のための経営ではなく、人間のための商売、人間のための経営というか、あの人の根底に常に流れている“人間大事”、つまり「人間とは非常に素晴らしいものであり、その本質はダイヤモンドだ」という意識が強かったのです。そのような人間観があります。
それと、もう一つ、松下幸之助さんは非常に苦労したということがあります。大正7年に松下電器製作所を始めましたが、言ってみれば中小零細企業ですから、吹けば飛ぶような小さな会社で、人を募集しても誰も来ない。もちろん優秀な人も来ないという状態でした。しかし、それでも人手が必要だという状況の中で、何とか人を採っていくのです。時には優秀ではない人も採用しました。しかし、いかがなものかと思えるような人たちも、松下幸之助さんと松下電器製作所で仕事をしていると、だんだん力をつけていくのです。
そして、それを「わしが教育しているから当たり前だ」とか「仕事をしているのだから当たり前だ」という考え方ではなく、「なぜ人間はどんどん成長していくのか」「なぜどんどん仕事ができるようになるのか」「人手が要るからと、能力がないのではないかと思いながらも採用した人も、能力を発揮するようになるのはすごい」という考え方を持ってやっていったのです。それが、「人間は誰もが大事だ」「素晴らしい存在だ」という意識につながるのです。
ですから、松下幸之助さんと話をすると、“人間から出発する”ということが根底に流れている話が多いのです。例えば、“いいものを安くたくさん”という話がありますが、それは、いいものを安くたくさんつくれば「もうかるから」という、商売や経営の次元で考えたことではなく、“いいもの”の背景にあるのは、「人間というものは素晴らしい。その素晴らしい存在にふさわしいいいものをつくらなければ、素晴らしい本質を持った人間に対して失礼だ」という考え方なのです。“安く”も、「そんな素晴らしい人間に...










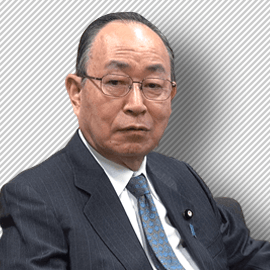
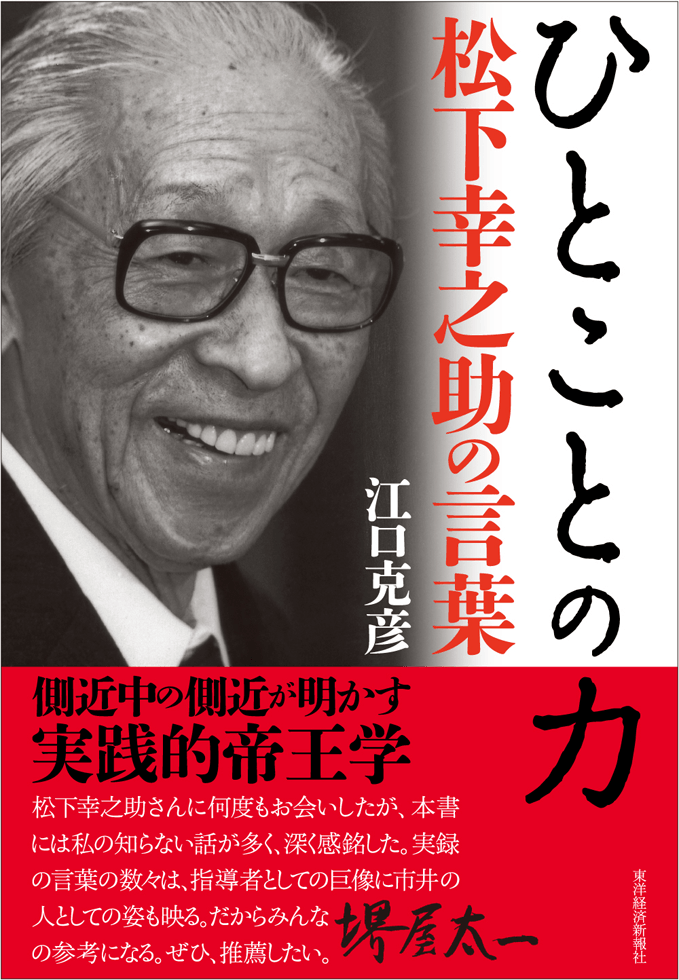

(江口克彦著、東洋経済新報社)