テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
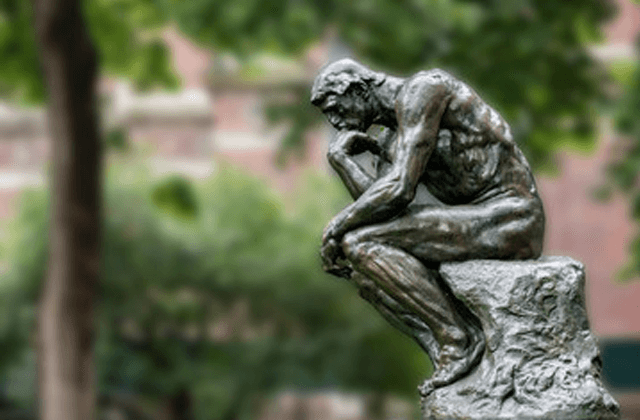
『哲学しててもいいですか?』に学ぶ、現代社会を変える力
人文社会学を学ぶことの意義は?
2015年、文部科学省が国立大学の人文社会科学へ「組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換」を求めたというニュースを覚えていますか? 競争の進むグローバル社会において、より社会経済が人員を必要とする分野に力を入れ、学生を養育しなさいという改革指導でした。ところがこの文部科学省の提言は、「社会的要請の高い分野」という部分を「即戦力」や「高いコストパフォーマンス」という意図で解釈され、ペイバックの望める理系を重視し、文系を軽視したと受け取られる事態に発展しました。「国は文系廃止をするつもりなのでは?」と批難の声があがり、大きな波紋を呼んだのです。文部科学省は「そんな意図はなかった」と火消しのために奔走しましたが、こうした、「人文社会科学を学んでどんな役に立つのか? 必要なのか?」という議論は、度々なされています。
ではみなさんに問います。「人文社会科学を学ぶことの意義」とは何でしょうか。なかでも、どんな学問なのか、具体的にイメージがしづらいものが「哲学」かもしれません。哲学が社会に出る上でどう役に立つのか、すんなりと答えられる人は少ないでしょう。
そこで今回紹介したいのが、信州大学人文学部准教授・三谷尚純氏の著書『哲学しててもいいですか?―文系学部不要論へのささやかな反論―』(ナカニシヤ出版)です。
哲学が与えてくれる「箱の外で考える力」
三谷氏は本書のなかで、哲学を「箱の外で思考する力」としています。ここで述べられている「箱」とは、わたしたちの暮らす現代社会や、現実そのもののことです。そこには、安全なものとして社会からの要求があり、決まっているルールに従って生きる世界があります。冒頭で述べた、国立大学の人文社会科学へ「組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換」という提言は、社会の求める規範に従った「箱」の中に収まる人物をつくるということだと、三谷氏は語ります。例えば「社会的要請の高い分野」が、英語を話せる人を増やすだとか、就職してすぐに役に立つ技術を学ばせるといったことであるなら、そうした大学は職業訓練校になってしまうということでしょう。実際に、現在の大学では本来の趣旨である「学問をする」という行為よりも、こうした「社会的要請」に答えることが重要視されつつあるといいます。
それが社会・経済のためになるなら、歓迎すべきと考える人もいるかもしれません。しかし、インターネットが普及し、急速なグローバル化が進んだ今、これまで「良し」とされていた、あるいは「安全」と思われていたものの価値が簡単にゆらぐ時代になっています。つまり、与えられた「箱」のあり方が変わり、「箱の外」に出なくてはいけないときが来ているということです。そうしたとき、「箱の外」を思い描くことをせず、即時的な技能だけを与えられた人間はもろく、変化に対応することがなかなかできないのです。
行き詰まった社会に一石を投じる
「箱の外で思考する力」は、普段起こりえないこと、イレギュラーなことを考えておく訓練にもなり、哲学は、「箱の外」に出てさまざまなことに思いを巡らせることでもあります。また「箱の外」の考えを、内側に取り入れることを、三谷氏は「異邦人の目」を持つことだとしています。哲学は、「耳障りであること/不快であること」を理由に理論や理屈を除外するということはしません。三谷氏は、「哲学を実践するものたちには、みずからには異質を感じられる他者の見解をも土俵の上に招き入れるための、開かれた態度と器量が要求される」としています。近年、日本では若者の内向的な態度が問題視され、世界では排外主義の動きが盛んになっています。哲学にとって、こうした内向きの思想や、排他的な行為は、真逆のものといえるでしょう。
三谷氏は本書のエピローグで、余裕がなく、息苦しい時代になればなるほど、「大義」や「明確でわかりやすい答え」から距離をとることが難しくなっていくとしています。たしかに、今の日本は格差や貧困、近隣諸国との政治的な困難など、多くの問題が複雑に絡み合い、次第に息苦しさが増していくとともに、「右か左か、黒か白か」といったわかりやすい答えが求められ、それに流される人も少なくないでしょう。こうして状況が行き詰まると、「誰も反論できない正論」を踏み絵のように突きつける場面が増えるのではと、三谷氏はいいます。
そして、エピローグの最後にはこう綴られています。
「箱の外に出て思考し、異邦人の目をもって時代に対峙する哲学の声がその役割を発揮すべく期待されるのは、まさしくこのような状況においてなのではないだろうか」
誰もが行き詰まり、選択肢を見失ったときこそ、「社会的要請」とは別の学問、つまり哲学の出番といえるのではないでしょうか。
<参考文献>
『哲学しててもいいですか?―文系学部不要論へのささやかな反論―』(三谷尚純著、ナカニシヤ出版)
http://www.nakanishiya.co.jp/book/b281524.html
<関連サイト>
三谷尚澄氏のブログ
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/arts/prof/mitani_1/blog.php
『哲学しててもいいですか?―文系学部不要論へのささやかな反論―』(三谷尚純著、ナカニシヤ出版)
http://www.nakanishiya.co.jp/book/b281524.html
<関連サイト>
三谷尚澄氏のブログ
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/arts/prof/mitani_1/blog.php
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
葛飾北斎と応為の見事な「画狂人生」を絵と解説で辿る
テンミニッツ・アカデミー編集部
最近の話題は宇宙生命学…生命の起源に迫る可能性
川口淳一郎










