テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
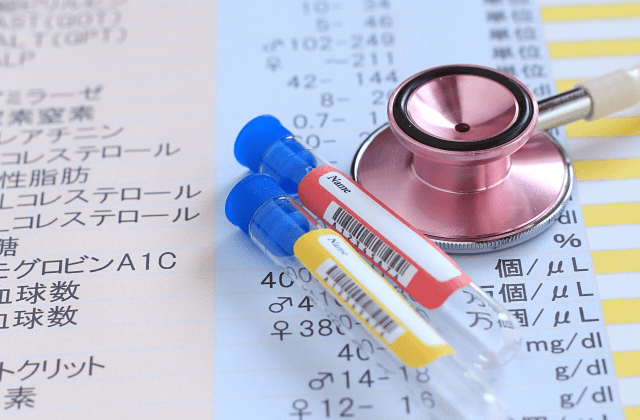
40~50代で急増する「生活習慣病」の予防と対策
2017年9月、厚生労働省から「2016年の国民健康・栄養調査」の結果が発表されました(2016年10~11月に実施)。この調査では、基本項目に加え重点項目として、「生活習慣病」の一つでもある「糖尿病」についての調査が行われました。その結果、糖尿病が疑われる成人の推計が、はじめて1000万人を上ったことがわかりました。
さらに、糖尿病とも関係する「肥満度」をBMI(体格指数:BMI18.5~25未満「普通」、25以上「肥満」、18.5未満「低体重(やせ)」)で算出したところ、「肥満」の割合は、男性31.3%、女性20.6%。とくに男性の50歳代で36.5%と3人に1人以上が肥満、また女性も50歳代で21.3%となり以降も割合が増加するという結果が出ました。
こういった結果を文字通り安易に捉えてしまうと、成人病は年齢を重ねること、つまり「加齢」によって起こる病気というイメージにつながるかもしれません。たとえば、加齢による基礎代謝の低下が肥満を誘引し、加齢により血管の弾力性に低下しが血圧の原因になるといったことは多々あります。また、なかには原因が詳しくわかっていない病状や、遺伝要因が含まれることも少なからずあります。
しかしそれ以上に、生活習慣病は、偏った食事や運動不足、喫煙、飲酒などの、生活習慣が発症と進行に大きく関係しています。主要因は文字通り生活習慣に、つまりは「生活習慣の乱れ」もしくは「悪しき生活習慣」にあるといわれています。
まずは正しい知識をもって、自身の生活習慣を見直してみましょう。インターネットや書籍などで、たくさんの情報やツールが紹介されています。
たとえば、厚生労働省では、生活習慣病予防として普段の生活習慣の見直しや検診、生活習慣病の実態を知ることなどを呼びかけ、情報を提供しています。ほかにも日本生活習慣病予防協会では、生活習慣病のリスクチェックツールや関連情報の発信、「一無、二少、三多(無煙、少食・少酒、多動・多休・多接)」などの勧め、イベントや講演会などを行っています。
わかりやすいサイトや書籍からの正しい情報を得て、自分にあったチェックシートなどを使い、生活習慣病や予備軍の該当項目と自身の生活習慣を照らし合わせてみましょう。客観的に自身の現状を把握し、食生活や運動状況などの生活習慣を見直し、過剰分のカットや不足分の補填をしていきましょう。
脳科学者の岩崎一郎氏は『何をやっても続かないのは、脳がダメな自分を記憶しているからだ』で、「『習慣を変える』とは、『脳を変化させる』こと」と言っています。ここでは例として、キーワード“快”にまつわる方法を取り上げてみます。
「行動を習慣化するためには、“快”が毎回得られる必要があります。習慣化したいのであれば、どうしたら毎回同じ“快”が得られるのか工夫してみましょう」と言っています。脳へ“快”を与えることにより、習慣化が促進されます。“快”はささやかなことでかまいません。例えば、アプリで記録をとって行動を視覚化したり、身近な人に褒めてもらうようにお願いし報酬をえたりするなどでも大丈夫です。
また、「ある行動(A)をして、60秒以内に何か(B)が起こると、脳がAとBを結びつける」ことや「200回くらいの繰り返しがあって、行動の習慣化ができてくる」ため、“快”を与えるタイミングは「60秒位内」に、回数は「200回以上」を目安にします。一度習慣化されると、“快”がなくても継続していくことができるということです。
45歳で2018年の平昌オリンピックの代表に選ばれ、史上初の8大会連続出場を達成したスキージャンプ界のレジェンド葛西紀明選手も、「時間がない日は10分間でもいいし、気分が乗らないときはウォーキングでもいいのです。無理をせず、継続していくことを優先させましょう」(『40歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れない体」と「折れない心」のつくり方』)と、習慣化に工夫を取り入れることがわかります。
習慣を変えて生活習慣病を予防・対策することは、簡単ではなく時間も手間もかかります。ですが不可能なことではありませんし、そのための技術や方法も提示されています。ぜひ一度、自身の生活習慣を見直してみてください。
さらに、糖尿病とも関係する「肥満度」をBMI(体格指数:BMI18.5~25未満「普通」、25以上「肥満」、18.5未満「低体重(やせ)」)で算出したところ、「肥満」の割合は、男性31.3%、女性20.6%。とくに男性の50歳代で36.5%と3人に1人以上が肥満、また女性も50歳代で21.3%となり以降も割合が増加するという結果が出ました。
「生活習慣病」ってどんな病気? 主要因は?
実は「2010年の国民健康・栄養調査結果」でも、「生活習慣病をもつ人の割合は40歳以降、男女ともに増加している」と発表されており、以前から生活習慣病の増加は大きな社会問題となっていました。なお、生活習慣病の代表的な病気には、糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満、悪性新生物(がん)、脳卒中、心筋梗などがあげられます。こういった結果を文字通り安易に捉えてしまうと、成人病は年齢を重ねること、つまり「加齢」によって起こる病気というイメージにつながるかもしれません。たとえば、加齢による基礎代謝の低下が肥満を誘引し、加齢により血管の弾力性に低下しが血圧の原因になるといったことは多々あります。また、なかには原因が詳しくわかっていない病状や、遺伝要因が含まれることも少なからずあります。
しかしそれ以上に、生活習慣病は、偏った食事や運動不足、喫煙、飲酒などの、生活習慣が発症と進行に大きく関係しています。主要因は文字通り生活習慣に、つまりは「生活習慣の乱れ」もしくは「悪しき生活習慣」にあるといわれています。
「生活習慣病」の理解と「生活習慣」の見直し
生活習慣病の主要因を「生活習慣の乱れ」と考えると、一筋の光明が差してきます。それは、「自分で対策のしようがある」ということです。ただし、予防と対策のためには、多少なりとも知識と手間は必要になります。まずは正しい知識をもって、自身の生活習慣を見直してみましょう。インターネットや書籍などで、たくさんの情報やツールが紹介されています。
たとえば、厚生労働省では、生活習慣病予防として普段の生活習慣の見直しや検診、生活習慣病の実態を知ることなどを呼びかけ、情報を提供しています。ほかにも日本生活習慣病予防協会では、生活習慣病のリスクチェックツールや関連情報の発信、「一無、二少、三多(無煙、少食・少酒、多動・多休・多接)」などの勧め、イベントや講演会などを行っています。
わかりやすいサイトや書籍からの正しい情報を得て、自分にあったチェックシートなどを使い、生活習慣病や予備軍の該当項目と自身の生活習慣を照らし合わせてみましょう。客観的に自身の現状を把握し、食生活や運動状況などの生活習慣を見直し、過剰分のカットや不足分の補填をしていきましょう。
「脳」が変わると「習慣」も変化する
しかし、正しい自己認識や予防や対策のための知識を獲得しても、習慣を変えることはなかなか難しいことでもあります。そこで知識や意志を持つだけではなく、脳科学の理論も活用して、悪しき習慣を良い習慣に変換する方法を試してみてはいかがでしょうか。脳科学者の岩崎一郎氏は『何をやっても続かないのは、脳がダメな自分を記憶しているからだ』で、「『習慣を変える』とは、『脳を変化させる』こと」と言っています。ここでは例として、キーワード“快”にまつわる方法を取り上げてみます。
「行動を習慣化するためには、“快”が毎回得られる必要があります。習慣化したいのであれば、どうしたら毎回同じ“快”が得られるのか工夫してみましょう」と言っています。脳へ“快”を与えることにより、習慣化が促進されます。“快”はささやかなことでかまいません。例えば、アプリで記録をとって行動を視覚化したり、身近な人に褒めてもらうようにお願いし報酬をえたりするなどでも大丈夫です。
また、「ある行動(A)をして、60秒以内に何か(B)が起こると、脳がAとBを結びつける」ことや「200回くらいの繰り返しがあって、行動の習慣化ができてくる」ため、“快”を与えるタイミングは「60秒位内」に、回数は「200回以上」を目安にします。一度習慣化されると、“快”がなくても継続していくことができるということです。
先人とアスリートに学ぶ「習慣化」
哲学者の三木清は『人生論ノート』で、「習慣を自由になし得る者は人生において多くのことをなし得る。習慣は技術的なものである故に自由にすることができる」と断言しています。45歳で2018年の平昌オリンピックの代表に選ばれ、史上初の8大会連続出場を達成したスキージャンプ界のレジェンド葛西紀明選手も、「時間がない日は10分間でもいいし、気分が乗らないときはウォーキングでもいいのです。無理をせず、継続していくことを優先させましょう」(『40歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れない体」と「折れない心」のつくり方』)と、習慣化に工夫を取り入れることがわかります。
習慣を変えて生活習慣病を予防・対策することは、簡単ではなく時間も手間もかかります。ですが不可能なことではありませんし、そのための技術や方法も提示されています。ぜひ一度、自身の生活習慣を見直してみてください。
<参考文献・参考サイト>
・『何をやっても続かないのは、脳がダメな自分を記憶しているからだ』(岩崎一郎著、クロスメディア・パブリッシング)
・『人生論ノート』(三木清、PHP研究所)
・『40歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れない体」と「折れない心」のつくり方』(葛西紀明著、東洋経済新報社)
・厚生労働省:平成28年「国民健康・栄養調査」の結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177189.html
・日本生活習慣病予防協会:40歳以降で生活習慣病が増加 【2010年国民健康・栄養調査】
http://www.seikatsusyukanbyo.com/calendar/2012/001977.php
・『何をやっても続かないのは、脳がダメな自分を記憶しているからだ』(岩崎一郎著、クロスメディア・パブリッシング)
・『人生論ノート』(三木清、PHP研究所)
・『40歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れない体」と「折れない心」のつくり方』(葛西紀明著、東洋経済新報社)
・厚生労働省:平成28年「国民健康・栄養調査」の結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177189.html
・日本生活習慣病予防協会:40歳以降で生活習慣病が増加 【2010年国民健康・栄養調査】
http://www.seikatsusyukanbyo.com/calendar/2012/001977.php
人気の講義ランキングTOP20
高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?
テンミニッツ・アカデミー編集部










