テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
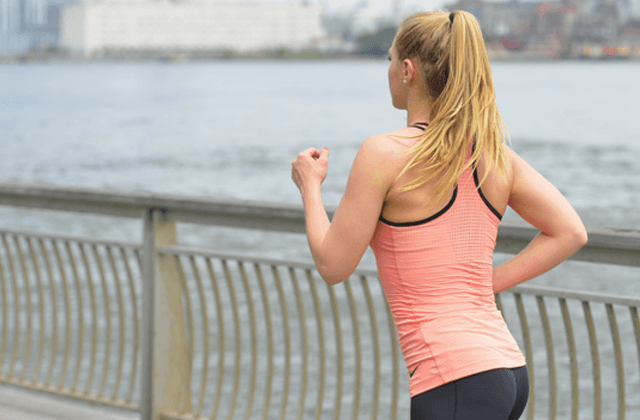
ランニングは「体に良い」とは限らない?
ランニングは健康に良い…はずが
皇居はいまやランニングの聖地。「皇居ランナー」は、平日の18時から21時の間で約4千人にのぼるといわれます。このほかにも駒沢オリンピック公園や代々木公園など多くのランニングコースが賑わっており、日本のランニング人口は1千万人を超えるとのデータも。なぜ、ここまでランニングブームが盛り上がっているのでしょうか。その理由には、2007年に初回が開催された東京マラソンをはじめとするマラソン大会の充実があげられるでしょう。参加する市民ランナーには初心者がたくさんいますし、おもしろいコスプレ姿のランナーもいるので、「自分もできそう」、「楽しそう」と感じる人が増えているのです。運動不足やメタボを心配する現代人が多い中、自分もできそうで楽しそうなスポーツをはじめる人が増えるのは自然な流れですよね。
ここで改めて注目したいのは、ランニングをはじめる動機として「体に良い」という考えが含まれている点です。しかしイギリスの医学誌『ブリティッシュメディカルジャーナル』の報告では、ランニングが寿命を縮めることもあるのだとか。それは、次のような条件を満たすランナーに見られるケースだそうです。
長く速く走るのは危険という研究結果
結論からいうとランニングをする人すべての寿命が短くなるわけではなく、「長い時間、速いスピードで走る人」が当てはまります。この条件はふたつの研究から導かれました。まず一つ目は、30年間にわたって5万6千200人を調査した研究で、対象を「ハードなランニングをする人」、「普通のランニングをする人」、「ランニングをしない人」の3グループにわけたものです。この各グループの死亡率を集計すると、普通グループはしないグループよりも19%低いという結果に。それでは週に32から40kmを走るハードグループはもっと低いかというとそんなことはなく、普通グループが最も低かったのです。
そして二つ目は、走るスピードを測定した研究です。この結果、自転車で走るのと同じくらいの時速12km以上で走る人には、心臓をいためてしまう危険性があることがわかりました。実は心臓病を専門とする医師にとって、アスリートに心房細動の発作が起きやすいことは常識です。心房細動とは不整脈の一種。脳の血管が詰まってしまう脳梗塞の3分の1は、心房細動が原因と考えられています。
『ブリティッシュメディカルジャーナル』はこの結果から、「極端なトレーニングは、過度の心臓の消耗と破壊を引き起こすと推測できる」という見解を示しています。
有酸素運動と無酸素運動のはざまで
それではなぜ、長く速く走る人は寿命が短くなってしまうのでしょうか。そこには有酸素運動と無酸素運動の境界が関係していると考えられます。有酸素運動といえばランニングやエアロビクスのような持続的な運動、無酸素運動といえば短距離走や筋トレのような瞬発的な運動というイメージを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。これは正しくもあり、間違ってもいます。
両者は運動の種類ではなく、燃焼方法で区別されるもの。有酸素運動とは酸素を炭水化物や脂肪と反応させて燃焼させる運動で、無酸素運動とは酸素を使わず糖質を燃焼させる運動です。そして、酸素の反応が間に合わないときに無酸素運動が行われます。つまり負荷が低ければ筋トレも有酸素運動になり、逆に負荷が高くなればランニングも無酸素運動になります。もちろん、この境界には個人差があります。
無酸素運動は非常手段といえる燃焼方法なので、糖質の貯蔵量はさほど多くありません。このため、長時間の無酸素運動は体に大きなダメージを与えます。「ランニングは有酸素運動だから長時間やっても大丈夫」と思ってハードすぎるトレーニングを行うと、いつの間にか無酸素運動を長時間やっていることになり、心臓や筋肉をいためてしまうのです。
無理をしないことが一番大切
負荷が強すぎるランニングの危険性には注意が必要ですが、『ブリティッシュメディカルジャーナル』の報告からもわかるように、「普通のランニングをする人」は長生きできる傾向にあります。やはり「適度な運動」は健康増進に有効なようです。しかし「適度」といわれてもどれくらいなのか、なかなかわからないですよね。その指標にできる数字のひとつが、台湾国立医療研究所の研究チームから発表されました。それによると、1日15分程度の軽めの運動で健康増進の効果があるとのことです。この研究は41万6175人の台湾人を対象に平均8年間の調査を行ったもの。運動習慣がある人とない人の全死因の死亡率を比較すると、運動している人のほうが14%低い結果となりました。しかも軽めの歩行のような低負荷の運動強度でも、明らかに死亡率が低くなっていたのです。
また、1日あたりの運動時間を15分増やすごとに死亡の可能性が4%ずつ低下することもわかりました。30分の運動を毎日行えば、寿命が約4年延びると考えられるのです。研究者たちはこの結果を踏まえ、「あまり激しくない運動を毎日15分行うことからはじめて、1日30分まで延ばすことを目標とするのがよいのではないか」と提案しています。
ランニングは強すぎる負荷で長時間続けると、健康を害してしまうことを忘れないようにしましょう。苦しくないペースで毎日少しずつ続けるのが体に良い楽しみ方です。
<参考サイト>
・WIRED:ランニングは体に良いのか、悪いのか:研究結果
https://wired.jp/2012/12/24/jogging_is_bad_for_health/
・糖尿病ネットワーク:1日15分の運動が命を延ばす 台湾で大規模研究
http://www.dm-net.co.jp/calendar/sp/2011/015779.php
・WIRED:ランニングは体に良いのか、悪いのか:研究結果
https://wired.jp/2012/12/24/jogging_is_bad_for_health/
・糖尿病ネットワーク:1日15分の運動が命を延ばす 台湾で大規模研究
http://www.dm-net.co.jp/calendar/sp/2011/015779.php
人気の講義ランキングTOP20
高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?
テンミニッツ・アカデミー編集部
歴史作家・中村彰彦先生に学ぶ歴史の探り方、活かし方
テンミニッツ・アカデミー編集部
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










