テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
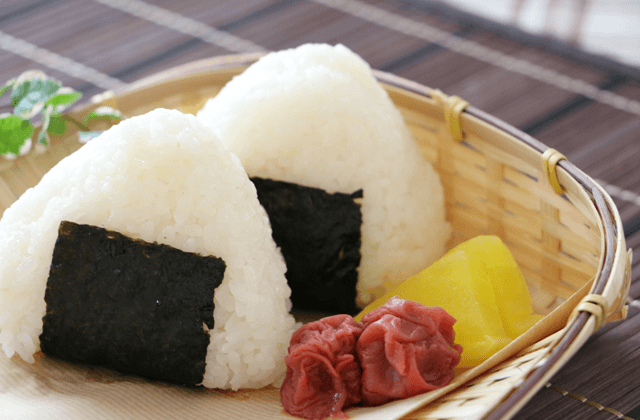
「炭水化物が寿命を縮める」のは本当か?
2017年8月29日、世界的に権威のある医学雑誌『ランセット』のオンライン版に「炭水化物の摂取増加で死亡リスク上昇」という大規模コホート研究結果が掲載され、大きな話題を呼びました。
炭水化物は人類にとっても欠かせない栄養素です。そして、もっとも身近で大切な食品であるごはんやパンなど主食の原材料である穀物の主成分で、まさに「命の主成分」ともいえる物質です。その炭水化物を摂取が寿命を縮めることにつながるとは、いったいどういうことなのでしょうか。
今回は炭水化物と死亡リスクについて、考察してみたいと思います。
炭水化物は、たんぱく質・脂質と並ぶ三大栄養素のひとつで、主にエネルギー源となる栄養素です。地球上でもっとも多量に存在する有機化合物で、その成分は「炭水化物=糖質+食物繊維」であり、最終的には糖質として体内に吸収されるため、広義には糖質または糖類ともいえます。このため、「糖質」という近年話題のキーワードも、炭水化物と深く関わっています。
また炭水化物は、人類はもとより生物にとってきわめて重要な物質であり、生物的機能にも大きく関与しています。なお、炭水化物の二大生物的機能は、「1.生物体の構成成分であること」、「2.活動のエネルギー源となること」です。このうち、2の「活動のエネルギー源となる」機能の余剰分が、現代の主に先進国における生活習慣病と密接に関係しています。
しかし消費分より摂取分のエネルギーが多くなり、余剰分のエネルギーが肥満などの原因となって悩む人にとっては、その利点はむしろマイナスの要因となってしまっています。そうした中、短期的に効果が得られやすいことから流行したのが「糖質制限」でした。方法は手軽で、「糖質(=炭水化物)を摂取しないかできるだけ少なくする」というものです。
ただし糖質制限は、脳梗塞や動脈硬化のリスクを高めるなど、危険視もされていました。その渦中に冒頭で紹介した、『ランセット』のオンライン版で、「18ヵ国の13万5千例以上を約7年半追跡」の結果、「炭水化物は、摂取量が多いほど全死亡リスクが高く、最低5分位群(エネルギー比中央値46.4%)に対する最高5分位群(同77.2%)のハザード比は1.28であった」が発表されため、多くの糖質制限愛好者に喜ばれることとなったのです。
東北大学院農研究科の都築毅准教授は、「通常食」と「糖質制限食」を与えたマウスによる実験により、糖質制限食グループは、「1.平均寿命が20~25%短命であった」、「2.背骨の曲がりや脱毛など通常食に比べて30%も早く老化が進んだ」、「3.学習能力の低下も見られた」ことを発表(『週刊新潮』)。
血液中に含まれる「インターロイキンシックス(IL-6)」という物質に注目し、糖質制限グループはIL-6の数値が通常食グループの1.5倍もあったことや、「その数値が高いとがんや糖尿病などの発症率が上がるのはもちろん、体全体の炎症を促進させる物質として知られています」と述べています。
また、女子栄養大学教授の本田佳子氏は、「血糖値をめぐる栄養学」において、「炭水化物は控えたほうがよい?」の問い対して、「もともと炭水化物をとりすぎている人が控えれば血糖コントロールが良好になります」と回答しています(『栄養と料理』)。
ただし、必要最低量あるため控えすぎは要注意なことと、「血糖値の変動範囲をなるべく一定に保つことが重要」なため、糖質は3食均等に控えることもあわせて提言。あくまでも個々人の状況にあわせて、食生活の基本である「量・タイミング・バランス」を適切に保つことを呼びかけています。
食べることは生きること。寿命を延ばすことも大切ですが、生きている間の「生活の質(QOL)」も大切にしたいものです。
炭水化物は人類にとっても欠かせない栄養素です。そして、もっとも身近で大切な食品であるごはんやパンなど主食の原材料である穀物の主成分で、まさに「命の主成分」ともいえる物質です。その炭水化物を摂取が寿命を縮めることにつながるとは、いったいどういうことなのでしょうか。
今回は炭水化物と死亡リスクについて、考察してみたいと思います。
そもそも炭水化物とは?人類との関係は?
米、麦、とうもろこし、アワ、ヒエ、キビなど、世界中で命の源である主食として大切にされてきた穀物ですが、その主要成分は炭水化物でできています。炭水化物は、たんぱく質・脂質と並ぶ三大栄養素のひとつで、主にエネルギー源となる栄養素です。地球上でもっとも多量に存在する有機化合物で、その成分は「炭水化物=糖質+食物繊維」であり、最終的には糖質として体内に吸収されるため、広義には糖質または糖類ともいえます。このため、「糖質」という近年話題のキーワードも、炭水化物と深く関わっています。
また炭水化物は、人類はもとより生物にとってきわめて重要な物質であり、生物的機能にも大きく関与しています。なお、炭水化物の二大生物的機能は、「1.生物体の構成成分であること」、「2.活動のエネルギー源となること」です。このうち、2の「活動のエネルギー源となる」機能の余剰分が、現代の主に先進国における生活習慣病と密接に関係しています。
炭水化物は人類の敵!?摂取制限が必要?
人類も動物である以上、もともと今より動いていました。また動物にとって、食物確保は生命維持にとってなにより重要な、文字通り命がけの生存のための行為です。全ての人類にとっても、本来は一番の重労働でありました。そのような状況においては、高エネルギー食品である炭水化物は、効率よくエネルギーを確保できるスーパーフードです。しかし消費分より摂取分のエネルギーが多くなり、余剰分のエネルギーが肥満などの原因となって悩む人にとっては、その利点はむしろマイナスの要因となってしまっています。そうした中、短期的に効果が得られやすいことから流行したのが「糖質制限」でした。方法は手軽で、「糖質(=炭水化物)を摂取しないかできるだけ少なくする」というものです。
ただし糖質制限は、脳梗塞や動脈硬化のリスクを高めるなど、危険視もされていました。その渦中に冒頭で紹介した、『ランセット』のオンライン版で、「18ヵ国の13万5千例以上を約7年半追跡」の結果、「炭水化物は、摂取量が多いほど全死亡リスクが高く、最低5分位群(エネルギー比中央値46.4%)に対する最高5分位群(同77.2%)のハザード比は1.28であった」が発表されため、多くの糖質制限愛好者に喜ばれることとなったのです。
反論!糖質「制限」こそが寿命を縮める!?
しかし、本当に炭水化物を摂取すると死亡リスクはたかまる、言いかえると糖質制限をしないと寿命は縮まるのでしょうか。東北大学院農研究科の都築毅准教授は、「通常食」と「糖質制限食」を与えたマウスによる実験により、糖質制限食グループは、「1.平均寿命が20~25%短命であった」、「2.背骨の曲がりや脱毛など通常食に比べて30%も早く老化が進んだ」、「3.学習能力の低下も見られた」ことを発表(『週刊新潮』)。
血液中に含まれる「インターロイキンシックス(IL-6)」という物質に注目し、糖質制限グループはIL-6の数値が通常食グループの1.5倍もあったことや、「その数値が高いとがんや糖尿病などの発症率が上がるのはもちろん、体全体の炎症を促進させる物質として知られています」と述べています。
また、女子栄養大学教授の本田佳子氏は、「血糖値をめぐる栄養学」において、「炭水化物は控えたほうがよい?」の問い対して、「もともと炭水化物をとりすぎている人が控えれば血糖コントロールが良好になります」と回答しています(『栄養と料理』)。
ただし、必要最低量あるため控えすぎは要注意なことと、「血糖値の変動範囲をなるべく一定に保つことが重要」なため、糖質は3食均等に控えることもあわせて提言。あくまでも個々人の状況にあわせて、食生活の基本である「量・タイミング・バランス」を適切に保つことを呼びかけています。
生活の質の見直しも大切
人類に限らず生物の死亡率は、「今のところ」と前置きをしたとしても、100%です。何を食べても、また何かを食べなくても、いずれ寿命はつきます。また、どんなにがんばって食べ物に気を配ったとしても、大前提として何かを食べないことには生きていくことはできません。食べることは生きること。寿命を延ばすことも大切ですが、生きている間の「生活の質(QOL)」も大切にしたいものです。
<参考文献・参考サイト>
・『週刊新潮』(2018年4月5日号、新潮社)
・『栄養と料理』(2015年12月号、女子栄養大学出版部)
・CareNet:炭水化物の摂取増加で死亡リスク上昇/Lancet
https://www.carenet.com/news/journal/carenet/44610
・『週刊新潮』(2018年4月5日号、新潮社)
・『栄養と料理』(2015年12月号、女子栄養大学出版部)
・CareNet:炭水化物の摂取増加で死亡リスク上昇/Lancet
https://www.carenet.com/news/journal/carenet/44610
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部










