テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
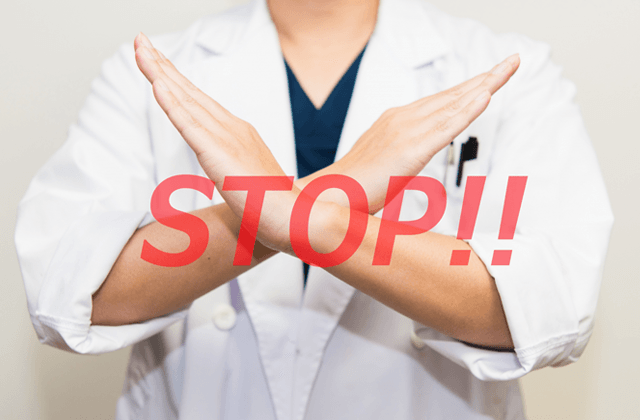
高血圧に動脈硬化…塩分の取り過ぎと病気の関係
塩分は人間のみならず生物が生きていくために欠かせないミネラルですが、取り過ぎるとさまざまな病気を誘引するとされています。今回は、塩分の取り過ぎと病気の関係を考察してみたいと思います。
まずは高血圧です。塩分の取り過ぎが血圧を上昇させることがこれまでの多くの研究で明らかとされており、特に日本人の高血圧の原因は「食塩の取り過ぎ」が圧倒的に多くなっています(『よくわかる塩分1日6gで血圧を正常化するおいしい食事』)。
医学博士・管理栄養士の本多京子氏は、著書『塩分が日本人を滅ぼす』において、「高血圧が怖いのは、それを繰り返しているうちに血管がダメになる」こと、そして「血管の老化は“動脈硬化”という形で表れ」て、脳出血や心筋梗塞等を引き起こす要因となると述べています。
また同書において本多氏は、塩分の取り過ぎは日常的な腎臓の酷使につながり、中高年になってから腎臓病を発症するケースが増えることなども示唆しています。
さらには胃がんリスクも高めるといいます。もっとも、女子栄養大学学園長・医学博士の香川芳子氏は著書『食卓の品格』において、「塩自体に発がん性があるわけではないのです<中略>塩の場合、胃粘膜のバリアーを壊すのが大きな原因といわれています」と述べています。
長崎大学病院助教で泌尿器科・腎移植外科医の松尾朋博氏が、食事でとる塩分量を減らすことにより、頻尿が改善されるという調査結果を発表しました(『朝日新聞』2018年5月1日付)。
松尾氏の研究結果を裏づけるような、減塩と頻尿改善の「正の相関関係」を示している自治体が山梨県です。山梨県では自治体レベルで減塩に取り組み、見事「頻尿が少ない都道府県ランキング」で1位となっています(『健康』2018年4月号)。
山梨県では県民への減塩指導として、食生活改善推進員・通称「ショッカイさん」が各家庭を回って料理の塩分濃度をチェックするほか、減塩に役立つ資料を配付したり具体的な減塩のコツを伝授しています。
ではなぜ減塩が頻尿に効果的なのでしょうか。東京都リハビリテーション病院副院長で泌尿器科医の鈴木康之氏は、以下の2点から頻尿改善の可能性を解説しています。
1)塩分摂取量が多いと、のどが渇きやすくなり水分摂取量も増え頻尿の原因となるが、減塩することにより水分量を適正にすることができ、頻尿が改善される。
2)塩分の取り過ぎにより高血圧になると、血管の老化が進み全身の血流が悪くなる。それによって膀胱や脳の老化を早め頻尿の原因となるが、減塩することによって予防することができる。
例えば、栄養面でもすばらしいといわれる和食の唯一ともいわれる欠点は「塩分量が多い」ことです。WHOの塩分摂取量の目標値である「成人1日あたり5g未満」の約2倍にあたる、男性10.8g・女性9.2g の食塩を平均して摂取しているといわれています(「平成28年国民健康・栄養調査結果の概要」2017年9月21日発表)。
加えて、『食卓の品格』の著者・香川氏によると、遺伝子の研究が進んだことにより、白人に比べて日本人には塩分をため込みやすい遺伝子を持つ人が多いことがわかってきたといいます。そこで香川氏は、あくまでも塩分の取り方に十分な注意を促しながらも、塩分の高い食事をとるのなら「時間栄養学」の考えを生活に取り入れ、塩分排出が多い夕食にとることもすすめています。
塩分は生理的必需品であり、料理をおいしくしてくれる最高の調味料でもあります。ですがやはり、摂り過ぎは病気のリスクを高めるようです。減塩を心がけ、体にもよい適塩な食生活を送りたいものです。
塩分の取り過ぎは万病の元?
塩分の取り過ぎでリスクが高まる病気の一例を取り上げてみましょう。まずは高血圧です。塩分の取り過ぎが血圧を上昇させることがこれまでの多くの研究で明らかとされており、特に日本人の高血圧の原因は「食塩の取り過ぎ」が圧倒的に多くなっています(『よくわかる塩分1日6gで血圧を正常化するおいしい食事』)。
医学博士・管理栄養士の本多京子氏は、著書『塩分が日本人を滅ぼす』において、「高血圧が怖いのは、それを繰り返しているうちに血管がダメになる」こと、そして「血管の老化は“動脈硬化”という形で表れ」て、脳出血や心筋梗塞等を引き起こす要因となると述べています。
また同書において本多氏は、塩分の取り過ぎは日常的な腎臓の酷使につながり、中高年になってから腎臓病を発症するケースが増えることなども示唆しています。
さらには胃がんリスクも高めるといいます。もっとも、女子栄養大学学園長・医学博士の香川芳子氏は著書『食卓の品格』において、「塩自体に発がん性があるわけではないのです<中略>塩の場合、胃粘膜のバリアーを壊すのが大きな原因といわれています」と述べています。
減塩で頻尿も改善?
大病以外の身近な体質にも、塩分は関係しています。長崎大学病院助教で泌尿器科・腎移植外科医の松尾朋博氏が、食事でとる塩分量を減らすことにより、頻尿が改善されるという調査結果を発表しました(『朝日新聞』2018年5月1日付)。
松尾氏の研究結果を裏づけるような、減塩と頻尿改善の「正の相関関係」を示している自治体が山梨県です。山梨県では自治体レベルで減塩に取り組み、見事「頻尿が少ない都道府県ランキング」で1位となっています(『健康』2018年4月号)。
山梨県では県民への減塩指導として、食生活改善推進員・通称「ショッカイさん」が各家庭を回って料理の塩分濃度をチェックするほか、減塩に役立つ資料を配付したり具体的な減塩のコツを伝授しています。
ではなぜ減塩が頻尿に効果的なのでしょうか。東京都リハビリテーション病院副院長で泌尿器科医の鈴木康之氏は、以下の2点から頻尿改善の可能性を解説しています。
1)塩分摂取量が多いと、のどが渇きやすくなり水分摂取量も増え頻尿の原因となるが、減塩することにより水分量を適正にすることができ、頻尿が改善される。
2)塩分の取り過ぎにより高血圧になると、血管の老化が進み全身の血流が悪くなる。それによって膀胱や脳の老化を早め頻尿の原因となるが、減塩することによって予防することができる。
減塩・適塩で体にもおいしい食生活を
日本人は、世界的にみても塩分を取り過ぎているといわれています。例えば、栄養面でもすばらしいといわれる和食の唯一ともいわれる欠点は「塩分量が多い」ことです。WHOの塩分摂取量の目標値である「成人1日あたり5g未満」の約2倍にあたる、男性10.8g・女性9.2g の食塩を平均して摂取しているといわれています(「平成28年国民健康・栄養調査結果の概要」2017年9月21日発表)。
加えて、『食卓の品格』の著者・香川氏によると、遺伝子の研究が進んだことにより、白人に比べて日本人には塩分をため込みやすい遺伝子を持つ人が多いことがわかってきたといいます。そこで香川氏は、あくまでも塩分の取り方に十分な注意を促しながらも、塩分の高い食事をとるのなら「時間栄養学」の考えを生活に取り入れ、塩分排出が多い夕食にとることもすすめています。
塩分は生理的必需品であり、料理をおいしくしてくれる最高の調味料でもあります。ですがやはり、摂り過ぎは病気のリスクを高めるようです。減塩を心がけ、体にもよい適塩な食生活を送りたいものです。
<参考サイト>
・『よくわかる塩分1日6gで血圧を正常化するおいしい食事』(忍田聡子指導・監修、主婦の友社編、主婦の友社)
・『塩分が日本人を滅ぼす』(本多京子著、幻冬舎新書)
・『食卓の品格』(香川芳子著、幻冬舎ルネッサンス新書)
・『健康』2018年4月号(主婦の友インフォス):「頻尿改善」日本一!」、
・『朝日新聞』(2018年5月1日付):塩分減らすと…おしっこ回数減 頻尿改善、長崎大が調査
https://www.asahi.com/articles/ASL4T42SVL4TULBJ006.html
・厚生労働省:平成28年国民健康・栄養調査結果の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/kekkagaiyou_7.pdf
・『よくわかる塩分1日6gで血圧を正常化するおいしい食事』(忍田聡子指導・監修、主婦の友社編、主婦の友社)
・『塩分が日本人を滅ぼす』(本多京子著、幻冬舎新書)
・『食卓の品格』(香川芳子著、幻冬舎ルネッサンス新書)
・『健康』2018年4月号(主婦の友インフォス):「頻尿改善」日本一!」、
・『朝日新聞』(2018年5月1日付):塩分減らすと…おしっこ回数減 頻尿改善、長崎大が調査
https://www.asahi.com/articles/ASL4T42SVL4TULBJ006.html
・厚生労働省:平成28年国民健康・栄養調査結果の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/kekkagaiyou_7.pdf
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部










