テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
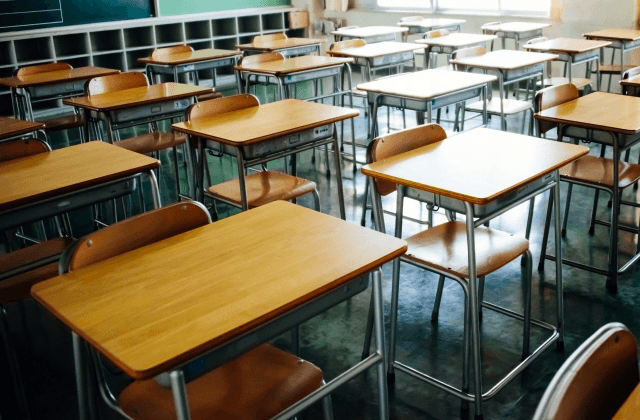
昔よりひどい?現代の「ブラック校則」の理不尽
2013年に流行語大賞トップテンにも選ばれた「ブラック企業」という言葉によって、「ブラック研修」や「ブラックバイト」など、産業界や社会に潜む闇が明るみになってきました。
それにともない、“ブラック○○”は産業構造や大人の世界だけの問題ではなく、子どもの世界にも潜んでいることが可視化されるようになり、「ブラック校則」や「ブラック部活動」などが社会問題として取り沙汰され、研究や調査の対象として真剣に考えられるようになってきました。
今回は、現代的課題としての「ブラック校則」について、考察してみたいと思います。
この報道をきっかけに、有志による「ブラック校則をなくそう! プロジェクト」(以下「プロジェクト」)が発足され、校則についての量的調査と質的調査の2つ実態調査が行われることとなりました。
量的調査は2018年2月、10代(15歳以上)から50代の男女2000人を対象に、人口動態の比率に合わせてランダムサンプリングを行い、うち1000人には中学生時の経験を、残り1000人には高校生時の経験を聞き、さらに予備調査を通じて「中高生の親である人」より抽出された現役中学生の保護者1000人と、現役高校生の保護者1000人に、調査会社を通じた4種類のアンケートによって実施されました。
その結果、校則にはトレンドがあるものの、以下のように近年になってむしろ増加傾向にある項目が多数判明するなど、現代の10代の方がかつてより校則が厳しくなっている傾向が判明しました。
【黒染め強要】
中学時代:10代・2.5%、20代・1.2%、30代・1.9%、40代・0.4%、50代・0.0%。
高校時代:10代・6.3%、20代・3.0%、30代・1.9%、40代・0.0%、50代・0.9%。
【スカートの長さ指定】
中学時代:10代:57.0%、20代・38.1%、30代・23.7%、40代・40.4%、50代・34.7%。
高校時代:10代・48.1%、20代・32.1%、30代・27.5%、40代・25.6%、50代・30.5%。
【下着の色指定】
中学時代:10代・15.8%、20代・4.8%、30代・1.9%、40代・3.2%、50代・0.9%。
高校時代:10代・11.4%、20代・7.1%、30代・1.4%、40代・1.6%、50代・0.9%。
【整髪料の使用禁止】
中学時代:10代・38.6%、20代・19.6%、30代・10.4%、40代・10.0%、50代・7.0%。
高校時代:10代・29.1%、20代・12.5%、30代・4.3%、40代・6.8%、50代・3.8%。
1)髪染めの強要:生まれつき茶髪であっても髪を黒くすることを強要したり、「地毛証明書」を要求したりする。
2)パーマ禁止:特に「くせ毛」の生徒たちがターゲットとして「指導被害」にあったり、ストレートパーマをかけることを強要したりする。
3)細かな毛髪指導:茶髪やパーマの禁止のようなブラックリスト方式ではなく、「肩にかかれば結ぶ」「眉毛にかかってはいけない」など、細かい規定をするホワイトリスト方式をとる学校も珍しくない。
4)服装規定:生徒手帳に明文化されていることにとどまらず、スカートや靴下の長さの指定やそれを確認するための測定や、「どんなに寒くても指定服以外のものを着てはいけない」「マフラーやタイツなども着用禁止」といった防寒や暑さ対策の禁止などが行われている。
5)セクハラ的指導:「下着の色は白のみ」など下着の色の指定をするだけでなく、ルールが守られているかを確認する「下着チェック」が増加していたり、「汗をかくから」という理由で体操服の下に肌着の着用が禁止されていたりするなど、細かな規制による管理が以前より強化されている。
6)差別を生む校則:知的・身体・発達障害、精神疾患、セクシャル・宗教・出身国など、さまざまな属性をもつ多様なマイノリティに対し、校則が排除の原理として機能する場面が少なくないことにより、多くの当事者にストレスを与える温床となっている。
7)部則:「一科目でも赤点を取れば丸坊主」「参加の強制や独自の罰則がある」など、部活動単位で行っている「部則」が存在し、悪しき伝統になっているケースがある。
8)健康被害・経済的打撃:「日焼け止めの禁止」による皮膚の炎症や「足に合わない革靴の強要」による足の痛みと歩行困難などの健康被害、健康被害の治療や過剰な校則遵守のためや割高な指定品購入による経済的打撃など。
9)校則の変更提案を止められた:1)~8)のような多数の問題校則について、異議申し立てを行ったり変更を求めたりする動きを禁じられたり、告発自体が潰されたり受け入れなかったりすることが多々ある。
荻上氏は、「ブラック校則は“昔はあったかもしれないけど”ではなく、現在もれっきとして存在する問題」であるとまとめながらも、「理不尽というのは耐えるものではなく、理不尽な状況を変えるか、身を守るなり逃げるなりするもの」であり、そのための手段を大人が確保する義務があることや、子どもの視点で校則の見直しを行う必要性を提言しています。
“ブラック○○”の元祖もいえる「ブラック企業」に対しては、厚生労働省が2015年より「過重労働撲滅特別対策班」(通称「かとく」)を設置して労働基準監督署による監督を強化するなど、社会全体が撲滅に本腰を入れてきています。しかし「ブラック校則」に対しては、まだ調査や議論ですら不十分と言わざるを得ない現状です。
内田氏は、「ブラック校則」の話題が前述の「たった“一人”の若者」が声を上げたことから始まったこと。そして、「ブラック校則」を見直す機運が高まっている今こそ、社会全体で知恵を出し合い、声をあげていかなければならないこと。その上で、「ブラック校則」という一部の問題を通して、社会全体にとって「一部の問題を、私たちみんなで考えていくという姿勢」の大切さと必要性を呼びかけています。
それにともない、“ブラック○○”は産業構造や大人の世界だけの問題ではなく、子どもの世界にも潜んでいることが可視化されるようになり、「ブラック校則」や「ブラック部活動」などが社会問題として取り沙汰され、研究や調査の対象として真剣に考えられるようになってきました。
今回は、現代的課題としての「ブラック校則」について、考察してみたいと思います。
理不尽な「ブラック校則」は増加している?
「ブラック校則」の話題は、2017年に端を発しています。この年、大阪府の公立高校に通学する生まれつき茶髪の生徒が、髪色を黒く染めるよう学校から強要されたことにより精神的苦痛を受けたとして、裁判を起こしました。この報道をきっかけに、有志による「ブラック校則をなくそう! プロジェクト」(以下「プロジェクト」)が発足され、校則についての量的調査と質的調査の2つ実態調査が行われることとなりました。
量的調査は2018年2月、10代(15歳以上)から50代の男女2000人を対象に、人口動態の比率に合わせてランダムサンプリングを行い、うち1000人には中学生時の経験を、残り1000人には高校生時の経験を聞き、さらに予備調査を通じて「中高生の親である人」より抽出された現役中学生の保護者1000人と、現役高校生の保護者1000人に、調査会社を通じた4種類のアンケートによって実施されました。
その結果、校則にはトレンドがあるものの、以下のように近年になってむしろ増加傾向にある項目が多数判明するなど、現代の10代の方がかつてより校則が厳しくなっている傾向が判明しました。
【黒染め強要】
中学時代:10代・2.5%、20代・1.2%、30代・1.9%、40代・0.4%、50代・0.0%。
高校時代:10代・6.3%、20代・3.0%、30代・1.9%、40代・0.0%、50代・0.9%。
【スカートの長さ指定】
中学時代:10代:57.0%、20代・38.1%、30代・23.7%、40代・40.4%、50代・34.7%。
高校時代:10代・48.1%、20代・32.1%、30代・27.5%、40代・25.6%、50代・30.5%。
【下着の色指定】
中学時代:10代・15.8%、20代・4.8%、30代・1.9%、40代・3.2%、50代・0.9%。
高校時代:10代・11.4%、20代・7.1%、30代・1.4%、40代・1.6%、50代・0.9%。
【整髪料の使用禁止】
中学時代:10代・38.6%、20代・19.6%、30代・10.4%、40代・10.0%、50代・7.0%。
高校時代:10代・29.1%、20代・12.5%、30代・4.3%、40代・6.8%、50代・3.8%。
現在的課題である、9種別の「ブラック校則」
一方、質的調査は2017年12月以降、プロジェクトが設置したウェブサイトの投稿フォームと個別ヒアリングによって収集されました。そのうちの投稿フォームに集まった2010年以降の具体的事例を、評論家でプロジェクトのスーパーバイザーかつ、『ブラック校則』の編著者の一人である荻上チキ氏が、大きく以下の9種別にまとめています。1)髪染めの強要:生まれつき茶髪であっても髪を黒くすることを強要したり、「地毛証明書」を要求したりする。
2)パーマ禁止:特に「くせ毛」の生徒たちがターゲットとして「指導被害」にあったり、ストレートパーマをかけることを強要したりする。
3)細かな毛髪指導:茶髪やパーマの禁止のようなブラックリスト方式ではなく、「肩にかかれば結ぶ」「眉毛にかかってはいけない」など、細かい規定をするホワイトリスト方式をとる学校も珍しくない。
4)服装規定:生徒手帳に明文化されていることにとどまらず、スカートや靴下の長さの指定やそれを確認するための測定や、「どんなに寒くても指定服以外のものを着てはいけない」「マフラーやタイツなども着用禁止」といった防寒や暑さ対策の禁止などが行われている。
5)セクハラ的指導:「下着の色は白のみ」など下着の色の指定をするだけでなく、ルールが守られているかを確認する「下着チェック」が増加していたり、「汗をかくから」という理由で体操服の下に肌着の着用が禁止されていたりするなど、細かな規制による管理が以前より強化されている。
6)差別を生む校則:知的・身体・発達障害、精神疾患、セクシャル・宗教・出身国など、さまざまな属性をもつ多様なマイノリティに対し、校則が排除の原理として機能する場面が少なくないことにより、多くの当事者にストレスを与える温床となっている。
7)部則:「一科目でも赤点を取れば丸坊主」「参加の強制や独自の罰則がある」など、部活動単位で行っている「部則」が存在し、悪しき伝統になっているケースがある。
8)健康被害・経済的打撃:「日焼け止めの禁止」による皮膚の炎症や「足に合わない革靴の強要」による足の痛みと歩行困難などの健康被害、健康被害の治療や過剰な校則遵守のためや割高な指定品購入による経済的打撃など。
9)校則の変更提案を止められた:1)~8)のような多数の問題校則について、異議申し立てを行ったり変更を求めたりする動きを禁じられたり、告発自体が潰されたり受け入れなかったりすることが多々ある。
荻上氏は、「ブラック校則は“昔はあったかもしれないけど”ではなく、現在もれっきとして存在する問題」であるとまとめながらも、「理不尽というのは耐えるものではなく、理不尽な状況を変えるか、身を守るなり逃げるなりするもの」であり、そのための手段を大人が確保する義務があることや、子どもの視点で校則の見直しを行う必要性を提言しています。
「ブラック校則」は社会全体の問題
『ブラック校則』の編著者のもう一人、名古屋大学大学院教育発達科学研究科准教授で教育社会学が専門の内田良氏は、「理不尽に制限することで、学校の日常をやりくりしやすくする。その意味では、指導に合理性がないわけではない。でもそれが、人権の目から見て正しいのか、個を尊重できているのか、という検討が必要」と述べています。“ブラック○○”の元祖もいえる「ブラック企業」に対しては、厚生労働省が2015年より「過重労働撲滅特別対策班」(通称「かとく」)を設置して労働基準監督署による監督を強化するなど、社会全体が撲滅に本腰を入れてきています。しかし「ブラック校則」に対しては、まだ調査や議論ですら不十分と言わざるを得ない現状です。
内田氏は、「ブラック校則」の話題が前述の「たった“一人”の若者」が声を上げたことから始まったこと。そして、「ブラック校則」を見直す機運が高まっている今こそ、社会全体で知恵を出し合い、声をあげていかなければならないこと。その上で、「ブラック校則」という一部の問題を通して、社会全体にとって「一部の問題を、私たちみんなで考えていくという姿勢」の大切さと必要性を呼びかけています。
<参考文献・参考サイト>
・『ブラック校則』(荻上チキ・内田良編著、東洋館出版社)
・「地毛証明書」、『イミダス2018』(菊地栄治著、集英社)
・「ブラック企業」、『現代用語の基礎知識 2018』(自由国民社)
・ブラック校則をなくそう!プロジェクト
https://www.black-kousoku.org/
・ブラック校則 | 東洋館出版社
http://www.toyokan.co.jp/special/book/black-kousoku/
・『ブラック校則』(荻上チキ・内田良編著、東洋館出版社)
・「地毛証明書」、『イミダス2018』(菊地栄治著、集英社)
・「ブラック企業」、『現代用語の基礎知識 2018』(自由国民社)
・ブラック校則をなくそう!プロジェクト
https://www.black-kousoku.org/
・ブラック校則 | 東洋館出版社
http://www.toyokan.co.jp/special/book/black-kousoku/
人気の講義ランキングTOP20
2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る
テンミニッツ・アカデミー編集部










