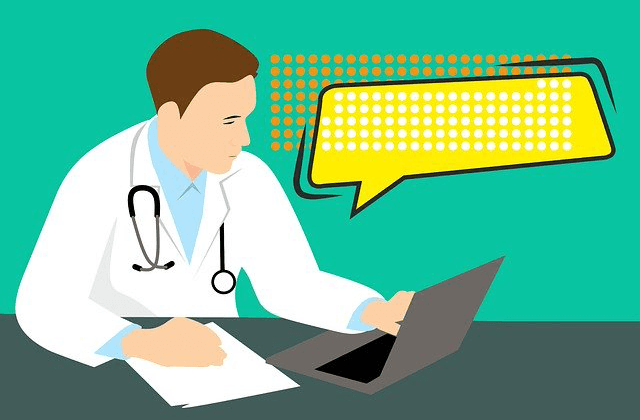
在宅でOKの「オンライン診療」で気を付けること
新型コロナウイルスの感染拡大が続くなかで「オンライン診療」があらためて脚光を浴びています。政府は2020年4月7日、オンライン診療の初診の解禁を決定しました。
オンライン診療の初診解禁について、もともと厚生労働省は反対していましたが、時限的な措置として当初の方針を見直しました。解禁後は利用者が急増しているようです。
もしかしたら今後、読者の皆さんもオンライン診療を利用する機会があるかもしれません。そんな時、オンライン診療の手続きや仕組みや注意点を簡単にでも知っておくと役に立ちます。
「オンライン診療」の対となる言葉に「対面診療」があります。対面診療は病院でお医者さんに会って診察してもらう方法です。つまり、これまで皆さんがおこなっていた、ごくごくフツーの診療方法を対面診療と呼びます。
スマホやタブレットがあり、インターネット環境が整ったら、オンライン診療のための専用アプリケーションをダウンロードすることが必要になる場合もあります。アプリケーションには「クリニクス」や「ポケットドクター」などがありますが、病院によって利用するアプリケーションは異なるのでよく確認してください。
このような情報通信機器に不慣れな方がいることを配慮し、電話によるオンライン診療も認められています。
まずは、かかりつけ医に相談することをおすすめします。かかりつけ医がいない場合も、最寄りの医療機関で探すようにしましょう。なぜかというと、医師の判断によっては、オンライン診療ではなく、すぐに医療機関を受診する必要が出てくる可能性があるからです。
薬の処方を受けた場合は、薬を出してもらう薬局を医療機関に伝えたうえで、診察後、薬局に連絡してください。電話やオンラインによる服薬指導を受け、その後、薬が配送されてきます。場合によっては、薬局に行って服薬指導を受けなければならないこともあります。
オンライン診療の初診は3割負担で最大でも「642円」です。対面診療より割安な価格設定となっています。支払い方法は「次回の来院時に合算する」、「クレジットカードによる請求」等が考えられます。先ほども書いた通り、診療する医療機関に確認してください。
希望する日時に受診することができますし、オンラインなら24時間いつでも予約することができるでしょう。待ち時間がないばかりか、自宅で診察できるので、通院時間もありません。時間の制約からかなり自由になれるのです。支払いも簡単にカードで済ませられますし、薬も自宅に届けてもらえます。
デメリットとしては、スマホやタブレットによる操作が必要になるため、そうした機器がなしには診療できないことです。また、操作に不慣れな人にとっては大きなストレスになります。支払いを含めたさまざまな手続きが医療機関によってまちまちで、まだ簡便とは言いがたい状態です。また、医師からすると患者の情報が制限されるため、誤診の可能性も高くなります。メリットとデメリットの両方を踏まえたうえで利用するようにしましょう。
そもそもオンライン診療は2018年4月から保険診療での利用が可能となったかなり新しい診療方法です。施設基準、算定基準等、適用できる疾患にも条件があり、多くの医療施設でシステム導入など対応が追いついていないのが現状です。対応できる医療機関はわずか1パーセント程度だと言われています。そんななかで、2020年4月の診療報酬改定や、新型コロナウィルス感染症対策により条件が変更され、時限的な措置ではありますが、受診する患者が増加しています。
はからずも解禁されオンライン診療が身近になったこの経験が、もしかしたら今後の医療の形を変えていくかもしれません。将来のことを抜きにしても、オンライン診療の知識を得ることは大切です。自分が診察する立場になったとき、少しでもスムーズに受診できれば、一人当たりの受診時間が減り、お医者さんはより多くの患者さんを診療できるようになります。一人ひとりのこうしたちょっとした思いやりのある行動が、新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるためには、今どうしても必要です。
オンライン診療の初診解禁について、もともと厚生労働省は反対していましたが、時限的な措置として当初の方針を見直しました。解禁後は利用者が急増しているようです。
もしかしたら今後、読者の皆さんもオンライン診療を利用する機会があるかもしれません。そんな時、オンライン診療の手続きや仕組みや注意点を簡単にでも知っておくと役に立ちます。
「オンライン診療」と「対面診療」
そもそも「オンライン診療」とは何か。オンライン診療とは、一言でいうと、スマホやタブレットなどのデバイスを使って、病院の予約も決済も含めて、インターネット上でおこなう診察方法のことです。「オンライン診療」の対となる言葉に「対面診療」があります。対面診療は病院でお医者さんに会って診察してもらう方法です。つまり、これまで皆さんがおこなっていた、ごくごくフツーの診療方法を対面診療と呼びます。
オンライン診療は電話でもOK?
対面診療は病院にさえ行きさえすれば診療することができますが、オンライン診療の場合はスマホやタブレットなどの通信機器と通信環境が必要になります。スマホやタブレットがあり、インターネット環境が整ったら、オンライン診療のための専用アプリケーションをダウンロードすることが必要になる場合もあります。アプリケーションには「クリニクス」や「ポケットドクター」などがありますが、病院によって利用するアプリケーションは異なるのでよく確認してください。
このような情報通信機器に不慣れな方がいることを配慮し、電話によるオンライン診療も認められています。
まずは「かかりつけ医」or「最寄りの医療機関」に相談を
厚生労働省が発表しているガイドに沿って、オンライン診療のダンドリをあらためて説明します。まずは受診したい医療機関に電話で確認するか、ホームページを確認するなどして、電話やオンラインによる診療を行っているかを確認してください。電話で連絡する際は、手元に保険証を用意しておきましょう。このとき、支払いの方法、診療時に必要なものについての確認も忘れずに。まずは、かかりつけ医に相談することをおすすめします。かかりつけ医がいない場合も、最寄りの医療機関で探すようにしましょう。なぜかというと、医師の判断によっては、オンライン診療ではなく、すぐに医療機関を受診する必要が出てくる可能性があるからです。
オンライン初診は最大642円
予約の時間に病院から電話が来るか、オンラインで接続されることで、診療は開始します。はじめに本人確認があると思います。求められた個人情報をスムーズに伝えられるように準備しておきましょう。その後、症状を説明します。診療後に医療機関にて対面資料を受診するように推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。薬の処方を受けた場合は、薬を出してもらう薬局を医療機関に伝えたうえで、診察後、薬局に連絡してください。電話やオンラインによる服薬指導を受け、その後、薬が配送されてきます。場合によっては、薬局に行って服薬指導を受けなければならないこともあります。
オンライン診療の初診は3割負担で最大でも「642円」です。対面診療より割安な価格設定となっています。支払い方法は「次回の来院時に合算する」、「クレジットカードによる請求」等が考えられます。先ほども書いた通り、診療する医療機関に確認してください。
オンライン診療のメリットとデメリット
今は必要に迫られて利用することになっていますが、オンライン診療のメリットとは何でしょうか。大きなメリットは病院につきものの「待ち時間」がなくなることでしょう。希望する日時に受診することができますし、オンラインなら24時間いつでも予約することができるでしょう。待ち時間がないばかりか、自宅で診察できるので、通院時間もありません。時間の制約からかなり自由になれるのです。支払いも簡単にカードで済ませられますし、薬も自宅に届けてもらえます。
デメリットとしては、スマホやタブレットによる操作が必要になるため、そうした機器がなしには診療できないことです。また、操作に不慣れな人にとっては大きなストレスになります。支払いを含めたさまざまな手続きが医療機関によってまちまちで、まだ簡便とは言いがたい状態です。また、医師からすると患者の情報が制限されるため、誤診の可能性も高くなります。メリットとデメリットの両方を踏まえたうえで利用するようにしましょう。
そもそもオンライン診療は2018年4月から保険診療での利用が可能となったかなり新しい診療方法です。施設基準、算定基準等、適用できる疾患にも条件があり、多くの医療施設でシステム導入など対応が追いついていないのが現状です。対応できる医療機関はわずか1パーセント程度だと言われています。そんななかで、2020年4月の診療報酬改定や、新型コロナウィルス感染症対策により条件が変更され、時限的な措置ではありますが、受診する患者が増加しています。
はからずも解禁されオンライン診療が身近になったこの経験が、もしかしたら今後の医療の形を変えていくかもしれません。将来のことを抜きにしても、オンライン診療の知識を得ることは大切です。自分が診察する立場になったとき、少しでもスムーズに受診できれば、一人当たりの受診時間が減り、お医者さんはより多くの患者さんを診療できるようになります。一人ひとりのこうしたちょっとした思いやりのある行動が、新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるためには、今どうしても必要です。
<参考サイト>
・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html
・初診からOKオンライン診療 手続きは? 値段は? <Q&A>│東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202004/CK2020041602100016.html
・<新型コロナ>初診オンライン、来週から 処方薬、配送で受け取り│東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202004/CK2020041102000180.html
・【患者編】オンライン診療とは? ~利用するためにはどうすればいいの?~│MedionLife
https://medionlife.jp/article6/
・オンライン診療の利用方法とメリット| オンライン診療(遠隔診療)サービス「スマホ診」
https://www.sumahoshin.or.jp/lab/online-medicalcare/merit/
・オンライン診療サービスcuron(クロン)によるオンライン診療/相談の対応をご検討の医療機関向けに導入サポートのご案内│curon
https://curon.co/covid19clinic/
・オンライン診療導入ガイド│Integrity Healthcare
https://www.integrity-healthcare.co.jp/telemedicine-guide#patient
・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html
・初診からOKオンライン診療 手続きは? 値段は? <Q&A>│東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202004/CK2020041602100016.html
・<新型コロナ>初診オンライン、来週から 処方薬、配送で受け取り│東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202004/CK2020041102000180.html
・【患者編】オンライン診療とは? ~利用するためにはどうすればいいの?~│MedionLife
https://medionlife.jp/article6/
・オンライン診療の利用方法とメリット| オンライン診療(遠隔診療)サービス「スマホ診」
https://www.sumahoshin.or.jp/lab/online-medicalcare/merit/
・オンライン診療サービスcuron(クロン)によるオンライン診療/相談の対応をご検討の医療機関向けに導入サポートのご案内│curon
https://curon.co/covid19clinic/
・オンライン診療導入ガイド│Integrity Healthcare
https://www.integrity-healthcare.co.jp/telemedicine-guide#patient
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子







