テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
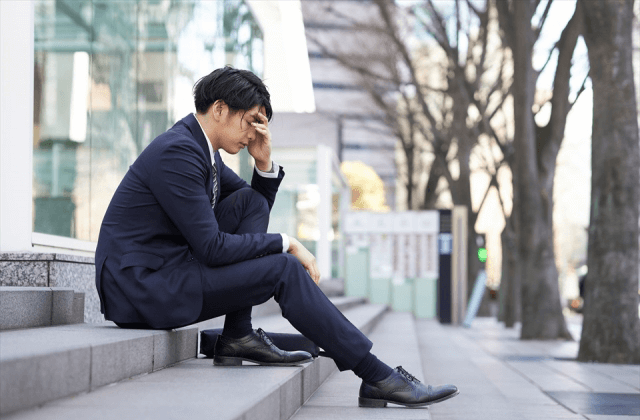
心配性な人の特徴と克服方法は?
“心配性な人”とは、こまごましたことまで気にかけて心配する性質の人を指します。したがって、あくまで「性(性質)」であれば、性格や気質の一つであるため大きな問題とはなりません。
しかし、心配が行き過ぎて病気の性質を帯びる「症(症状)」や、精神や身体器官のさわりやさまたげとなる「障(障害)」の状態となって、「不安症(不安障害)」のような疾患となってしまうと、自他公私ともに様々な問題が生じてしまい、さらには適切な治療が必要となります。
そこでまずは、“心配性な人”として見過ごされやすい「不安症(不安障害)」のうち、代表的な症例である「強迫症(強迫性障害)」と「社交不安症(社交不安障害)」を取り上げて、特徴をみてみたいと思います。
頭ではおかしいとわかっていながら、不快な思考(強迫観念)がどうしても頭から離れず、それを打ち消すために表面的には意味があるように見える行為(強迫行為)を何度も繰り返してしまいます。
しかも、当人は強迫症状が奇異であったり、不合理であるという自覚を持っていたりするため、思い悩むケースが多いことも特徴です。
また、強迫行為に大変長い時間を費やしたり、強迫症状を刺激するようなものを回避したりするために生活が強迫症状によって支配されるようになりさらなるストレスにつながるうえに、一般的にストレスにより悪化する傾向があるといわれています。
【強迫症(強迫性障害)の具体例】
強迫行為の具体例には、施錠や火の元を何度も確認しないと安心できない“確認強迫”、トイレ後や外出後に何度も手を洗ってしまう“洗浄強迫”などがあります。また、行動をする際に必ず決まった順番でやらないと気がすまない“儀式”をやめられない、他者にも“儀式”を強要してトラブルとなる場合などもあります。
【強迫症(強迫性障害)の治療法】
心理教育(まずは症状に対する患者や家族の理解を高め、治療意志を強化する)、薬物療法(主にSSRIという抗うつ薬の一種である選択的セロトニン再取り込み阻害薬を用いる)、さらには森田療法や認知行動療法などの精神療法などが一般的とされています。
このうち、認知行動療法の一種である「曝露反応妨害法(ERP)」(「曝露法」で強い不安が生じてもすぐにそれを鎮静化しようとせずに不安に自分自身を曝す一方、「反応妨害法」で一時的に不安を鎮静化するために行ってきた強迫行為をがまんして行わないようにする)が、有効な治療法として知られています。
「自分が人からどう思われるか」といった他者からの評価が心配でたまらなく、緊張のあまり心身に影響をおよぼしています。
さらに、他者からの評価を心配するあまり対策が増えすぎ日常生活がままならない状態に陥ったり、悪い結果ばかりを考えて行動を制限したり、不安に対して極端に「避ける」か「苦しみながら耐える」かのどちらかをとったりする傾向があります。
なお、人との関わり全般への不安が強いタイプと、人前で話をするなど、特定の状況についての不安が強いタイプ(パフォーマンス限局型)があります。また、社会恐怖、社交恐怖などと呼ばれる場合もあります。
【社交不安症(社交不安障害)の具体例】
人と接することが怖い“対人恐怖”、人前で話すことが非常につらい“スピーチ恐怖”、オフィスで電話に出られない“電話恐怖”、他者の視線が気になる“視線恐怖”、会食や人と一緒に食べることが苦痛な“会食恐怖”、人前で字を書こうとする手が震える“書痙”、また“赤面恐怖”“発汗恐怖”“腹鳴恐怖”“自己臭恐怖”などがあります。
【社交不安症(社交不安障害)の治療法】
一般的に、薬物療法(主にSSRIという抗うつ薬の一種である選択的セロトニン再取り込み阻害薬を用いる)と心理療法(カウンセリングや認知行動療法など)を併用して行います。
特に、個別やグループで行う認知行動療法や、認知行動療法の一つであるマインドフルネス(今この瞬間の自身の精神状態に深く意識を向けること。またそのために行われる瞑想)などが推奨されています。
そこでここでは、「“ネガティヴな”未来指向性」である心配性をもう一歩すすめて、心配事に対応するための「“ポジティブな”未来指向性」の視点から、心配性の特徴を見直してみたいと思います。
【“ポジティブな”未来指向性から見直した心配性の特徴】
※『心配性』から「心配性に対するポジティブ信念」より
1:心配性は、自分の問題解決を助けてくれている。
「あらゆる結果の可能性を考慮に入れなかったら、どうやって、起こるかもしれない問題に対して準備することができるだろう?」
2:心配性は、ものごとへの自分のモチベーションを上げてくれている。
「これらのものごとについて心配しなかったら、きっと手つかずのままだ」
3:心配性は、自分をネガティヴな感情から守ってくれる。
「それが“靴を片方脱いだら、もう片方脱ぐだけの”ようなあたりまえのことであっても、そのときになって驚くより、今心配しておきたいんです」
4:心配性は、ネガティヴな結果を防いでくれている。
「もし、病気にならないかと心配するのをやめてしまったら、なにか悪いことが起きるかもしれない」
5:心配性は、自分に良識があり、責任のある証拠である。
「自分の子どもたちを心配していなかったら、いったい、私はどんなやつになってしまうんだ?」
そのうえで、心配性だと自覚する人に大切なことは、「心配自体が問題とならないようにすること」です。つまり、たとえ心配事があったとしても、「性(性質)」で対処できるうちに対処し、「症(症状)」や「障(障害)」とならないようにすることが求められます。
そして、心配性の克服法、つまりは心配性に対する根本原則は、心配性と戦わない、心配や不安なことの根源を「なぜ」と問わないことです。
なぜなら、心配性が「性(性質)」である以上、心配性と戦ったところで自分の心との不毛な戦いに陥って勝てることはありません。また、心配や不安の根源を自分の感情だけで思考することは、心配に対する脳の働きを敏感にしてしまい、かえって負の印象づけになりかねないからです。
誰しも未来はわからない以上、心配性は正しく特徴を捉えて適切につきあうことができれば、優れた能力となりえます。
ただし、心配性な人にとって自身の心配性が重大な問題であり続けている場合、残念ながらそれは「性(性質)」の範疇をはみ出てしまっています。「強迫症(強迫性障害)」や「社交不安症(社交不安障害)」などの特徴と自身の状況をチェックしてみたり、出来るだけ早く周りの人や医療機関・公的機関に援助を求めたりしてください。
しかし、心配が行き過ぎて病気の性質を帯びる「症(症状)」や、精神や身体器官のさわりやさまたげとなる「障(障害)」の状態となって、「不安症(不安障害)」のような疾患となってしまうと、自他公私ともに様々な問題が生じてしまい、さらには適切な治療が必要となります。
そこでまずは、“心配性な人”として見過ごされやすい「不安症(不安障害)」のうち、代表的な症例である「強迫症(強迫性障害)」と「社交不安症(社交不安障害)」を取り上げて、特徴をみてみたいと思います。
鍵をかけたかいつも心配な人は・・・強迫症?
【強迫症(強迫性障害)の特徴】頭ではおかしいとわかっていながら、不快な思考(強迫観念)がどうしても頭から離れず、それを打ち消すために表面的には意味があるように見える行為(強迫行為)を何度も繰り返してしまいます。
しかも、当人は強迫症状が奇異であったり、不合理であるという自覚を持っていたりするため、思い悩むケースが多いことも特徴です。
また、強迫行為に大変長い時間を費やしたり、強迫症状を刺激するようなものを回避したりするために生活が強迫症状によって支配されるようになりさらなるストレスにつながるうえに、一般的にストレスにより悪化する傾向があるといわれています。
【強迫症(強迫性障害)の具体例】
強迫行為の具体例には、施錠や火の元を何度も確認しないと安心できない“確認強迫”、トイレ後や外出後に何度も手を洗ってしまう“洗浄強迫”などがあります。また、行動をする際に必ず決まった順番でやらないと気がすまない“儀式”をやめられない、他者にも“儀式”を強要してトラブルとなる場合などもあります。
【強迫症(強迫性障害)の治療法】
心理教育(まずは症状に対する患者や家族の理解を高め、治療意志を強化する)、薬物療法(主にSSRIという抗うつ薬の一種である選択的セロトニン再取り込み阻害薬を用いる)、さらには森田療法や認知行動療法などの精神療法などが一般的とされています。
このうち、認知行動療法の一種である「曝露反応妨害法(ERP)」(「曝露法」で強い不安が生じてもすぐにそれを鎮静化しようとせずに不安に自分自身を曝す一方、「反応妨害法」で一時的に不安を鎮静化するために行ってきた強迫行為をがまんして行わないようにする)が、有効な治療法として知られています。
人の視線がいつも心配な人は・・・社交不安症?
【社交不安症(社交不安障害)の特徴】「自分が人からどう思われるか」といった他者からの評価が心配でたまらなく、緊張のあまり心身に影響をおよぼしています。
さらに、他者からの評価を心配するあまり対策が増えすぎ日常生活がままならない状態に陥ったり、悪い結果ばかりを考えて行動を制限したり、不安に対して極端に「避ける」か「苦しみながら耐える」かのどちらかをとったりする傾向があります。
なお、人との関わり全般への不安が強いタイプと、人前で話をするなど、特定の状況についての不安が強いタイプ(パフォーマンス限局型)があります。また、社会恐怖、社交恐怖などと呼ばれる場合もあります。
【社交不安症(社交不安障害)の具体例】
人と接することが怖い“対人恐怖”、人前で話すことが非常につらい“スピーチ恐怖”、オフィスで電話に出られない“電話恐怖”、他者の視線が気になる“視線恐怖”、会食や人と一緒に食べることが苦痛な“会食恐怖”、人前で字を書こうとする手が震える“書痙”、また“赤面恐怖”“発汗恐怖”“腹鳴恐怖”“自己臭恐怖”などがあります。
【社交不安症(社交不安障害)の治療法】
一般的に、薬物療法(主にSSRIという抗うつ薬の一種である選択的セロトニン再取り込み阻害薬を用いる)と心理療法(カウンセリングや認知行動療法など)を併用して行います。
特に、個別やグループで行う認知行動療法や、認知行動療法の一つであるマインドフルネス(今この瞬間の自身の精神状態に深く意識を向けること。またそのために行われる瞑想)などが推奨されています。
心配性を“ポジティブな”未来指向性から見直す
ところで、心配性とはいったい何なのでしょうか。とても難しい問題ですが、少なくともいえることは、心配性を構成する要素は、あくまでも「未来指向性」であるとくことです。ただし「“ネガティヴな”未来指向性」であることが特徴です。そこでここでは、「“ネガティヴな”未来指向性」である心配性をもう一歩すすめて、心配事に対応するための「“ポジティブな”未来指向性」の視点から、心配性の特徴を見直してみたいと思います。
【“ポジティブな”未来指向性から見直した心配性の特徴】
※『心配性』から「心配性に対するポジティブ信念」より
1:心配性は、自分の問題解決を助けてくれている。
「あらゆる結果の可能性を考慮に入れなかったら、どうやって、起こるかもしれない問題に対して準備することができるだろう?」
2:心配性は、ものごとへの自分のモチベーションを上げてくれている。
「これらのものごとについて心配しなかったら、きっと手つかずのままだ」
3:心配性は、自分をネガティヴな感情から守ってくれる。
「それが“靴を片方脱いだら、もう片方脱ぐだけの”ようなあたりまえのことであっても、そのときになって驚くより、今心配しておきたいんです」
4:心配性は、ネガティヴな結果を防いでくれている。
「もし、病気にならないかと心配するのをやめてしまったら、なにか悪いことが起きるかもしれない」
5:心配性は、自分に良識があり、責任のある証拠である。
「自分の子どもたちを心配していなかったら、いったい、私はどんなやつになってしまうんだ?」
心配性の克服法または心配性に対する根本原則
いかがでしょうか。心配性の利点や心配することは人間にとって大切な心の働きであるという一面が、見えてきたのではないでしょうか。そのうえで、心配性だと自覚する人に大切なことは、「心配自体が問題とならないようにすること」です。つまり、たとえ心配事があったとしても、「性(性質)」で対処できるうちに対処し、「症(症状)」や「障(障害)」とならないようにすることが求められます。
そして、心配性の克服法、つまりは心配性に対する根本原則は、心配性と戦わない、心配や不安なことの根源を「なぜ」と問わないことです。
なぜなら、心配性が「性(性質)」である以上、心配性と戦ったところで自分の心との不毛な戦いに陥って勝てることはありません。また、心配や不安の根源を自分の感情だけで思考することは、心配に対する脳の働きを敏感にしてしまい、かえって負の印象づけになりかねないからです。
誰しも未来はわからない以上、心配性は正しく特徴を捉えて適切につきあうことができれば、優れた能力となりえます。
ただし、心配性な人にとって自身の心配性が重大な問題であり続けている場合、残念ながらそれは「性(性質)」の範疇をはみ出てしまっています。「強迫症(強迫性障害)」や「社交不安症(社交不安障害)」などの特徴と自身の状況をチェックしてみたり、出来るだけ早く周りの人や医療機関・公的機関に援助を求めたりしてください。
<参考文献・参考サイト>
・「心配性」『日本国語大辞典』(小学館)
・「症」『日本国語大辞典』(小学館)
・「障害・障碍・障礙」『日本国語大辞典』(小学館)
・【不安障害】心配性とはちょっと違う。苦痛な不安を感じていたら要チェック!
https://hidamarikokoro.jp/kanayama/blog/%E3%80%90%E4%B8%8D%E5%AE%89%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%80%91%E5%BF%83%E9%85%8D%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%A3%E3%81%A8%E9%81%95%E3%81%86%E3%80%82%E8%8B%A6%E7%97%9B%E3%81%AA%E4%B8%8D/
・「強迫症」[メンタルヘルス]『イミダス 2018』(集英社)
・「強迫性障害」[メンタルヘルス]『イミダス 2018』(島悟・佐藤恵美著、集英社)
・強迫性障害
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/detail_compel.html
・強迫症(強迫性障害)
https://doctorsfile.jp/medication/80/
・強迫性障害 - 東京認知行動療法センター
https://tokyo-cbt-center.com/programs/ocd
・「社交不安症(社会不安症/SAD)」[メンタルヘルス]『現代用語の基礎知識 2019』(自由国民社)
・「社交不安障害(SAD)」[メンタルヘルス]『イミダス 2018』(島悟・佐藤恵美著、集英社)
・『社交不安症がよくわかる本』(貝谷久宣監修、講談社)
・不安障害
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/know/know_02.html
・社交不安症(社交不安障害)とは?
https://fuanclinic.com/med_content/sad/
・「人はなぜ心配するのか」『こころと脳のサイエンス 04号』(V.スターン著、日経サイエンス編集部編、日経サイエンス)
・『心配性』(ケビン・L.ギョールコー&パメラ・S.ウィーガルツ著、中森拓也訳、大野裕監修、創元社)
・『「心配でたまらない」が消える心理学』(根本橘夫著、朝日文庫)
・『少し「心配性」のほうが、うまくいく!』(大野裕著、大和書房)
・「心配性」『日本国語大辞典』(小学館)
・「症」『日本国語大辞典』(小学館)
・「障害・障碍・障礙」『日本国語大辞典』(小学館)
・【不安障害】心配性とはちょっと違う。苦痛な不安を感じていたら要チェック!
https://hidamarikokoro.jp/kanayama/blog/%E3%80%90%E4%B8%8D%E5%AE%89%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%80%91%E5%BF%83%E9%85%8D%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%A3%E3%81%A8%E9%81%95%E3%81%86%E3%80%82%E8%8B%A6%E7%97%9B%E3%81%AA%E4%B8%8D/
・「強迫症」[メンタルヘルス]『イミダス 2018』(集英社)
・「強迫性障害」[メンタルヘルス]『イミダス 2018』(島悟・佐藤恵美著、集英社)
・強迫性障害
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/detail_compel.html
・強迫症(強迫性障害)
https://doctorsfile.jp/medication/80/
・強迫性障害 - 東京認知行動療法センター
https://tokyo-cbt-center.com/programs/ocd
・「社交不安症(社会不安症/SAD)」[メンタルヘルス]『現代用語の基礎知識 2019』(自由国民社)
・「社交不安障害(SAD)」[メンタルヘルス]『イミダス 2018』(島悟・佐藤恵美著、集英社)
・『社交不安症がよくわかる本』(貝谷久宣監修、講談社)
・不安障害
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/know/know_02.html
・社交不安症(社交不安障害)とは?
https://fuanclinic.com/med_content/sad/
・「人はなぜ心配するのか」『こころと脳のサイエンス 04号』(V.スターン著、日経サイエンス編集部編、日経サイエンス)
・『心配性』(ケビン・L.ギョールコー&パメラ・S.ウィーガルツ著、中森拓也訳、大野裕監修、創元社)
・『「心配でたまらない」が消える心理学』(根本橘夫著、朝日文庫)
・『少し「心配性」のほうが、うまくいく!』(大野裕著、大和書房)
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部










