テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
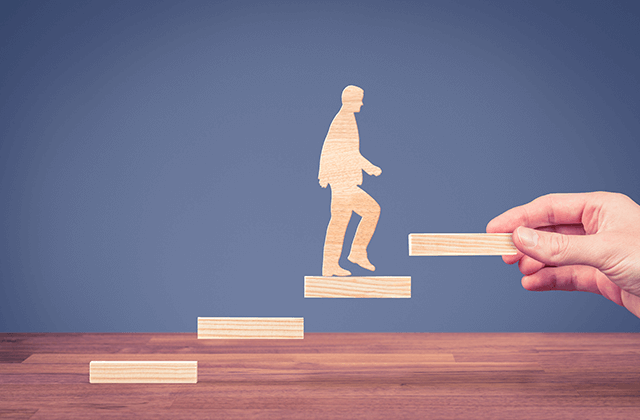
40歳でキャリアを一度考え直す必要がある理由
日本人の働き方が今、大きく変わろうとしています。東京大学大学院経済学研究科の柳川範之教授によると、その要因は二つ。一つはAI技術の進化をはじめとするデジタル化などの技術革新により、経済全体の変化するスピードが劇的に早まったこと。そしてもう一つは、「人生100年時代」ということで働く年数が長期化してきたことだといいます。
その上、世界中が襲われた新型コロナウイルスにより、社会の変革スピードにも拍車がかかっています。「ニューノーマル」と呼ばれる新しい社会・経済構造の構築も急ピッチ。そのような変化についていくには、それぞれの人が自分のキャリア、必要な能力について絶えず振り返りつつ変革していく必要があります。
かつてない潮流のなか、日本の労働慣行も変わりました。55歳が定年だった頃は、仮に20歳から働き始めると35年間だった職業生活が、定年が65歳まで延びるとすると45年間になるのです。
さらに定年が延びても、昔とった杵柄を生かせる職場でそのまま働き続け、ハッピーリタイアメントを迎える人はごく少数。たとえ長期雇用の会社であっても、定年後は別の会社で働く必要のある人がほとんどになります。
また、企業はかつての好調な時代のような「内部労働市場」をうまく回せなくなってきました。これは終身雇用を前提としたもので、「適材適所」を社内に配置するため、各企業は人事部を中心に社内教育を充実させてきたからです。
社内で人材を回すというシステムが限界にぶつかり、各企業は社内人事に時間とお金をかける余裕がなくなっています。その結果、個々人は自らキャリアを転換する必要に迫られることになっているわけです。
これまでの「年齢を重ねるにつれて、上へ上がり続けていく」というイメージは今後社会全体で修正されるだろうと、柳川教授は予測します。もし20年たって頂点に立ったなら、その先は別の方向で生き残りを考えなくてはならないという心構えを築く必要があるわけです。
そうなると、新卒の頃と40歳では、本人のプライドが違いますが、20年を一つのサイクルとして、セカンドキャリアをゼロスタートできるメンタルも要求されるでしょう。時にはセカンドライフを送るアスリートや定年後に別分野で活躍する方を参考にしたり、自分がやりたいことだけでなく、自分がいまできることと社会のニーズを見直したり、次へのステップのための勉強を始めたりと、できることはいろいろあります。
最初に決めたレールを全うするスタイルではなく、「定期的な選び直し」「定期的な学び直し」をするのが、「人生100年時代」のキャリアプランを成功させる秘訣ではないでしょうか。
その上、世界中が襲われた新型コロナウイルスにより、社会の変革スピードにも拍車がかかっています。「ニューノーマル」と呼ばれる新しい社会・経済構造の構築も急ピッチ。そのような変化についていくには、それぞれの人が自分のキャリア、必要な能力について絶えず振り返りつつ変革していく必要があります。
企業も社会も変わるなか、40歳の意識も変える
このような背景を考えると、柳川教授が早くから提唱してきた「40歳定年制」、すなわち「40歳でキャリアをもう1回考えなおす必要性」が現実味を帯びてきます。かつてない潮流のなか、日本の労働慣行も変わりました。55歳が定年だった頃は、仮に20歳から働き始めると35年間だった職業生活が、定年が65歳まで延びるとすると45年間になるのです。
さらに定年が延びても、昔とった杵柄を生かせる職場でそのまま働き続け、ハッピーリタイアメントを迎える人はごく少数。たとえ長期雇用の会社であっても、定年後は別の会社で働く必要のある人がほとんどになります。
また、企業はかつての好調な時代のような「内部労働市場」をうまく回せなくなってきました。これは終身雇用を前提としたもので、「適材適所」を社内に配置するため、各企業は人事部を中心に社内教育を充実させてきたからです。
社内で人材を回すというシステムが限界にぶつかり、各企業は社内人事に時間とお金をかける余裕がなくなっています。その結果、個々人は自らキャリアを転換する必要に迫られることになっているわけです。
「選び直し」と「学び直し」でセカンドキャリアを成功に
今はだれもがセカンドキャリアを考えなくてはならないという状況ですが、60歳や65歳になってから「新しい働き方」を考えるのでは間に合わないかもしれません。人生の節目節目で自分のキャリアを見直し、新しい能力を身につけることが求められます。その節目として、働きはじめておよそ20年目の40歳前後は大きな転機といえるのです。これまでの「年齢を重ねるにつれて、上へ上がり続けていく」というイメージは今後社会全体で修正されるだろうと、柳川教授は予測します。もし20年たって頂点に立ったなら、その先は別の方向で生き残りを考えなくてはならないという心構えを築く必要があるわけです。
そうなると、新卒の頃と40歳では、本人のプライドが違いますが、20年を一つのサイクルとして、セカンドキャリアをゼロスタートできるメンタルも要求されるでしょう。時にはセカンドライフを送るアスリートや定年後に別分野で活躍する方を参考にしたり、自分がやりたいことだけでなく、自分がいまできることと社会のニーズを見直したり、次へのステップのための勉強を始めたりと、できることはいろいろあります。
最初に決めたレールを全うするスタイルではなく、「定期的な選び直し」「定期的な学び直し」をするのが、「人生100年時代」のキャリアプランを成功させる秘訣ではないでしょうか。
人気の講義ランキングTOP20
2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る
テンミニッツ・アカデミー編集部










