テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
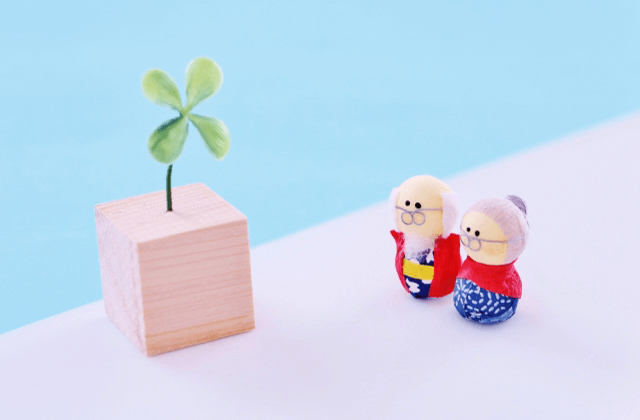
「老後が快適な国」ランキング、日本は何位?
フランスの投資銀行「Natixis(ナティクシス)」は、主要先進国44カ国を対象とした、退職後の生活に影響を与えるさまざまな要因を相対的に評価のうえランキング化した、「Global Retirement Index(世界引退指数)」を、毎年発表しています。
そのため、「世界引退指数」のランキングは、「老後が快適な国」ランキングとしても見ることができます。
2022年版となる「2022 Global Retirement Index(2022年版 世界引退指数)」のうち、TOP25となる【2022年版「老後が快適な国」ランキング・TOP25】は、以下のようになっています。
【2022年版「老後が快適な国」ランキング・TOP25】
《国名(世界引退指数):健康/退職後の資金/生活の質/物質的な豊かさ》
1位ノルウェー(81%):☆91%/▲69%/87%/79%
2位スイス(80%):☆90%/74%/86%/▲69%
3位アイスランド(79%):☆88%/▲68%/86%/77%
4位アイルランド(76%):☆89%/70%/80%/▲67%
5位オーストラリア(75%):☆88%/72%/77%/▲66%
6位ニュージーランド(75%):☆85%/71%/81%/▲64%
7位ルクセンブルク(75%):☆91%/▲59%/81%/72%
8位オランダ(75%):☆89%/▲56%/80%/78%
9位デンマーク(74%):86%/▲54%/☆88%/76%
10位チェコ(73%):76%/▲64%/68%/☆84%
11位ドイツ(72%):☆87%/▲55%/80%/71%
12位フィンランド(71%):84%/▲55%/☆89%/63%/
13位スウェーデン(71%):☆90%/▲56%/87%/59%
14位オーストリア(71%):☆86%/▲54%/82%/69%
15位カナダ(71%):☆87%/67%/74%/▲58%
16位イスラエル(70%):☆82%/66%/74%/▲60%
17位韓国(70%):☆80%/73%/▲59%/68%
18位アメリカ(69%):☆85%/67%/72%/▲56%
19位イギリス(69%):☆83%/▲55%/82%/61%
20位ベルギー(69%):☆85%/▲51%/74%/70%
21位スロベニア(69%):☆82%/▲51%/69%/77%
22位日本(69%)::☆91%/▲51%/67%/72%
23位マルタ(68%):☆78%/63%/▲61%/72%
24位フランス(66%):☆90%/▲48%/78%/▲57%
25位エストニア(66%):☆68%/☆68%/☆68%/▲60%
※☆大インデックスのうち最も高いスコア:▲大インデックスのうち最も低いスコア
4つの大インデックスのうち最も高いスコアである「健康」は、1位のノルウェーおよび7位のルクセンブルクと同じく91%と高く、TOP3に入っています。しかし、4つの大インデックスのうち最も低いスコアである「退職後の資金」51%が他の指数と比べても低く、ネックとなっています。
また、サブインデックスのうち、「Old-Age Dependency(高齢者依存人口)」3%、さらに「Government Indebtedness(政府債務)」1%と極めて低く、日本の順位を下げる大きな要因となっています。
なお、日本は前年の2021年版でも22位と同順位ですが、10年前の2012年版の25位よりランクアップしています。ただし、順位ではなく世界引退指数のスコアそのものを見てみると、日本の2022年版は69%、2021年版は68%で、2012年版の71%よりわずかではあるももの低下しています。
「老後が快適な国」ランキングからは、近未来の日本をより良くしていくために、少子化対策による人口分布の改善や国全体および国民一人ひとりの財務の健全化と安定化など、多くの課題があることが見えてきます。
2022年版「老後が快適な国」ランキング・TOP25
「世界引退指数」の評価基準となる「Index(インデックス・指数)」は、(1)医療・平均寿命などの「Health(健康)」、(2)国家財政・経済の状況などの「Finances in Retirement(退職後の資金)」、(3)環境の良さ・幸福度などの「Quality of Life(生活の質)」、(4)平均給与・所得の均等性・失業率などの「Material Wellbeing(物質的な豊かさ)」の4つの大インデックスと、その他のサブインデックスの計18のスコアを調査し、算出・分析したうえで、総合的なランク付けがなされています。そのため、「世界引退指数」のランキングは、「老後が快適な国」ランキングとしても見ることができます。
2022年版となる「2022 Global Retirement Index(2022年版 世界引退指数)」のうち、TOP25となる【2022年版「老後が快適な国」ランキング・TOP25】は、以下のようになっています。
【2022年版「老後が快適な国」ランキング・TOP25】
《国名(世界引退指数):健康/退職後の資金/生活の質/物質的な豊かさ》
1位ノルウェー(81%):☆91%/▲69%/87%/79%
2位スイス(80%):☆90%/74%/86%/▲69%
3位アイスランド(79%):☆88%/▲68%/86%/77%
4位アイルランド(76%):☆89%/70%/80%/▲67%
5位オーストラリア(75%):☆88%/72%/77%/▲66%
6位ニュージーランド(75%):☆85%/71%/81%/▲64%
7位ルクセンブルク(75%):☆91%/▲59%/81%/72%
8位オランダ(75%):☆89%/▲56%/80%/78%
9位デンマーク(74%):86%/▲54%/☆88%/76%
10位チェコ(73%):76%/▲64%/68%/☆84%
11位ドイツ(72%):☆87%/▲55%/80%/71%
12位フィンランド(71%):84%/▲55%/☆89%/63%/
13位スウェーデン(71%):☆90%/▲56%/87%/59%
14位オーストリア(71%):☆86%/▲54%/82%/69%
15位カナダ(71%):☆87%/67%/74%/▲58%
16位イスラエル(70%):☆82%/66%/74%/▲60%
17位韓国(70%):☆80%/73%/▲59%/68%
18位アメリカ(69%):☆85%/67%/72%/▲56%
19位イギリス(69%):☆83%/▲55%/82%/61%
20位ベルギー(69%):☆85%/▲51%/74%/70%
21位スロベニア(69%):☆82%/▲51%/69%/77%
22位日本(69%)::☆91%/▲51%/67%/72%
23位マルタ(68%):☆78%/63%/▲61%/72%
24位フランス(66%):☆90%/▲48%/78%/▲57%
25位エストニア(66%):☆68%/☆68%/☆68%/▲60%
※☆大インデックスのうち最も高いスコア:▲大インデックスのうち最も低いスコア
「老後が快適な国」日本は真ん中の22位
2022年版「老後が快適な国」ランキングでは、日本は44カ国中22位という、ほぼ真ん中の順位という結果でした。4つの大インデックスのうち最も高いスコアである「健康」は、1位のノルウェーおよび7位のルクセンブルクと同じく91%と高く、TOP3に入っています。しかし、4つの大インデックスのうち最も低いスコアである「退職後の資金」51%が他の指数と比べても低く、ネックとなっています。
また、サブインデックスのうち、「Old-Age Dependency(高齢者依存人口)」3%、さらに「Government Indebtedness(政府債務)」1%と極めて低く、日本の順位を下げる大きな要因となっています。
なお、日本は前年の2021年版でも22位と同順位ですが、10年前の2012年版の25位よりランクアップしています。ただし、順位ではなく世界引退指数のスコアそのものを見てみると、日本の2022年版は69%、2021年版は68%で、2012年版の71%よりわずかではあるももの低下しています。
「老後が快適な国」ランキングからは、近未来の日本をより良くしていくために、少子化対策による人口分布の改善や国全体および国民一人ひとりの財務の健全化と安定化など、多くの課題があることが見えてきます。
<参考サイト>
・2022 Global Retirement Index│Natixis
https://www.im.natixis.com/intl/resources/2022-global-retirement-index-report-full
・2022 Global Retirement Index | Natixis Investment Managers
https://www.im.natixis.com/intl/research/2022-global-retirement-index
・「老後が快適な国」ランキングTOP25! 1位は「アイスランド」 日本は22位【2021年最新】
https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/384397/
・「老後が快適な国」ランキングTOP25! 1位は「アイスランド」 日本は23位【2020年調査】
https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/314933/
・老後が快適な国 韓国17位 日本は22位 - Korea.net
https://japanese.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=221266
・首位はスイス、日本は22位~「定年生活快適度世界ランキング」に見る、世界の定年後生活保障問題
https://ampmedia.jp/2018/10/15/global-retirement-index/
・2022 Global Retirement Index│Natixis
https://www.im.natixis.com/intl/resources/2022-global-retirement-index-report-full
・2022 Global Retirement Index | Natixis Investment Managers
https://www.im.natixis.com/intl/research/2022-global-retirement-index
・「老後が快適な国」ランキングTOP25! 1位は「アイスランド」 日本は22位【2021年最新】
https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/384397/
・「老後が快適な国」ランキングTOP25! 1位は「アイスランド」 日本は23位【2020年調査】
https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/314933/
・老後が快適な国 韓国17位 日本は22位 - Korea.net
https://japanese.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=221266
・首位はスイス、日本は22位~「定年生活快適度世界ランキング」に見る、世界の定年後生活保障問題
https://ampmedia.jp/2018/10/15/global-retirement-index/
人気の講義ランキングTOP20










