テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
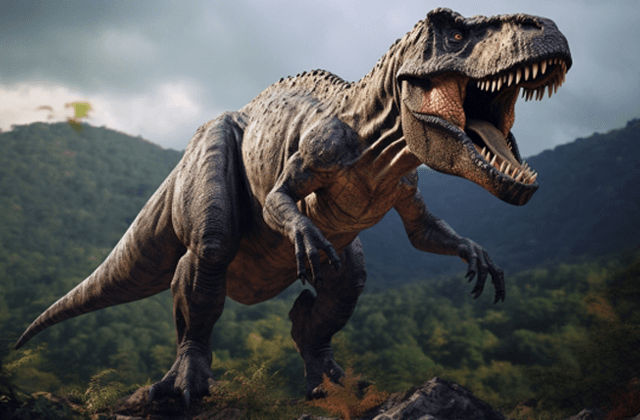
『デジタル時代の恐竜学』から知る古生物研究の最前線
恐竜と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、ティラノサウルスではないでしょうか。映画「ジュラシックパーク」にも出てきましたが、その全長は12メートルを超すものもいたほどの最強の肉食恐竜です。強力な顎でほかの生き物を骨ごと噛み砕いて食べていました。さら体に対して小さな腕でも200キロを持ち上げる腕力はあったそうです。ただし6600万年前に起こった隕石の衝突により、他の恐竜と共にティラノサウルスも絶滅します。
なぜ6600万年以上も前の生態が分かるのかといえば、地層に埋もれた岩石の中から研究者が骨を見つけ解析するからです。最近はこのための技術や研究方法が大きく発展しました。その一端が、CTスキャン、MRI、フォトグラメトリ、3Dプリンター、理論モデル、コンピュータシミュレーションなどです。こういった最新の手法を古生物研究に応用する現場を伝える本が『デジタル時代の恐竜学』(河部壮一郎著、インターナショナル新書)です。
著者の河部壮一郎氏は1985年愛媛県生まれ、福井県立大学恐竜学研究所准教授です。専門は脊椎動物の比較形態学で、東京大学大学院理学系研究科博士課程に在籍中から、鳥類や鳥類化石の脳形態に関する研究に没頭します。現在では研究対象はもっと広く、鳥類を含む恐竜や哺乳類など様々な生物や古生物に及びます。はじめは恐竜の研究がしたいと思いながらその子孫である鳥類の研究に向かったそうですが、現在では恐竜だとか恐竜じゃないだとか関係なく「面白い研究がしたい」という一心とのことです。
この作業を通して河部氏らは、「フクイベナートル」という福井県で発見された恐竜の分岐図上での位置を明らかにします。この恐竜の全身骨格をCTスキャンする取り組みを行ったのは、河部氏の同僚である服部創紀氏です。2020年のコロナ禍で展示施設が休館した際、100時間以上をかけて地道にCTスキャンに取り組んだそうです。この結果をもとにコンピュータで細かいデータ処理を行い、三次元CGを作ります。
このときまでに処理したCT画像はおよそ8万枚を越えました。こうして新しい細かな特徴が300以上確認され、「フクイベナートル」の歯は鋭くなく、原始的な肉食性から少しずつ草食性へ変化する途中だったとわかってきました。さらに脳はそれほど大きくなく、嗅覚を司る領域が桁違いに大きかったようです。このことから「フクイベナートル」は鋭い嗅覚と聴覚を頼りに俊敏に昆虫のような獲物を追っていた、といった様子が見えるようになりました。
ただし、角質のクチバシは爪などと同様で化石となることは稀です。このクチバシがどういうものであったのかを知るために、まずはCTスキャンをもとに作られた頭骨の3Dモデルに仮想的なクチバシを覆ったモデルを用意します。このとき「最小限角質があったモデル」「歯のある領域まで広く角質のあったモデル」「角質の代わりに歯があったモデル」の3つを用いて比較しました。これをFEAと呼ばれる、主に工学で用いられる手法(物体の強度や剛性などの物理的な性質を計算するもの)で検証します。
これによると、ある程度の柔らかさを持った組織があることで、摂食時の応力や歪みを緩和して頭骨の安定性を高める働きをすることがわかりました。加えて、シミュレーションでは最小限の角質のクチバシだけで十分効果を発揮しました。つまり、「エルリコサウルス」は小さなクチバシを備えた恐竜だったようです。このように現代のコンピュータ技術によるシミュレーションを経て、現存しない恐竜の部分に関しても様子がわかるようになってきました。
さらに部分ごとに散らばっている標本を合わせて、恐竜の全体像を作ることもできます。またいつか本体が失われたとしてもデジタルで残しておけば、未来に情報を引き継ぐことが可能です。河部氏は「このようなデジタル技術は、恐竜などの古生物の姿や生活をよりリアルに、より多角的に捉えることに役立ち、ぼくたちの恐竜への理解をより深めるための強力なツールとなっている」といいます。
恐竜の世界は、最新技術によって次々と新しい発見が相次いでいます。ただしこの背景にあるのは、広範な領域にまたがる最新技術を駆使し、なんとしてでも新しい発見に辿り着こうとする研究者の情熱と根気であるということにも、本書は気づかせてくれます。このような情熱、根気、最新技術の融合によって、6600万年前より前の世界は少しずつ現代に蘇っています。ぜひ手に取ってこの臨場感に触れてみてください。
なぜ6600万年以上も前の生態が分かるのかといえば、地層に埋もれた岩石の中から研究者が骨を見つけ解析するからです。最近はこのための技術や研究方法が大きく発展しました。その一端が、CTスキャン、MRI、フォトグラメトリ、3Dプリンター、理論モデル、コンピュータシミュレーションなどです。こういった最新の手法を古生物研究に応用する現場を伝える本が『デジタル時代の恐竜学』(河部壮一郎著、インターナショナル新書)です。
著者の河部壮一郎氏は1985年愛媛県生まれ、福井県立大学恐竜学研究所准教授です。専門は脊椎動物の比較形態学で、東京大学大学院理学系研究科博士課程に在籍中から、鳥類や鳥類化石の脳形態に関する研究に没頭します。現在では研究対象はもっと広く、鳥類を含む恐竜や哺乳類など様々な生物や古生物に及びます。はじめは恐竜の研究がしたいと思いながらその子孫である鳥類の研究に向かったそうですが、現在では恐竜だとか恐竜じゃないだとか関係なく「面白い研究がしたい」という一心とのことです。
CTスキャンによる地道な解析
CTといえば病院を思い浮かべますが、岩石と化石との境界を見分けることに対しても有効です。ただし人体と異なり一律のCT値(X線の量)だけで処理を終えることはできません。一つのサンプル内でも岩石の密度の差異が激しいからです。このため数千枚のCT画像一枚一枚で人の目と手を使って、岩石の状態を把握しながらCT値を変えて撮影する必要があります。なかなか気の遠くなるような作業です。この作業を通して河部氏らは、「フクイベナートル」という福井県で発見された恐竜の分岐図上での位置を明らかにします。この恐竜の全身骨格をCTスキャンする取り組みを行ったのは、河部氏の同僚である服部創紀氏です。2020年のコロナ禍で展示施設が休館した際、100時間以上をかけて地道にCTスキャンに取り組んだそうです。この結果をもとにコンピュータで細かいデータ処理を行い、三次元CGを作ります。
このときまでに処理したCT画像はおよそ8万枚を越えました。こうして新しい細かな特徴が300以上確認され、「フクイベナートル」の歯は鋭くなく、原始的な肉食性から少しずつ草食性へ変化する途中だったとわかってきました。さらに脳はそれほど大きくなく、嗅覚を司る領域が桁違いに大きかったようです。このことから「フクイベナートル」は鋭い嗅覚と聴覚を頼りに俊敏に昆虫のような獲物を追っていた、といった様子が見えるようになりました。
コンピュータシミュレーションによる発見
さて、恐竜のなかには現在の鳥の祖先がいますので、恐竜にクチバシがあったものがいてもおかしくありません。実際に「フクイベナートル」と同じテリジノサウルス類に属する「エルリコサウルス」の口元は、口先に歯がない鳥類によく似ていることから、角質でできたクチバシがあったと想定されました。この恐竜の化石はモンゴルの約9000万年前の地層から見つかっています。ただし、角質のクチバシは爪などと同様で化石となることは稀です。このクチバシがどういうものであったのかを知るために、まずはCTスキャンをもとに作られた頭骨の3Dモデルに仮想的なクチバシを覆ったモデルを用意します。このとき「最小限角質があったモデル」「歯のある領域まで広く角質のあったモデル」「角質の代わりに歯があったモデル」の3つを用いて比較しました。これをFEAと呼ばれる、主に工学で用いられる手法(物体の強度や剛性などの物理的な性質を計算するもの)で検証します。
これによると、ある程度の柔らかさを持った組織があることで、摂食時の応力や歪みを緩和して頭骨の安定性を高める働きをすることがわかりました。加えて、シミュレーションでは最小限の角質のクチバシだけで十分効果を発揮しました。つまり、「エルリコサウルス」は小さなクチバシを備えた恐竜だったようです。このように現代のコンピュータ技術によるシミュレーションを経て、現存しない恐竜の部分に関しても様子がわかるようになってきました。
デジタルにより可能になったこと
こういったシミュレーションによる仮想モデルを作って解析することで、ティラノサウルスがどのくらいのスピードで走ることができたのか、羽毛恐竜や始祖鳥がどのように飛行していたのかもわかるようになりました。デジタルデータがあれば3Dプリンターを使ってレプリカを作れるので、展示を充実させることができます。また海外の博物館にある貴重な標本でも、レプリカによってある程度詳しく検証できます。さらに部分ごとに散らばっている標本を合わせて、恐竜の全体像を作ることもできます。またいつか本体が失われたとしてもデジタルで残しておけば、未来に情報を引き継ぐことが可能です。河部氏は「このようなデジタル技術は、恐竜などの古生物の姿や生活をよりリアルに、より多角的に捉えることに役立ち、ぼくたちの恐竜への理解をより深めるための強力なツールとなっている」といいます。
大学や博物館などの資料は、全人類共有の財産
技術が発展して全て順調ということではありません。本書最後ではコストの問題について示されています。研究用のスキャナーや人件費にはそれなりのお金がかかります。クラウドファンディングも行われますが、費用や寄付に対するリターンに対してお金と時間がかかります。河部氏は「大学や博物館などの資料は、全人類共有の財産」だと述べます。デジタル化は研究の発展に大きな成果をもたらすことは間違いないだけに、この先多くの人の協力が必要不可欠であることはいうまでもありません。恐竜の世界は、最新技術によって次々と新しい発見が相次いでいます。ただしこの背景にあるのは、広範な領域にまたがる最新技術を駆使し、なんとしてでも新しい発見に辿り着こうとする研究者の情熱と根気であるということにも、本書は気づかせてくれます。このような情熱、根気、最新技術の融合によって、6600万年前より前の世界は少しずつ現代に蘇っています。ぜひ手に取ってこの臨場感に触れてみてください。
<参考文献>
『デジタル時代の恐竜学』(河部壮一郎著、インターナショナル新書)
https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-7976-8138-3
<参考サイト>
福井県立大学恐竜学研究所HP
https://idr-fpu.jimdofree.com/
河部壮一郎氏のX(旧Twitter)
https://twitter.com/So1_Kawabe
『デジタル時代の恐竜学』(河部壮一郎著、インターナショナル新書)
https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-7976-8138-3
<参考サイト>
福井県立大学恐竜学研究所HP
https://idr-fpu.jimdofree.com/
河部壮一郎氏のX(旧Twitter)
https://twitter.com/So1_Kawabe
人気の講義ランキングTOP20
2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る
テンミニッツ・アカデミー編集部










