テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
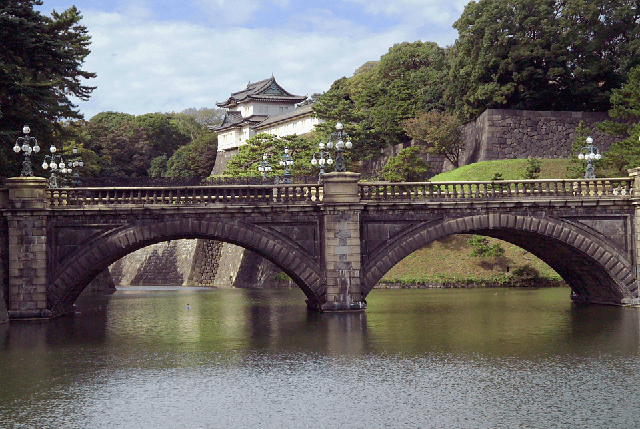
天皇陛下のビデオメッセージ~私たち国民はどう捉えるべきなのか
2016年8月8日の午後3時に、天皇陛下は象徴としてのお務めについて心の内をビデオメッセージにして、広く国民に語った。これは、平成という時代を区切り、次へとつながる大きな節目となるおことばだったと思うし、また多くの国民が共感できるおことばであった。
象徴天皇の地位に関わる発言には、大変重いものがあった。二度の外科手術を経験し、加えて高齢化によって身体の衰えを感じるようになった。そうなると、「全身全霊」で象徴天皇としてのお務めを果たすことが難しいのではないか、と語ったのだ。
天皇陛下は、常に国民の安寧を願い、喜びも悲しみも国民と共に分かち合ってきた。皇后陛下と共に「象徴天皇とは何か」「いかに行為すべきか」を実践されてきた。
そうやって「象徴天皇制」が具体的な姿を帯びることで、私たちの生活に不可欠なものとなった。市井の人々が、それぞれの場所で社会を支えていることを天皇陛下はご覧になり、そこから国民のために祈るという役割を自ら担ってきた。それは幸せなことであったという気持ちを、陛下は率直に表明されたのだ。
問題は、天皇陛下ご自身が「老い」を迎えていることだ。超高齢化社会の中で、天皇陛下もまた老いる一人の人間である。その中で、象徴天皇としての役割を果たすことがこれからもできるのかどうか。
「摂政を置けばいい」という議論もあるが、責任感と義務感の強い天皇陛下ならば、摂政を置いたところでご自分のお務めが軽減されるとは考えないだろう。天皇という地位にとどまる限り、常に重い責任が付随することを、私たちは思い知った。
また天皇陛下は「天皇の終焉」というおことばを使い、葬儀に関わる行事と新しい時代を迎える行事が並行して行われることで、国民と家族に重い負担を強いることを危惧された。そうした国民の将来についてまで考えられていた。
メッセージの結びは、国民の理解を求めるものだった。天皇陛下はあくまでも主権が国民に存する以上、象徴天皇としての自分の将来や地位は、国民の判断に委ねられていることを強調した。ここに、今回のおことばの重みと尊さがある。
日本人全体が直面している問題と結び付けると、これは「老い」と関わる問題である。そうした状況では、象徴天皇としてのお務めを「全身全霊」で果たすことが難しくなる。このことを心境として語られたことが、メッセージの主眼だ。それはある意味で、「象徴天皇とは何か」を皇后陛下と共に模索されてきた歴史の集大成ともいえるものだ。
象徴とは、国民のために心を込めて何かをする存在であり、それこそが「国民の総意に基づく天皇」という地位のあり方に関係する。その努力による御心の表明が今回行われた。
そして、そのことについて国民の理解を求めるという表現が、今回のおことばの中にはあった。自身の象徴天皇としてのあり方は、常に国民と共にある。だからこそ、高齢化によって天皇としてのお務めが全うできないことに対する危惧を、国民に理解してもらいたい。今回はそういった意思が込められていたおことばだった。
天皇陛下は、昨年の誕生日で82歳になられた。その会見の席上でも、天皇陛下は「老い」について言及され、その義務を全うできるかどうかについて、おことばを述べられた。今回のおことばの中では、「全身全霊」という表現が使われたが、これは大変重いおことばで、「全てに対し心を込めて接する」ことを意味する。
身体障害者や大災害の被災者など、弱い立場にある人々に接するとき、「老い」によって「全身全霊」でそうした人々と接することが難しくなるのではないか。
私たちのような市井の人間であれば、「引退」「隠居」して楽に暮らそうと考えるところだが、それとは別の次元で、天皇陛下はご自身の生活やお仕事を考えておられる。
「象徴としての天皇」である以上、「全身全霊」でお仕事ができないことは、相対する様々な人々に対し、失礼に当たるのではないか。そういう危惧が、このおことばには込められている。
「心を込めて」といった場合、例えばそれは戦地で兵士として亡くなった方や巻き込まれて亡くなった方の悲しみに向かい合うことも意味する。そうした悲しみを心の中に抱いたまま、天皇陛下は生活を続けている。
しかもそれらの悲しみは、一つとして同じものはない。日々、そして年々において、違うとき、違う場所で、まったく違う悲しみに向かい合うという、大変つらい仕事をされている。
一般人であれば、「老い」で現役から退くことも可能だが、天皇陛下にその選択肢はない。皇族には職業選択の自由はなく、世襲という地位と責任が義務付けられた上に、離脱する自由もない。そして天皇陛下はご自分で退位や譲位をする自由もない。
これは、あまりにもご自分に自己犠牲や献身を強いる立場であり、私たち日本人はそれに甘んじることを強制してきたことになる。そして、70年にわたり、天皇陛下がそうした大変なお立場に立つことに疑問を感じてこなかった。
しかし、天皇陛下はご高齢の中、例えば東北三県を新幹線やバスを使って長時間移動され、沿道に立つ国民に寄り添うよう、ご挨拶やご会釈をされる。そういった大変につらい日帰りの旅を連日している、いわば私たちの社会でいう「老人」は、日本では他にいないだろう。
安倍首相も、天皇陛下のおことばを重く受け止め、十分な配慮が必要であると発言したが、この問題は政府に投げるのではなく、私たち国民が世論として考えていくべき問題である。
象徴天皇の地位に関わる発言には、大変重いものがあった。二度の外科手術を経験し、加えて高齢化によって身体の衰えを感じるようになった。そうなると、「全身全霊」で象徴天皇としてのお務めを果たすことが難しいのではないか、と語ったのだ。
天皇陛下は、常に国民の安寧を願い、喜びも悲しみも国民と共に分かち合ってきた。皇后陛下と共に「象徴天皇とは何か」「いかに行為すべきか」を実践されてきた。
そうやって「象徴天皇制」が具体的な姿を帯びることで、私たちの生活に不可欠なものとなった。市井の人々が、それぞれの場所で社会を支えていることを天皇陛下はご覧になり、そこから国民のために祈るという役割を自ら担ってきた。それは幸せなことであったという気持ちを、陛下は率直に表明されたのだ。
問題は、天皇陛下ご自身が「老い」を迎えていることだ。超高齢化社会の中で、天皇陛下もまた老いる一人の人間である。その中で、象徴天皇としての役割を果たすことがこれからもできるのかどうか。
「摂政を置けばいい」という議論もあるが、責任感と義務感の強い天皇陛下ならば、摂政を置いたところでご自分のお務めが軽減されるとは考えないだろう。天皇という地位にとどまる限り、常に重い責任が付随することを、私たちは思い知った。
また天皇陛下は「天皇の終焉」というおことばを使い、葬儀に関わる行事と新しい時代を迎える行事が並行して行われることで、国民と家族に重い負担を強いることを危惧された。そうした国民の将来についてまで考えられていた。
メッセージの結びは、国民の理解を求めるものだった。天皇陛下はあくまでも主権が国民に存する以上、象徴天皇としての自分の将来や地位は、国民の判断に委ねられていることを強調した。ここに、今回のおことばの重みと尊さがある。
日本人全体が直面している問題と結び付けると、これは「老い」と関わる問題である。そうした状況では、象徴天皇としてのお務めを「全身全霊」で果たすことが難しくなる。このことを心境として語られたことが、メッセージの主眼だ。それはある意味で、「象徴天皇とは何か」を皇后陛下と共に模索されてきた歴史の集大成ともいえるものだ。
象徴とは、国民のために心を込めて何かをする存在であり、それこそが「国民の総意に基づく天皇」という地位のあり方に関係する。その努力による御心の表明が今回行われた。
そして、そのことについて国民の理解を求めるという表現が、今回のおことばの中にはあった。自身の象徴天皇としてのあり方は、常に国民と共にある。だからこそ、高齢化によって天皇としてのお務めが全うできないことに対する危惧を、国民に理解してもらいたい。今回はそういった意思が込められていたおことばだった。
天皇陛下は、昨年の誕生日で82歳になられた。その会見の席上でも、天皇陛下は「老い」について言及され、その義務を全うできるかどうかについて、おことばを述べられた。今回のおことばの中では、「全身全霊」という表現が使われたが、これは大変重いおことばで、「全てに対し心を込めて接する」ことを意味する。
身体障害者や大災害の被災者など、弱い立場にある人々に接するとき、「老い」によって「全身全霊」でそうした人々と接することが難しくなるのではないか。
私たちのような市井の人間であれば、「引退」「隠居」して楽に暮らそうと考えるところだが、それとは別の次元で、天皇陛下はご自身の生活やお仕事を考えておられる。
「象徴としての天皇」である以上、「全身全霊」でお仕事ができないことは、相対する様々な人々に対し、失礼に当たるのではないか。そういう危惧が、このおことばには込められている。
「心を込めて」といった場合、例えばそれは戦地で兵士として亡くなった方や巻き込まれて亡くなった方の悲しみに向かい合うことも意味する。そうした悲しみを心の中に抱いたまま、天皇陛下は生活を続けている。
しかもそれらの悲しみは、一つとして同じものはない。日々、そして年々において、違うとき、違う場所で、まったく違う悲しみに向かい合うという、大変つらい仕事をされている。
一般人であれば、「老い」で現役から退くことも可能だが、天皇陛下にその選択肢はない。皇族には職業選択の自由はなく、世襲という地位と責任が義務付けられた上に、離脱する自由もない。そして天皇陛下はご自分で退位や譲位をする自由もない。
これは、あまりにもご自分に自己犠牲や献身を強いる立場であり、私たち日本人はそれに甘んじることを強制してきたことになる。そして、70年にわたり、天皇陛下がそうした大変なお立場に立つことに疑問を感じてこなかった。
しかし、天皇陛下はご高齢の中、例えば東北三県を新幹線やバスを使って長時間移動され、沿道に立つ国民に寄り添うよう、ご挨拶やご会釈をされる。そういった大変につらい日帰りの旅を連日している、いわば私たちの社会でいう「老人」は、日本では他にいないだろう。
安倍首相も、天皇陛下のおことばを重く受け止め、十分な配慮が必要であると発言したが、この問題は政府に投げるのではなく、私たち国民が世論として考えていくべき問題である。
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










