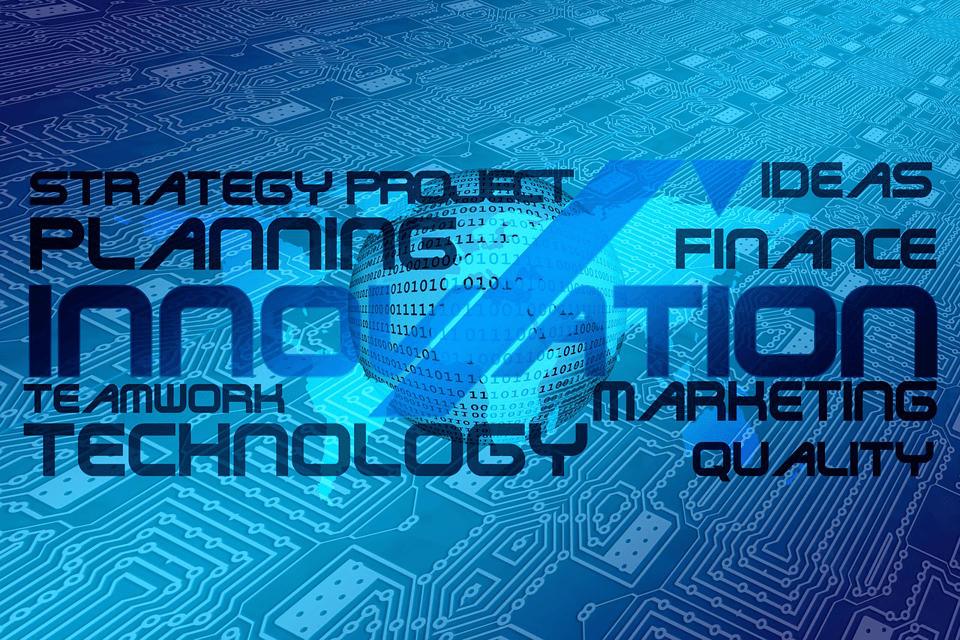●AIに期待してはいけないこととは何か
司会:それでは、鼎談を始めます。今日はおよそ30分という限られた時間ですので、テーマを二つに絞りました。最初のテーマは、「AIによって10年後の社会は、どうなっているのか」です。この点について語り合っていただきたいと思います。まずは小宮山理事長に、口火を切っていただきたいと思います。
小宮山:松尾先生が、今日の講演の最初(『AIで社会・ビジネスはどう変わる?』シリーズ参照)で、「過剰な期待は禁物である。AIにはできることとできないことがある」と言いました。松尾さんの口からネガティブな話が出たのを、私は初めて聞きました。
今日の話の中(松尾氏の講演)で私が一番好きなのは、AIによって「目」のついた機械ができたというところです。これは、カンブリア期における生物の爆発的な進化に匹敵します。脳に目がついたことで脳が進化し、体も大きくなるなどさまざまに進化していき、いろいろな種が生まれたということだと思います。AIの場合、目と脳をつなげたのがディープラーニングであり、体に相当する部分に、日本が得意とする機械やロボット、あるいは自動車といったものをつけていきます。松尾先生は講演の最後の方で、できる例をいろいろと挙げました。介護もできるし、防犯もできるという話がありました。では、できないこととは何か、また過剰な期待とは何なのか。この点を少し伺ってみたいと思います。
松尾:基本的に機械でも「認識」ができるようになるので、人間が見て分かるものは、機械にも分かるようになるはずです。ただその認識でも、できることとできないことがあると思っています。
例えばプロ野球で、ある場面を見て、ヒット性の当たりをショートが横っ飛びで取ってアウトにしたとします。これがファインプレーであることは、人間ならば分かりますが、これを機械にファインプレーだと認識させるには、前提として「通常ならばセーフになります」ということを予測できていないといけません。これは、高次の認知を必要とするような認識タスクになるのです。こういうものは難しいと思います。
つまり、画像を見て、その中の情報だけで「良い・悪い」を判断できるものはいいのですが、その画像の外にあるいろいろな情報と組み合わせて判断しないといけないようなものは難しいと思います。
そのため、比較的シンプルなもの、例...