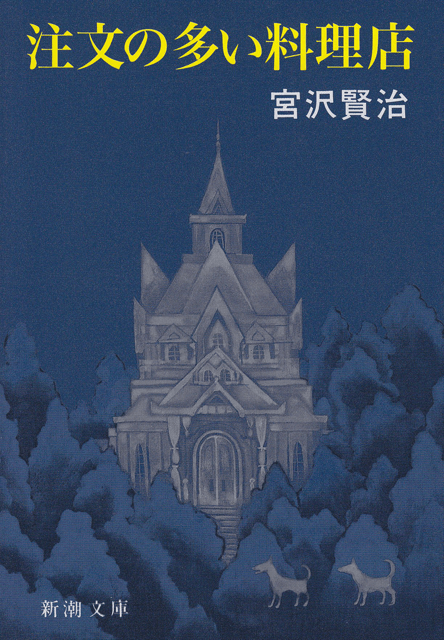●「動物の権利」と動物実験の「3R」
「動物の権利(animal rights)」という概念には多様な問題性があります。一つは、動物の虐待に倫理的問題性がないとは極めて言いにくいこと。それから、動物実験についての「3R」=Reduction、Refinement、Replacementが広く認められていることです。動物実験に肯定的な方々でも、「3R」は必ず掲げています。
Reduction(削減)は、動物実験の数を減らし、不必要な動物実験をしないようにしよう、ということ。今はどうか知りませんが、私が中学生の頃はカエルの解剖を行いました。カエルのお腹を切って、中身のなくなったカエルが水槽の中に浮いているような実験です。あれが本当に必要なのかというと、カエルの内臓の様子はもう分かっていて、人間の知識の中に蓄積されているわけです。だから、不必要な殺生である。ああいうことはしないようにしようという考え方です。
それからRefinement(改善)。これは洗練化していこうということで、できるだけ苦しみを与えないような動物実験を考えていきます。
それからReplacement(代替)。これは動物実験の代わりになるやり方があるならば、わざわざ生きた動物を使わないで、そちらを使いましょうということです。
以上の3Rが、今は広く認められています。
●動物虐待は、その人の犯罪傾向を示唆する
さらに、動物虐待がその人の犯罪傾向を示唆する点も見逃すことができません。
子どもには残酷な面があります。大人同士の関係では普通指摘しないようなことを、ズバッと急に指摘してしまうようなところがあります。それは動物に対しての行為もそうで、トンボの羽をむしったり、カエルの足をちぎったりするようなことを、案外やってのけます。私も思い当たる節が全くないとはいえず、少年に特有の行動といえるでしょう。問題は、成人してからもそういうことをやる方がまれにいるところです。
もう死刑囚として処刑されてしまった方なので実名を挙げると、宅間守という人がいました。小学校に乱入して子どもたちを何人も殺傷してしまい、死刑判決を受けて速やかに処刑されてしまった人物です。彼が成人してからも動物虐待を行っていたという情報が、処刑後に流れました。
動物虐待と犯罪傾向は、非常にパラレルな関係にある。その事実は見逃しがたいわけです。
●「動物の倫理」を語る三つの立場
...