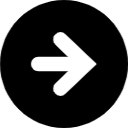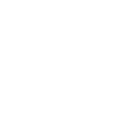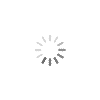この講義シリーズは第2話まで
登録不要で無料視聴できます!
異常気象と気候変動・地球温暖化2
アンサンブル予報を1週間以上先の確率予報に利用する
異常気象と気候変動・地球温暖化2(4)アンサンブル予報
中村尚(東京大学 先端科学技術研究センター シニアリサーシフェロー)
天気の数値予報には、数値大気モデルに伴う不確実性や複雑性に由来する、長期の予報を行えないという限界がある。そこで長期の天気予報に用いられるのが、確率論的な予報である。これは、「アンサンブル」と呼ばれるように、異なる誤差やモデルを利用して複数の予報を行い、それらを併用する天気予報である。(全6話中第4話)
時間:8分29秒
収録日:2019年3月26日
追加日:2019年7月23日
収録日:2019年3月26日
追加日:2019年7月23日
≪全文≫
●日々の数値天気予報には限界がある
決定論的な数値予報には、おのずと限界があります。日々の決定論的な天気予報の限界は、理論的には2週間といわれていますが、大体1週間から10日で限界になります。数値大気モデルの中では大気のいろいろなプロセスが表現されています。ですが、現在までに大きく発達したといっても、数値大気モデルによる表現、あるいは観測データをなじませるデータの同化には、若干の不完全性が残ってしまいます。
さらにそうした不確実性に加えて、大気の循環自体が実は非線型性を有しているという問題もあります。つまり、数値天気予報においては、予報される変数が積の形すなわち掛け算の形で出てきます。これはカオス的なものになりがちであることが数学的に分かっています。そこでは、非線型性が原因となって、初期に生じたほんのわずかな観測値の誤差が急速に拡大してしまいます。そして、いずれは限界に達してしまい、予報の価値がなくなるところまで増幅してしまうわけです。
●確率的な天気予報
しかし、数値予報に限界があるとしても、われわれはここで諦めているわけではありません。決定論的な予測を行うのはここまでにして、後は確率論的な予測を行っています。それが確率予報です。例えば、上の図に示したような落ち葉のことを考えてください。秋になると落ち葉が落下してきますが、正確にどの位置に落ちるか、これを予測するのは困難です。
それがなぜかといえば、非常に小さな大気の乱れがあるからです。しかしながら、われわれには、風がなければほぼ木の真下に落ち葉は落下するだろう、そう容易に想像することができるわけです。さらに風が吹いてきたとしても、この風がある程度一定であれば風下側に落ち葉が流れて落下するだろうし、この風全体が不安定であれば広い範囲に散らばってしまうだろう、といった予測もできます。つまりこれは、もし風が持続的であれば、その影響を確率論的に予測できることを意味します。例えば、風上側に落ち葉はほとんど来ないだろうと、われわれにはいえるわけです。
●アンサンブル予報によって、不確実性を逆手に取る
ですから、1週間以上先の確率予報では、こういった予測を利用するわけです。われわれはこれを「アンサンブル...
●日々の数値天気予報には限界がある
決定論的な数値予報には、おのずと限界があります。日々の決定論的な天気予報の限界は、理論的には2週間といわれていますが、大体1週間から10日で限界になります。数値大気モデルの中では大気のいろいろなプロセスが表現されています。ですが、現在までに大きく発達したといっても、数値大気モデルによる表現、あるいは観測データをなじませるデータの同化には、若干の不完全性が残ってしまいます。
さらにそうした不確実性に加えて、大気の循環自体が実は非線型性を有しているという問題もあります。つまり、数値天気予報においては、予報される変数が積の形すなわち掛け算の形で出てきます。これはカオス的なものになりがちであることが数学的に分かっています。そこでは、非線型性が原因となって、初期に生じたほんのわずかな観測値の誤差が急速に拡大してしまいます。そして、いずれは限界に達してしまい、予報の価値がなくなるところまで増幅してしまうわけです。
●確率的な天気予報
しかし、数値予報に限界があるとしても、われわれはここで諦めているわけではありません。決定論的な予測を行うのはここまでにして、後は確率論的な予測を行っています。それが確率予報です。例えば、上の図に示したような落ち葉のことを考えてください。秋になると落ち葉が落下してきますが、正確にどの位置に落ちるか、これを予測するのは困難です。
それがなぜかといえば、非常に小さな大気の乱れがあるからです。しかしながら、われわれには、風がなければほぼ木の真下に落ち葉は落下するだろう、そう容易に想像することができるわけです。さらに風が吹いてきたとしても、この風がある程度一定であれば風下側に落ち葉が流れて落下するだろうし、この風全体が不安定であれば広い範囲に散らばってしまうだろう、といった予測もできます。つまりこれは、もし風が持続的であれば、その影響を確率論的に予測できることを意味します。例えば、風上側に落ち葉はほとんど来ないだろうと、われわれにはいえるわけです。
●アンサンブル予報によって、不確実性を逆手に取る
ですから、1週間以上先の確率予報では、こういった予測を利用するわけです。われわれはこれを「アンサンブル...
「科学と技術」でまず見るべき講義シリーズ
なぜ雄と雌の2つの性別があるのか…「性」の謎とLGBT
長谷川眞理子
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子
MLBのスーパースターも一代限り…生物学から迫る性の実態
長谷川眞理子
人気の講義ランキングTOP10
【10分解説】福島第一原発事故…吉田昌郎氏と現場の底力
テンミニッツ・アカデミー編集部