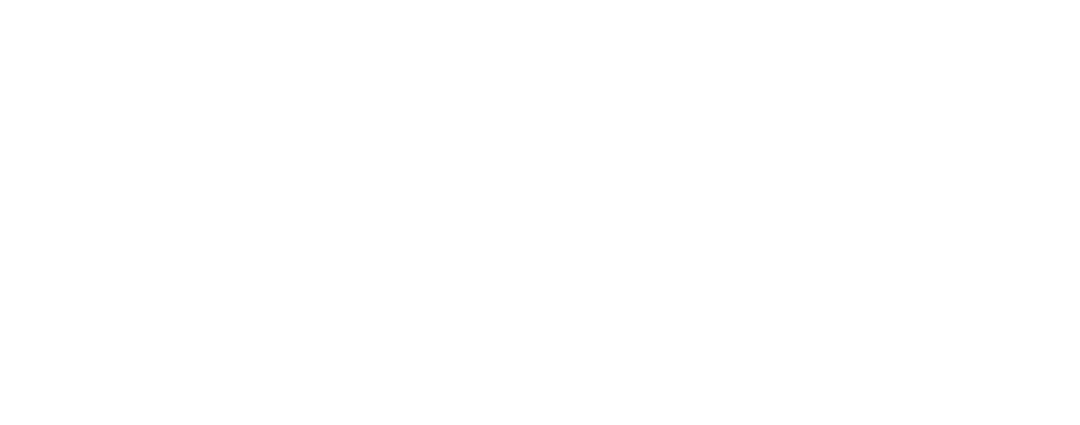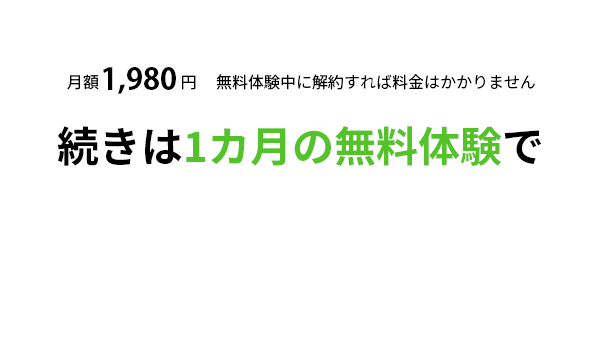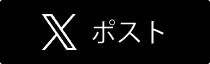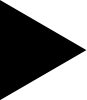●第二の人生のモデルを伊能忠敬から学ぶ
―― 本日は童門冬二先生に、「第二の人生を生かす工夫と覚悟」ということで、伊能忠敬のお話を伺いたいと思っております。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
童門 よろしくお願いいたします。
―― 最近、企業でも「リカレント教育」ということがよく言われて、いわゆる学び直しということで、40歳とか、50歳ぐらいの方々がまさに第二の人生を目指して、どう考えればいいのかとか、どういった生き方をすればいいか、ということについて、研修で取り組むケースが多いらしいのです。
そういうなかで、やはり皆さまがパッと頭に思い浮かべる1人が伊能忠敬だろうと思います。今見ても驚くほど精巧な日本地図を、まさに隠居した後で勉強を始めて、つくり出したというところは、今後の生き方の何か参考になるのではないかというところで、伊能忠敬についてお聞きしたいと思っております。
童門 分かりました。
―― ただ、そうは言っても、いきなり隠居の話からしても話が分かりませんので、まず伊能忠敬はどういう少年時代、壮年時代を過ごしたのかというところからお聞きしたいと思います。そもそもどういう少年だったんでしょうか。
童門 悪い言葉を使えば、やや肩を落とした、ぐれていた。
―― ぐれていた、と。
童門 これは家庭の事情だと思うんです。伊能忠敬のおじいさんは、九十九里のかなり大きい、なんていうんでしょうか、船稼業の親方だったんです。伊能忠敬のお父さんはそこへ養子に入ったんですけれども、そっちにはあまり向かない。どっちかというと学者肌で、まじめにコツコツと1人で生きていくというようなことならやれるんだけれども、大勢の荒くれ男を使ったり、現場の指揮を取ったり、荒海に乗り出してどうこうというのは不得意なのです。
結局、忠敬さんは、ある年までそこの家で生まれ育ったんですけど、自分の立ち位置がつかめない。おじいさんを見てれば、ガミガミと自分のお父さんを怒鳴りつけて、なんとか一人前の漁師宿の親方にしようとしている。ところが、先ほど言ったように、お父さんのタイプは全然違いますから、忠敬さんは間に入って、子どもながらにとても心を痛めていたんです。
●少年時代から星の知識は大人顔負け
童門 だけど、そんなことをいっていても、やっぱり自分もお父さんの子であり、おじいさんの孫な...