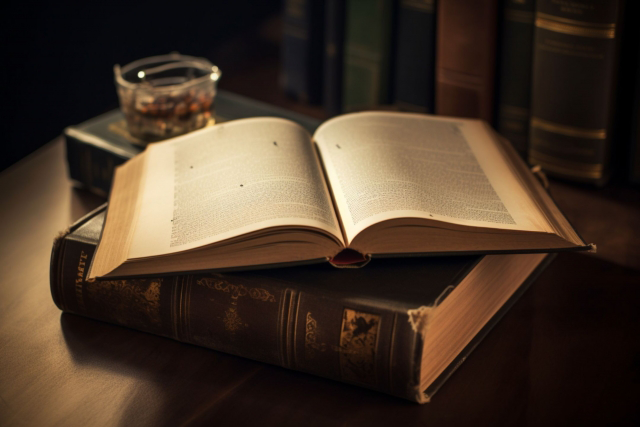●人間の愚かさを寿ぐシェイクスピアの喜劇世界と人文主義思想
こんにちは。河合祥一郎です。第4回は、シェイクスピアの喜劇世界を取り上げることにしましょう。
悲劇世界が“To be OR not to be(あれかこれか)”の世界ならば、喜劇世界は“To be AND not to be(あれでもあり、これでもある)”の世界だといわれています。これは、前回ご紹介したオクシモロン(矛盾語法)の世界です。
“Oxymoron”というのはもともとギリシャ語で“Oxy-”は「賢い」、“moron”は「愚か」を表します。シェイクスピアには“wise fool(賢い道化)”が多数登場しますが、道化(fool)というのは愚か者という意味ですから、“wise fool”自体がオクシモロンです。喜劇の最高峰とされる『十二夜』ではヒロインのヴァイオラが“This fellow is wise enough to play the fool.(この人は道化を演じられるほど賢い)”と言います。
愚かであることが寿(ことほ)がれる世界、それがシェイクスピアの喜劇世界だといっていいでしょう。シェイクスピアには、人間とは愚かな存在であるという認識があります。
シェイクスピアが描きだす人間の本質というものは、当時のヨーロッパに広く浸透していた人文主義思想、ユマニスムと切り離して考えることはできません。人文主義者としては、『痴愚神礼讃』を著したエラスムス(1466年-1536年)や、『ユートピア』を書いたサー・トマス・モア(1478年-1535年)などが有名ですが、その思想はギリシャ・ローマ時代の文芸復興の機運と結びつき、人間性を肯定するものでした。
その人間性とは、常に正しい神とは違って、人間は過ちを犯すものであり、過ちを改めることに意義があるとする考え方に基づきます。
人間は愚かだということを認めて、自分の至らなさを自覚するところから始めようとするのが人文主義思想です。
この思想を遡れば、哲学の父祖であるソクラテスに至ります。ソクラテスが説いた「無知の知」という思想が人文主義の基礎を成しているといえます。無知の知とは何か。それはこのように説明されます。
ある日アテネの神託があって、ソクラテスは「アテネ中で一番の賢者はソクラテス...