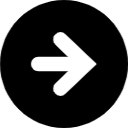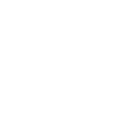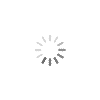ダーウィンの進化論は、生物の目的や社会の発展といった進歩思想とは区別された、純粋な科学的理論構築として取り組まれていた。しかし、ダーウィンの理論を受け入れ、広めた多くは進歩思想を支持する人々だった。進歩思想に「利用」された進化論、その内実について、スペンサーの「社会進化論」を交えながら解説する。(2025年5月15日開催:早稲田大学Life Redesign College〈LRC〉講座より、全9話中第7話)
※司会者:川上達史(テンミニッツ・アカデミー編集長)
≪全文≫
●社会思想としての進化論
長谷川 今までの話は生物学の進化の話です。(その話には)目的とか、目標とか、方向性とか、生気とか、魂とか、そういうものは全然入っていないのです。良くなるとも言っていません。それは環境次第、(つまり)環境からの圧力次第なので、どうなるかということに人間がいいと思うかどうかは関係ないのです。
ところが、社会思想としての進化論は必ずあって、それは「進歩思想」なのです。進歩思想は、世の中は変わる、変われる、良い方向に変わることができる、人間が考えて、より良い社会をつくることができる、未来は変えられるという確信です。それは人間の思考を信じることなので、人間万歳主義でもあります。人間礼讃でもあります。
それが欧米で始まったのはルネサンスの頃です。ルネサンスのときに人間が見るものを信用して、記述しましょうということになったのです。それまで、(つまり)中世までのヨーロッパは、人間はアホなのだから、神様に及びもつかないのだから、人間が書くもの、描写したものは全然信用できないといっていたのです。それがルネサンス(の頃に)変わって、人間中心主義になっていくのです。
それに対して保守思想は、世の中は変わらない、階級制度など変わらない、変えることはできない、だから各自、分相応に生きるべきだということです。なぜなら世の中がこうなるように神様がつくったので、神様の意思で変わるかもしれないけれど、人間が変えることはできないだろうということです。
また、神様は人間に悪いことはしないはずで、王権神授説はそういうものを逆手に取って、王様は神様からもらった地位なのだから、すごいという説明をするわけです。そういうものを受け入れることとか、災難が起こると、それは人間が悪かったから神様(から)の罰だと言ったり、人間に試練を与えているのだと言ったりして、災難をそのまま受け入れようとするという現状肯定、現状維持、変革必要なしというものを保守思想とすると、そうではない進歩思想がルネサンス以降は確実にあったと思います。
ヨーロッパの中世はまさに保守思想の時代です。変わらない神様がこうやって(世の中を)つくって、(それは)おそらく人間のためを思ってやっているのだから、分相応に生きましょう...