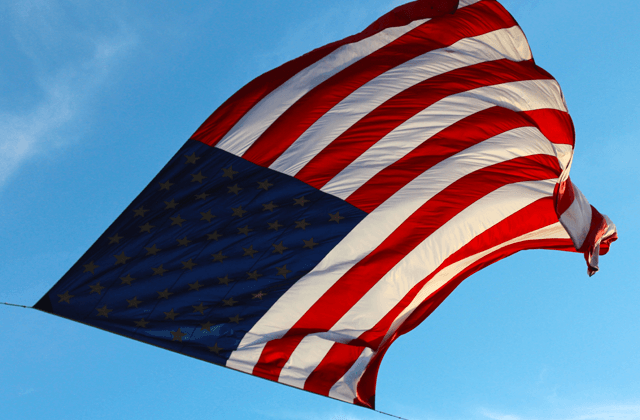
アメリカのマクロ政策が日本の追い風になる理由
アメリカ・ファーストの保護主義より注目すべきトランプ政策
「米国を偉大にする」ために着手されているトランプ大統領の政策。NAFTAの見直しやTPPからの離脱、メキシコ国境の壁建設など、保護主義・排他主義的な面のインパクトばかりが強く伝わっています。しかし、国際経済学を専門として学習院大学国際社会科学部でも教鞭をとる伊藤元重氏は、新大統領のマクロ政策にこそ注目すべきだと言います。この波にうまく乗れば、日本が2017年中にデフレから脱却することも夢ではないというのです。
アメリカ・ファーストの政策によって貿易摩擦が再来すれば、日米関係も悪化するのではないかと懸念される方も多いでしょう。しかし、「ジャパンバッシング」が激しかった1980年代から90年代にかけても、実は日米間の貿易や投資額は減少せず、むしろ増えていたのです。
貿易摩擦に遭遇する各個の企業や産業にとって痛みは耐えがたく思われるでしょうが、マクロ経済にとって最大の影響を及ぼすのは、トランプ政権による「財政拡張・金融引き締め」政策だと伊藤氏は強調しています。
アメリカのマクロ政策が日本の追い風になる理由
アメリカの「財政拡張・金融引き締め」路線は、なぜデフレ脱却を目指す日本に格好の追い風になるのでしょうか。もっとも分かりやすい例として、伊藤氏は十年物国債を例にとります。いま、日本の十年物国債は0%近傍に抑えられています。一方でアメリカやドイツの長期金利は2.5%前後まで上昇しています。このように2%以上もの長期金利差によって、日本のゼロ金利策が効果を上げることは、常識で考えても明らかでしょう。
アメリカの金利が上がれば上がるほど円安は長引き、日本のゼロ金利の効果は強くなります。これが、日本のマクロ政策にとって何よりの明るい側面なのです。
トランプ氏の口先介入は、警戒すべきなのか
金融市場では、トランプ大統領がドル高是正の「口先介入」を行なってくる点を非常に警戒しています。しかし、伊藤氏は「トランプにとっての最大の敵はトランプ自身」という『フィナンシャル・タイムズ』のコメントを紹介することで、この議論のおかしさを指摘しています。大統領自身が減税や歳出増やアメリカの雇用増を目指す保護主義的政策を進めていく。それにつれてアメリカ経済は刺激され、ドル高+金利上昇が起こるわけです。一方でそれを強力に推進しながら、口だけで「ドル高は好ましくない」と抑えようとしても、自身の政策と真逆を指すわけなので説得力がない、ということです。
実際、トランプ氏発言によって円高に振れる局面も何度かありましたが、2~3日もすればもとどおりの円安に戻っています。為替レートを決めるのは大統領発言ではなく、アメリカ経済と日本経済のファンダメンタルズなのです。その点を、日本は冷静に見ていく必要があるでしょう。
真のトランプ・リスクはどこにあるのか
将来に向けて警戒が必要なのは、1985年の「プラザ合意」の二の舞を引き起こす点だとも、伊藤氏は危惧しています。当時起こっていたのは、トランプ政権と瓜二つといってもいいレーガン政権の経済政策による極度のドル高でした。円・ドルレートは一時250円に達し、とりわけアメリカの対日貿易赤字が顕著でした。先進5カ国 (G5)による合意により、円高ドル安への速やかな誘導が行われたわけですが、実質的にはアメリカが主要各国に対してマクロ政策の変更を求めたわけです。日本においては、プラザ合意以降のマクロ政策対応の失敗が、バブルを引き起こし、その後のバブル崩壊につながっていったと、伊藤氏は警告しています。マクロ政策のレベルにまで、トランプ大統領が介入してくることこそ、最大のリスクと捉えておく必要があるでしょう。
しかし、当面のところは、アメリカの財政拡張が日本のデフレ脱却政策にとって追い風になるということです。だとすれば、日本はこのチャンスを生かして、なんとかデフレから脱出する道筋をつくっていきたいものですね。
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子







