テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
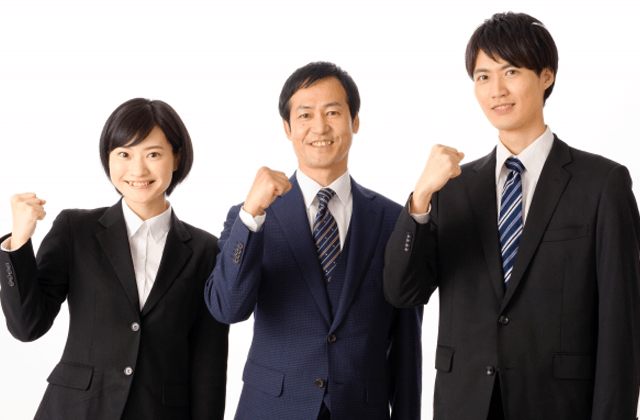
「働き方改革」と「ゆとり教育」の共通点とは?
働き方改革は具体的に何を改革するのか
安倍晋三首相が掲げる経済政策アベノミクスの中でも、ひときわ注目を集めている「働き方改革」。日本国民全員が活躍できる「一億総活躍社会」実現のための政策です。2016年9月27日には内閣の働き方改革実現会議で改革の具体策がまとめられました。その内容は、正社員と非正規社員の賃金格差をなくす同一労働同一賃金の導入、高齢者や女性の就業促進など。そして最も力を入れているのが長時間労働の是正です。
長時間労働の弊害といえば過労死がよく報道されますが、同じくらいに労働生産性の低さも問題視されています。日本は世界の主要国の中でも低レベルにあり、克服には長時間労働の是正が必要不可欠といわれています。
労働生産性の意味と計算方法
それでは、労働生産性とはどんなものでしょうか。そして、なぜ長時間労働を改めると労働生産性が向上するのでしょうか。「生産性」とは経済学の用語で、資源から付加価値を生み出す効率をいいます。計算式は「生産性=産出量(アウトプット)÷投入量(インプット)」。投入された資源からより多くの付加価値が産出されれば、生産性が高いといえます。
生産性は何を基準にするかで種類が異なり、労働生産性は労働量に対してどれだけの価値が生み出せたかを評価します。このとき、時間当たりの労働生産性を導き出す労働量の数値は「時間」です。計算式は「労働生産性=付加価値÷時間」。つまり同じ産出量を保って労働時間を減らせば、労働生産性は向上する計算になります。
「日本は労働生産性が低い」の真意
公益財団法人・日本生産性本部が発表した2015年の日本の労働生産性は、国際機関・経済協力開発機構、略称OECD加盟国35か国のうち22位でした。主要7か国の中では最低で、本当に労働生産性は低いように見えます。しかし、日本と世界では労働生産性の計算式が異なることを忘れてはいけません。国際比較では「労働生産性=GDP(国内総生産)÷総就業者数」という計算式を用います。インプットに当たる労働量の数値が時間ではなく人数なので、日本は世界と比べて長時間労働をしているという立証にはならないのです。
働き方改革はゆとり教育の二の舞を踏んではならない
しかもこれから日本に降りかかる大きな問題は、労働生産性の低さよりも人口減少による市場の縮小です。人口が減れば労働者だけでなく消費者も減ります。その結果、消費はすぐに限界を迎えます。長時間労働を是正して生産性を向上しても、消費されず無駄になってしまうのです。これからの時代は、付加価値を向上させるほうが重要になります。こうして見ると、長時間労働の是正はデータに踊らされた短絡的な発想かもしれません。しかし、働き方改革すべてが否定されるべきではないでしょう。過労死や女性の働きにくさなどは解決すべき問題です。
だからこそ働き方改革は、理想だけが先行した「ゆとり教育」の二の舞にならないよう進めなくてはなりません。ゆとり教育は長期的に豊かな発想力を育てる計画でしたが、数年後にOECDの調査で学力低下が判明するとすぐに批判され、中途半端な改革になってしまいました。こうしていわゆる「ゆとり世代」が誕生したのです。
すでに大企業社員のゆとり化がはじまっている
ゆとり世代の特徴といえば「楽な方向に流れたがる」、「自主性がない」などがあげられます。実は今、このような社会人が大企業を中心に増加しつつあります。現状の働き方改革における生産性の向上は、結局のところ時短勤務でしかありません。このため、大企業の社員は勤務時間内にさばけない仕事をすべて外注に回します。この結果、自分の仕事の細部を知ろうともせずに成果だけ求め、外注先に無茶ばかり言う「ゆとり社員」が増えているのです。
これでは社員自身の考える力が育たず、来たる市場縮小時代に付加価値を上げるアイデアなど出るはずもありません。大企業は自分で自分の首を絞めています。
働き方改革も理想は国民の願いと一致しますが、どんな弊害が生じるかを予測して進めなければ悲惨な終末を迎えるでしょう。一億総活躍社会実現をめざして、しっかり吟味しながら進めてほしいものです。
<参考サイト>
・財団法人日本生産性本部 労働生産性の国際比較
http://www.jpc-net.jp/intl_comparison/?fullweb=1
・財団法人日本生産性本部 労働生産性の国際比較
http://www.jpc-net.jp/intl_comparison/?fullweb=1
人気の講義ランキングTOP20










