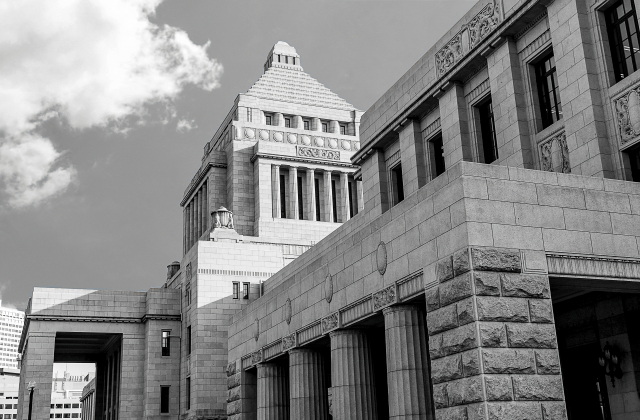
安倍首相が唱えた「戦後レジーム」とは何か?
2017年9月、「国難突破解散」が行われ、11月に第4次安倍内閣が発足しました。「国難」とは何なのか首をひねった国民も多いなか、安倍首相独特の言葉使いの原点として「戦後レジーム」を思い出す人も多かったのではないでしょうか。ここでは、政治学者で慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授である曽根泰教氏による「戦後レジーム」の解説を聞いてみましょう。
IMFが定まったのは、1944年7月のブレトンウッズ会議(連合国国際通貨金融会議)の席上でした。まだヒトラーがノルマンディー上陸作戦を受け止め、サイパン島で日本軍守備隊3万人が玉砕して日本への本土空襲が本格化する以前、すでにアメリカとイギリスは新しい世界システムの構築に乗り出していたのです。
新しいシステムが必要とされた背景には、二度にわたる世界大戦と国際金融の関係への反省がありました。世界44か国の代表が参加した会議で、国際金融のシステム、ルール、制度、手続きなどの議論を主導したのは、イギリスの政治経済学者ジョン・メーナード・ケインズとアメリカの官僚ハリー・ホワイト。協議の末、基軸通貨はドル、金とドルの交換レートが固定される固定相場制、金本位制とされました。IMFは、この結果を受け、戦後の体制下で安定した通貨制度を確保するために国際復興開発銀行(IBRD)とともに決定され、1945年12月に創設された機関です。
ブレトンウッズ体制崩壊後のIMFは、為替の安定化と国際的な金融秩序の維持を、国連の一部機関として担っています。具体的には加盟国の収支が悪化したときにSDR(特別引出権)制度を通じて融資をする一方、為替の安定のため各国の為替政策を監視する役割です。
SDRは、ドル、ポンド、ユーロ、円、元などの決済通貨で構成される通貨バスケットで、加盟国がIMFから融資を受けるときに利用する、いわば仮想の準備通貨。アメリカからの金の流出が続いた1969年に創設され、金本位制崩壊後のIMFを支えています。
リーマンショック後の2009年4月にロンドンでG20(20か国財務相・中央銀行総裁会議)が開催されたときには、英国のブラウン首相がブレトンウッズIIの構築を求めましたが、まだ実現はしていません。半年後の10月にはギリシャ危機が起こり、IMFはEUとともに構造改革を強く迫っています。
IMFは2014年に70周年を迎え、2016年現在の加盟国は188を数えます。同年10月、SDRバスケットに5番目の通貨として中国人民元が採用されて話題となりましたが、曽根氏はそれが戦後レジームを動かすきっかけになる可能性とともに、逆に中国経済を改善する「外圧」となる可能性も考えているようです。お目付役としてのIMFは、「戦後レジーム」の最後の役割を果たすため、まだまだ健在というところでしょうか。
「戦後レジーム」、日本の話だと思ったら大間違い
「レジーム」は体制のことですから、「戦後レジーム」は第二次世界大戦後に確立された世界秩序を指します。つまり、戦後レジームは日本一国の体制を指す言葉ではなく、世界を支えたヤルタ体制やその他の制度を指す言葉なのです。ただし、ヤルタ体制はすぐ冷戦に直面して効力を失いました。今も残る戦後レジームは「IMF(国際通貨基金)」に他ならないと曽根氏は指摘します。IMFが定まったのは、1944年7月のブレトンウッズ会議(連合国国際通貨金融会議)の席上でした。まだヒトラーがノルマンディー上陸作戦を受け止め、サイパン島で日本軍守備隊3万人が玉砕して日本への本土空襲が本格化する以前、すでにアメリカとイギリスは新しい世界システムの構築に乗り出していたのです。
新しいシステムが必要とされた背景には、二度にわたる世界大戦と国際金融の関係への反省がありました。世界44か国の代表が参加した会議で、国際金融のシステム、ルール、制度、手続きなどの議論を主導したのは、イギリスの政治経済学者ジョン・メーナード・ケインズとアメリカの官僚ハリー・ホワイト。協議の末、基軸通貨はドル、金とドルの交換レートが固定される固定相場制、金本位制とされました。IMFは、この結果を受け、戦後の体制下で安定した通貨制度を確保するために国際復興開発銀行(IBRD)とともに決定され、1945年12月に創設された機関です。
ニクソンショック後も片肺飛行を続けるIMF
ブレトンウッズ体制自体は1971年のニクソンショックの際、アメリカがドルと金の交換停止を一方的に宣言したために終了しましたが、IMFは依然として存続しています。変動相場制に移行したにもかかわらず、IMFが「片肺飛行」で続くことに誰も異を唱えなかったのでしょうか。ブレトンウッズ体制崩壊後のIMFは、為替の安定化と国際的な金融秩序の維持を、国連の一部機関として担っています。具体的には加盟国の収支が悪化したときにSDR(特別引出権)制度を通じて融資をする一方、為替の安定のため各国の為替政策を監視する役割です。
SDRは、ドル、ポンド、ユーロ、円、元などの決済通貨で構成される通貨バスケットで、加盟国がIMFから融資を受けるときに利用する、いわば仮想の準備通貨。アメリカからの金の流出が続いた1969年に創設され、金本位制崩壊後のIMFを支えています。
事実上の機能は果たせなくてもお目付役として
1997年のアジア通貨危機の際、IMFはタイ、インドネシア、韓国などの加盟国に対して、歳出削減や増税、金利引下げはおろか、構造改革の実施まで迫りました。権限を超えた動きであるとの批判もあり、IMFの役割終了を指摘する声も上がりましたが、事実上機能を果たせなかったのは、時代にマッチしない古さが問題でしょう。リーマンショック後の2009年4月にロンドンでG20(20か国財務相・中央銀行総裁会議)が開催されたときには、英国のブラウン首相がブレトンウッズIIの構築を求めましたが、まだ実現はしていません。半年後の10月にはギリシャ危機が起こり、IMFはEUとともに構造改革を強く迫っています。
IMFは2014年に70周年を迎え、2016年現在の加盟国は188を数えます。同年10月、SDRバスケットに5番目の通貨として中国人民元が採用されて話題となりましたが、曽根氏はそれが戦後レジームを動かすきっかけになる可能性とともに、逆に中国経済を改善する「外圧」となる可能性も考えているようです。お目付役としてのIMFは、「戦後レジーム」の最後の役割を果たすため、まだまだ健在というところでしょうか。
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子







