テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
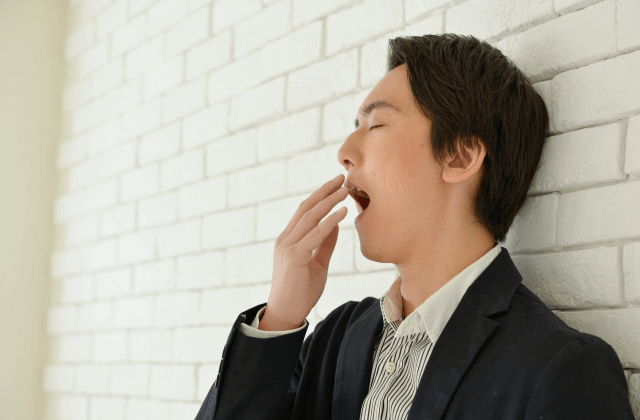
夜勤で寿命が縮む?昼夜逆転のリスク
最近、長期間にわたって頻繁に昼夜が逆転して体内時計が乱されると死亡率が高まる傾向にあることを、京都府立医大の研究チームがマウスの実験で明らかにしました。これまで、体内時計の乱れにより睡眠障害などのリスクがあることは知られていましたが、長期的な影響は初めて証明されたとのことです。
この話、シフト勤務の仕事の方に関連してくるのではないでしょうか。シフト勤務といえば看護師、介護士、消防士、警備員、24時間営業店のスタッフなどが代表的ですが、最近は特に医療や福祉の需要が高いこともあり、この形態で働く方も増えているように思われます。
「正循環の交代周期」とは、24時間毎におよそ1時間後ろにずれていく人間の生体リズムに逆らわないよう、連続勤務の開始時刻をより遅く設定するというものです。例として「日勤→準夜勤→休→深夜勤」が推奨されています。ですが、アンケートを取ると、これを実施している職場は2014年の時点で23.3%となっています。これは、現実問題としてそれを実施することが簡単ではないということでしょう。
こう考えると、今回の研究で明らかになった「頻繁に昼夜が逆転すると死亡率が高まる」という事実は、人手不足の現場の危機感をより明確に照らし出すようにも思えます。寿命にまで影響することがわかった以上、今後どのように人手不足を解消していけるのか、ということも大きな問題といえるのではないでしょうか。
「きついシフト」はリスクが大きい
実験は、明るい時間帯を7日ごとに8時間ずつ後ろにずらしていく「ゆるいシフト」と、4日ごとに8時間ずつ前倒しする「きついシフト」の2つの環境下で、1年9カ月かけてマウスを育てるというものです。実験の結果、「ゆるいシフト」だと体内時計の乱れは軽微でしたが、「きついシフト」ではマウスが変化に適応できず、行動リズムが乱れたそうです。死亡率に関しても「きついシフト」の方が4.26倍高いと推定されています。また、死んだマウスの67%で白血球の増加など、炎症反応が確認されたとのこと。この話、シフト勤務の仕事の方に関連してくるのではないでしょうか。シフト勤務といえば看護師、介護士、消防士、警備員、24時間営業店のスタッフなどが代表的ですが、最近は特に医療や福祉の需要が高いこともあり、この形態で働く方も増えているように思われます。
看護業界での現実
今回、長期的な健康への影響が明らかにされたわけですが、これ以前から、公益社団法人日本看護協会は「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」を出し、勤務時間の上限などとともに、「交代の方向は正循環の交代周期とする」ことを提案してきました。「正循環の交代周期」とは、24時間毎におよそ1時間後ろにずれていく人間の生体リズムに逆らわないよう、連続勤務の開始時刻をより遅く設定するというものです。例として「日勤→準夜勤→休→深夜勤」が推奨されています。ですが、アンケートを取ると、これを実施している職場は2014年の時点で23.3%となっています。これは、現実問題としてそれを実施することが簡単ではないということでしょう。
シフト勤務の人手不足も大きな問題
どのようなシフトであればより身体への負担が少ないのかという点に関しては、まだ明確な解答が出ていないようです。もちろん、ここはさらなる研究が待たれます。しかし、シフト勤務の職場は、体調を崩して離職する人も多いといわれる職場です。先ほど示した「正循環の交代周期」が保てない理由も、最も大きい点は人手不足にあると考えていいのでしょう。そこで足りない人手の穴埋めに追われ、さらに急なシフトの変更が起こります。つまり、連鎖的に人間の生体リズムを逸脱した過酷な労働が起こるという悪循環があります。こう考えると、今回の研究で明らかになった「頻繁に昼夜が逆転すると死亡率が高まる」という事実は、人手不足の現場の危機感をより明確に照らし出すようにも思えます。寿命にまで影響することがわかった以上、今後どのように人手不足を解消していけるのか、ということも大きな問題といえるのではないでしょうか。
<参考サイト>
・朝日新聞:頻繁に昼夜逆転→死亡率高く きついシフトをマウス実験
http://www.asahi.com/articles/ASKBK5S15KBKPLBJ002.html
・公益社団法人日本看護協会:看護職の労働環境の整備の推進
https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/yakinkotai/chosa/index.html
・朝日新聞:頻繁に昼夜逆転→死亡率高く きついシフトをマウス実験
http://www.asahi.com/articles/ASKBK5S15KBKPLBJ002.html
・公益社団法人日本看護協会:看護職の労働環境の整備の推進
https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/yakinkotai/chosa/index.html
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
昭和陸軍の派閥抗争には三つの要因があった
中西輝政










