テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
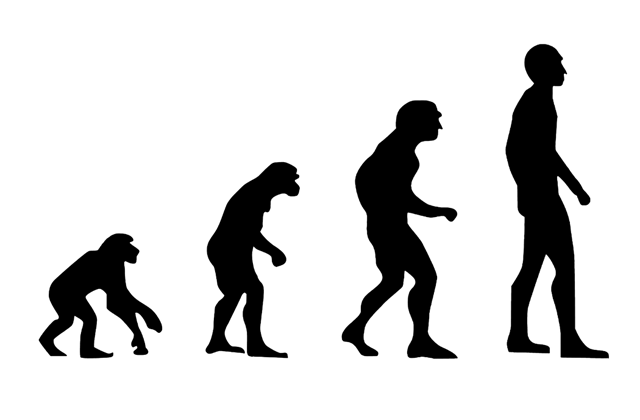
人類の進化の歴史と科学技術の発展
人類の進化に影響する環境要素
地球と人類の歴史の長さをたとえる時、時計を用いて「人類は最後のほんの一秒で地球上に現われた超新参者」という表現が使われます。チンパンジーから分岐して道具を使い文明を持つ人類が誕生したのが約600万年前。その人類進化史のなかで科学と技術が結びつき新たな道具や方法が生みだされた産業革命はほんの100~150年前のことです。ですから、人類はまばたき一つの何十分の一といったごく短い時間で、信じられないようなスピードで進化をしてきたのだと言えるでしょう。総合研究大学院大学長であり、長年、進化生物学の研究に携わってきた長谷川眞理子氏は、ヒトの進化の鍵を握る人類共通の環境要素として5項目を挙げます。
それは「高栄養・高エネルギーの獲得困難な食物に特化したこと」「食料獲得その他に対して、いろいろな技術を使用したこと」「集団内で協力をしながら生きてきたこと」「両親や血縁だけでなく、非血縁のいろいろな人が協力して子育てをしたこと」そして「言語などによって非常に高度な知識を共有して伝達してきたこと」です。
このような共通する環境要素のもと、科学技術文明の発展とともに人類は進化してきました。
人類の進化と科学文明の歴史
科学文明の大本は古代ギリシャにあると言われています。世界を客観的・総体的・普遍的・合理的に説明しようとする知の営みが繰り広げられ、多くの哲学者や思想家、歴史家、文学者等による一大文明が形成されました。しかし、こうした思索、思弁に加えて、普遍的な説明体系が構築されたのは17世紀以降のヨーロッパにおける近代科学の発祥を待たなければなりません。科学的考え方そのものは、古代ギリシャに端を発します。問題解決のために議論を繰り返し、説明に裏打ちされた仮説を提出する。さらに改訂をどんどん加えて取り入れていく。こうした議論をもって得た結論は、「神のお告げによるものだから」という権威で無条件に受け入れるものではなく、また一人の思想家が「こう思う」と結論づけるものでもありません。みなで議論したことによる「集合知」として獲得、蓄積されていったのです。
さらに、このような集合知にいたるプロセスを基盤に、17世紀ヨーロッパでは実験や観察を行うことで、近代科学としての文明のあり方を確立していきました。
近代科学の基礎確立に貢献した帰納法と演繹法
長谷川氏は、17世紀ヨーロッパの近代科学の柱となった人物として、二人の哲学者を挙げます。一人はイギリスのフランスシス・ベーコン。もう一人はフランスのルネ・デカルトです。ベーコンは観察なくして思弁だけでは真実に到達できないと考えました。そこで、複数の具体的な事実を観察し、その中からある傾向を抽出して経験的な法則を見出す帰納法を編みだしました。一方、デカルトは一般的かつ普遍的事実を前提として、そこから結論を導きだすという論理的展開を行う演繹法を提唱しました。こうして観察や実験によって、客観的に現象を把握し論理的に仮説を創出する、実証、反証を加えて改訂を施していくという近代科学の基礎が成立しました。これが、その後のめくるめく人類進化に大きく寄与していくこととなったのです。
ヒトの賢さを過信してはならない
しかし、このような科学文明を享受してきたヒトの脳も万能コンピューターというわけではありません。それどころか、霊長類以前の猿の臓器としての脳みその働きが、われわれ人間の行動に重大な役割を果たしているのだ、と長谷川氏は述べ、認知心理学者で動物行動学者のフランス・ドゥ・ヴァール氏の著書『動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか?』による問題提起に注目しています。人間はもっと自身の愚かさ、動物の賢さを知った上で進化の歴史を振りかえる必要があるのではないでしょうか。やがて人類が「賢さにおぼれ、自分自身が生みだした科学技術にからめとられて滅んでしまった愚かな生き物」などと他生物から烙印を押される、そんな日を迎えないためにも。
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
葛飾北斎と応為の見事な「画狂人生」を絵と解説で辿る
テンミニッツ・アカデミー編集部
最近の話題は宇宙生命学…生命の起源に迫る可能性
川口淳一郎










