テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
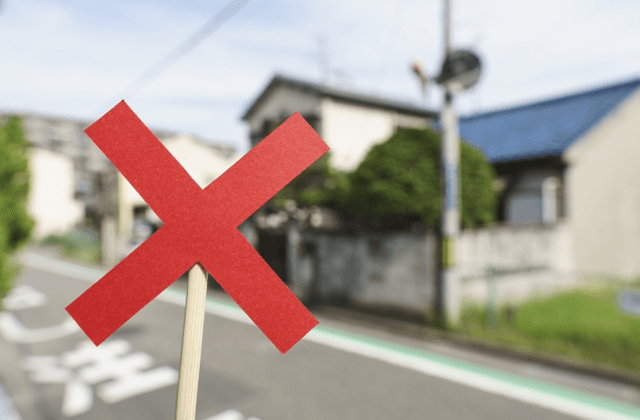
最も多いご近所トラブル、第1位は?
新生活を始めるにあたって、気になるのがご近所とのお付き合い。ご近所とは末永く仲良くいたいものですが、やはりトラブルがあった時のことを考えておくに越したことはありません。
実際にはどのようなご近所トラブルが多いのでしょうか。ご近所トラブルランキングと、実際にトラブルに遭った場合の対処法や、未然に防ぐための予防法などをご紹介します。
また少し前の調査となりますが、不動産検索サイトSUUMOによる2015年の調査でも、ご近所トラブルで1位は「騒音(45.9%)」。次いで「挨拶(25.9%)」「車や駐車場の使い方(21.5%)」「タバコのマナー(19.3%)」「ペットの飼育やマナー(14.8%)」となったそうです。
特に密集率の高いマンションやアパート住まいでは、ご近所との騒音トラブルが最も多く寄せられる相談だそう。騒音トラブルは生活上付きものと考えたほうがよさそうです。
男女ともに1位は「騒音」でしたが、顕著に差が出たのは「車や駐車場の使い方(男性/28.4%、女性/14.7%)」と「バルコニーなど共有部での植物の育て方(男性/1.5%、女性/8.8%)」。それぞれがよく使う場所であるために気になるのではないかということです。
年齢別では、20代が不満に感じること第1位が「挨拶(54.5%)」となっており、全年齢平均から飛び抜けて高くなったそうです。第2位が「騒音(45.4%)」、第3位に「タバコのマナー(36.4%)」が挙がっています。30代においては、全年齢平均で見て顕著なのは「タバコを除く異臭(17.1%)」で、これは全年齢で見て倍の数値になったそう。40代は「騒音(52.5%)」が最も多く、50代は「騒音(35.7%)」に並び「挨拶(35.7%)」が不満点第1位タイとなりました。
20代と50代、共通して「挨拶」が不満第1位というのはおもしろいですね。挨拶しても無視されるorイヤな顔をされる、挨拶が面倒だ、顔を見られたくない……など理由はさまざまにありそうです。
そのため家を契約する前にまず、周囲に騒音トラブルがあるか、またはそれにつながりかねない懸念材料がないかをチェックしておきましょう。
建物は音が響きにくい構造か(一般的に木造は一番音が響きやすく、鉄筋は比較的響きにくい)、玄関やベランダの扉を開ける音が気にならないか、床材にはクッション機能があるか、騒音対策がなされているかなど。ゴミ置き場やエレベーター、駐車場といった共用部もまた、マンションの住民のマナーや管理体制をチェックする重要なポイントです。また日中よりも、住民の在宅率が高い時間帯である夜のほうが、実態に近い調査をすることができます。
住民向けの掲示板も見ておくといいでしょう。「苦情が出ています」などの注意書きや警告があるところは、すでに何かしらのトラブルが発生している可能性があります。そもそも壁の薄い割安物件や子育て世代向けの住宅、ペット可物件の場合、泣き声などの騒音は当然のようにあると考えたほうがいいかもいしれません。
ちなみに筆者の知人はいずれ子育てをする場合を考え、子育て支援サービスが充実した「子育て応援マンション」を選んだそうです。(「埼玉県子育て応援マンション認定制度」https://www.pref.saitama.lg.jp/a1107/kosodate-ouen-manshon/index.html#meritto)
不安な場合は、内見の時に担当者に聞くか、直接不動産業者やオーナーに問い合わせてOK。質問・確認することで、トラブルに対してどの程度の配慮がなされているのかがわかりますし、オーナー側にとっても「騒音に配慮してくれる入居者だ」と感じられます。
とはいえ、赤ちゃんの泣き声のように「どうにもならないこと」には多少、目をつぶるくらいの心の余裕は必要かもしれません。また自分は気にならないことでも、他人にとって迷惑・不快なことはたくさんあります。もしもクレームを受けたら相手の言い分はしっかり受け止め、改善するようにしましょう。こちらに事情があるように、相手にも事情があるものです。
もしもトラブルに悩んだら、まずは管理会社に連絡しましょう。注意しようとして怒鳴り込むのは逆効果です。どうしても解決しない、自分の手に負えない場合は、行政や警察に頼るのも手。大ごとにしたくない気持ちもあるでしょうが、抱え込んで我慢していては、家で休む意味がなくなってしまいます。
さきほど不満点として挙げられていた「挨拶」ですが、普段から挨拶を交わす程度のコミュニケーションは取った方が、双方気持ち良く過ごせることに違いありません。声かけしやすくなれば災害時の避難救助や、防犯という面からもメリットがあります。
ご近所同士、お互いのプライベートに配慮しながら、居心地良く生活したいものですね。
実際にはどのようなご近所トラブルが多いのでしょうか。ご近所トラブルランキングと、実際にトラブルに遭った場合の対処法や、未然に防ぐための予防法などをご紹介します。
ご近所トラブル、第1位は「騒音」
国土交通省の調査(平成30年度)によると、居住者間のマナーをめぐるトラブルでもっとも多かったのが「生活音」の38.0%。次に「違法駐車・駐輪」が28.1%、「ペット飼育」18.1%という結果となったそうです。また少し前の調査となりますが、不動産検索サイトSUUMOによる2015年の調査でも、ご近所トラブルで1位は「騒音(45.9%)」。次いで「挨拶(25.9%)」「車や駐車場の使い方(21.5%)」「タバコのマナー(19.3%)」「ペットの飼育やマナー(14.8%)」となったそうです。
特に密集率の高いマンションやアパート住まいでは、ご近所との騒音トラブルが最も多く寄せられる相談だそう。騒音トラブルは生活上付きものと考えたほうがよさそうです。
男女別・年齢別によって、不満に感じる点に差も
SUUMOの調査によると、性別や年齢によって不満に感じるポイントが違うようです。男女ともに1位は「騒音」でしたが、顕著に差が出たのは「車や駐車場の使い方(男性/28.4%、女性/14.7%)」と「バルコニーなど共有部での植物の育て方(男性/1.5%、女性/8.8%)」。それぞれがよく使う場所であるために気になるのではないかということです。
年齢別では、20代が不満に感じること第1位が「挨拶(54.5%)」となっており、全年齢平均から飛び抜けて高くなったそうです。第2位が「騒音(45.4%)」、第3位に「タバコのマナー(36.4%)」が挙がっています。30代においては、全年齢平均で見て顕著なのは「タバコを除く異臭(17.1%)」で、これは全年齢で見て倍の数値になったそう。40代は「騒音(52.5%)」が最も多く、50代は「騒音(35.7%)」に並び「挨拶(35.7%)」が不満点第1位タイとなりました。
20代と50代、共通して「挨拶」が不満第1位というのはおもしろいですね。挨拶しても無視されるorイヤな顔をされる、挨拶が面倒だ、顔を見られたくない……など理由はさまざまにありそうです。
騒音について契約前に判断する方法は?
快適に毎日を過ごすためにも、トラブルは未然に防ぎたいですよね。特に生活音に関しては、個人で気になるレベルが違うため、意識のズレからトラブルになりやすいもの。もっとも多いトラブルなのに、対処の仕方が難しい案件でもあるのです。最悪、どうにもならずすぐに引っ越しをするハメになったり、訴訟問題にまで発展したりするケースも少なくありません。そのため家を契約する前にまず、周囲に騒音トラブルがあるか、またはそれにつながりかねない懸念材料がないかをチェックしておきましょう。
建物は音が響きにくい構造か(一般的に木造は一番音が響きやすく、鉄筋は比較的響きにくい)、玄関やベランダの扉を開ける音が気にならないか、床材にはクッション機能があるか、騒音対策がなされているかなど。ゴミ置き場やエレベーター、駐車場といった共用部もまた、マンションの住民のマナーや管理体制をチェックする重要なポイントです。また日中よりも、住民の在宅率が高い時間帯である夜のほうが、実態に近い調査をすることができます。
住民向けの掲示板も見ておくといいでしょう。「苦情が出ています」などの注意書きや警告があるところは、すでに何かしらのトラブルが発生している可能性があります。そもそも壁の薄い割安物件や子育て世代向けの住宅、ペット可物件の場合、泣き声などの騒音は当然のようにあると考えたほうがいいかもいしれません。
ちなみに筆者の知人はいずれ子育てをする場合を考え、子育て支援サービスが充実した「子育て応援マンション」を選んだそうです。(「埼玉県子育て応援マンション認定制度」https://www.pref.saitama.lg.jp/a1107/kosodate-ouen-manshon/index.html#meritto)
不安な場合は、内見の時に担当者に聞くか、直接不動産業者やオーナーに問い合わせてOK。質問・確認することで、トラブルに対してどの程度の配慮がなされているのかがわかりますし、オーナー側にとっても「騒音に配慮してくれる入居者だ」と感じられます。
ご近所トラブルに巻きこまれないために
お互い快適に過ごすためにも、入居時のルールを遵守することはもちろん、洗濯や掃除など音の出る行為は日中に済ます、深夜に大声を出さない、共用部を汚さない、ペットのしつけをしっかり行うなど、「自分がされたら困ること」を常に念頭に置いて行動しましょう。それだけでもトラブルを回避することは十分可能です。とはいえ、赤ちゃんの泣き声のように「どうにもならないこと」には多少、目をつぶるくらいの心の余裕は必要かもしれません。また自分は気にならないことでも、他人にとって迷惑・不快なことはたくさんあります。もしもクレームを受けたら相手の言い分はしっかり受け止め、改善するようにしましょう。こちらに事情があるように、相手にも事情があるものです。
もしもトラブルに悩んだら、まずは管理会社に連絡しましょう。注意しようとして怒鳴り込むのは逆効果です。どうしても解決しない、自分の手に負えない場合は、行政や警察に頼るのも手。大ごとにしたくない気持ちもあるでしょうが、抱え込んで我慢していては、家で休む意味がなくなってしまいます。
さきほど不満点として挙げられていた「挨拶」ですが、普段から挨拶を交わす程度のコミュニケーションは取った方が、双方気持ち良く過ごせることに違いありません。声かけしやすくなれば災害時の避難救助や、防犯という面からもメリットがあります。
ご近所同士、お互いのプライベートに配慮しながら、居心地良く生活したいものですね。
<参考サイト>
・近隣トラブル、悩まされていること1位は……?(SUUMOジャーナル)
https://suumo.jp/journal/2015/09/16/97532/
・管理のプロに聞く、マンションの「居住者トラブル」とその回避法(SUUMOジャーナル)
https://suumo.jp/journal/2015/09/09/97109/
・ご近所トラブル1位は「騒音」…契約前に確認する方法は?【専門家に聞く】
https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00384/
・マンションに関する統計・データ等(国土交通省)
「平成 30 年度マンション総合調査結果からみたマンション居住と管理の現状」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000058.html
・近隣トラブル、悩まされていること1位は……?(SUUMOジャーナル)
https://suumo.jp/journal/2015/09/16/97532/
・管理のプロに聞く、マンションの「居住者トラブル」とその回避法(SUUMOジャーナル)
https://suumo.jp/journal/2015/09/09/97109/
・ご近所トラブル1位は「騒音」…契約前に確認する方法は?【専門家に聞く】
https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00384/
・マンションに関する統計・データ等(国土交通省)
「平成 30 年度マンション総合調査結果からみたマンション居住と管理の現状」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000058.html
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










