テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
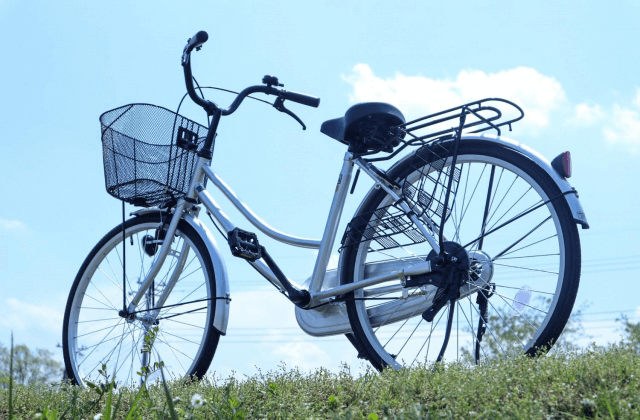
「自転車」を「チャリンコ」と呼ぶ理由
自転車のことを「チャリンコ」「チャリ」などと呼ぶことがありますが、そもそもなぜそう呼ぶのかご存じでしょうか。今回は「チャリンコ」の由来やそのほかの呼び方、あわせて自転車の歴史についても解説します!
【説その1】自転車のベル説
「チャリンチャリン」という自転車のベル音から呼ばれるようになった。
【説その2】韓国語「チャジョンゴ」説
韓国語で自転車は「チャジョンゴ」。それが日本に伝わり、音が変化して「チャリンコ」となった。
【説その3】「子どものスリ」説
終戦直後、スリや食い逃げなど悪さをする子どものことを「ジャリンコ」「チャリンコ」と呼んでおり、それがいつの間にか自転車を指すようになった。
筆者はてっきりベル音が由来と思っていたので、【説その2】【説その3】には驚きです。いずれもどのように自転車の呼称として定着したのかが不明なため、説としてはやや飛躍しているように思えるのですが、もしかしたらベルの「チャリン」という音と、もともと言葉としてあった「チャリンコ」や「チャジョンゴ」と結びついた可能性もありそうです。
なお、自転車が「チャリンコ」と呼ばれるようになった時期は1962年(昭和37年)から1963年(昭和38年)ごろで、東京の下町で使われていたことが分かっているそう。また別の考察記事では、石ノ森章太郎氏の『がんばれ!! ロボコン』という作品で「チャリンコ」という言葉が頻出したことから、徐々に一般へ定着していったという説を挙げています。
その約40年後の1861年になると、前輪にペダルのついた鉄製の自転車(ミショー型ボーンシェーカー)が登場。乗り心地は今ひとつなものの速く走れるようになり、自転車レースも始まりました。1880年頃にはより早く走れるよう前輪が極端に大きくなった「オーディナリー」と呼ばれる自転車が生まれました。
徐々に自転車の生産が増え、多くの人が自転車に乗るようになると、安全性を考えた自転車が求められるようになります。1879年には、ペダルから繋がるチェーンにより後輪が回る「ビシクレット」という仕組みを取り入れた自転車が開発されました。この「ビシクレット」が「バイシクル」の語源です。そして1885年に、前輪と後輪の大きさが同じ「ローバー」が誕生。これが現在の自転車の原型となったのです。
いっぽう日本では、文明開化したばかりの1872年(明治3年)の錦絵『東京日本橋繁栄之図(芳虎画)』に三輪車に乗っている外国人らしき男の絵が描かれており、これが二輪車・三輪車が描かれた最初の絵だといわれています。
同じ年、竹内虎次郎という者が自転車製造・販売の許可願書を東京府に提出しており、それが「自転車」という名称の初出と考えられています。当時自転車は二輪、三輪、四輪までありましたが、やがて二輪のみの自転車が普及したことにともない「二輪=自転車」という呼称が定着していったのです。
今や安全面だけでなく、電動アシストなど機能も充実、より個性的な乗り物となった自転車。昨今では自転車通勤をする人も増えてきたようです。今後自転車がどのように進化していくのか、楽しみですね!
3つの説がある「チャリンコ」の由来
株式会社メディア・ヴァーグが運営する『乗りものニュース』の記事には、自転車文化センターの学芸員の方へのインタビュー取材が掲載されています。それによると、自転車が「チャリンコ」と呼ばれるようになった理由にはいくつかの説が挙げられるとしています。【説その1】自転車のベル説
「チャリンチャリン」という自転車のベル音から呼ばれるようになった。
【説その2】韓国語「チャジョンゴ」説
韓国語で自転車は「チャジョンゴ」。それが日本に伝わり、音が変化して「チャリンコ」となった。
【説その3】「子どものスリ」説
終戦直後、スリや食い逃げなど悪さをする子どものことを「ジャリンコ」「チャリンコ」と呼んでおり、それがいつの間にか自転車を指すようになった。
筆者はてっきりベル音が由来と思っていたので、【説その2】【説その3】には驚きです。いずれもどのように自転車の呼称として定着したのかが不明なため、説としてはやや飛躍しているように思えるのですが、もしかしたらベルの「チャリン」という音と、もともと言葉としてあった「チャリンコ」や「チャジョンゴ」と結びついた可能性もありそうです。
なお、自転車が「チャリンコ」と呼ばれるようになった時期は1962年(昭和37年)から1963年(昭和38年)ごろで、東京の下町で使われていたことが分かっているそう。また別の考察記事では、石ノ森章太郎氏の『がんばれ!! ロボコン』という作品で「チャリンコ」という言葉が頻出したことから、徐々に一般へ定着していったという説を挙げています。
名古屋では「ケッタマシーン」という俗称も
「チャリンコ」のほかにも自転車の俗称として独特の呼び方をしている地域があります。それが名古屋地方で、自転車のことを「ケッタマシーン」または「ケッタクリマシーン」、「ケッタ」などと呼ぶそうです。これはペダルに片足を乗せ、もう片足で地面を蹴って(ケッテ)から乗るスタイルにちなんでいるとされています。今だと「?」と感じる動作かもしれませんが、昔は自転車が重く、またがる前に地面を蹴って助走をつけ、車体を安定させてからでないとうまく乗れなかったのです。「自転車」はどのように進化した?
自転車が誕生したのは1818年のドイツ。タイプライターの発明者でもあるドライス男爵によって発明されました。当時の自転車は木製でペダルがなく、地面を蹴って前後の2つの車輪を動かして走行しました。貴族階級を中心に、遊びとして流行したようです。その約40年後の1861年になると、前輪にペダルのついた鉄製の自転車(ミショー型ボーンシェーカー)が登場。乗り心地は今ひとつなものの速く走れるようになり、自転車レースも始まりました。1880年頃にはより早く走れるよう前輪が極端に大きくなった「オーディナリー」と呼ばれる自転車が生まれました。
徐々に自転車の生産が増え、多くの人が自転車に乗るようになると、安全性を考えた自転車が求められるようになります。1879年には、ペダルから繋がるチェーンにより後輪が回る「ビシクレット」という仕組みを取り入れた自転車が開発されました。この「ビシクレット」が「バイシクル」の語源です。そして1885年に、前輪と後輪の大きさが同じ「ローバー」が誕生。これが現在の自転車の原型となったのです。
いっぽう日本では、文明開化したばかりの1872年(明治3年)の錦絵『東京日本橋繁栄之図(芳虎画)』に三輪車に乗っている外国人らしき男の絵が描かれており、これが二輪車・三輪車が描かれた最初の絵だといわれています。
同じ年、竹内虎次郎という者が自転車製造・販売の許可願書を東京府に提出しており、それが「自転車」という名称の初出と考えられています。当時自転車は二輪、三輪、四輪までありましたが、やがて二輪のみの自転車が普及したことにともない「二輪=自転車」という呼称が定着していったのです。
今や安全面だけでなく、電動アシストなど機能も充実、より個性的な乗り物となった自転車。昨今では自転車通勤をする人も増えてきたようです。今後自転車がどのように進化していくのか、楽しみですね!
<参考サイト>
・チャリンコ=自転車のナゾ 戦後広まった俗称、それ以前は?(乗りものニュース)
https://trafficnews.jp/post/79583
・自転車が「チャリンコ」と呼ばれるようになった理由は?(ニッポン放送「NEWS ONLINE」)
https://news.1242.com/article/143125
・自転車まめ知識 自転車の歴史(自転車博物館)
http://www.bikemuse.jp/knowledge/
・自転車文化センターHP
http://cycle-info.bpaj.or.jp
・チャリンコ=自転車のナゾ 戦後広まった俗称、それ以前は?(乗りものニュース)
https://trafficnews.jp/post/79583
・自転車が「チャリンコ」と呼ばれるようになった理由は?(ニッポン放送「NEWS ONLINE」)
https://news.1242.com/article/143125
・自転車まめ知識 自転車の歴史(自転車博物館)
http://www.bikemuse.jp/knowledge/
・自転車文化センターHP
http://cycle-info.bpaj.or.jp
人気の講義ランキングTOP20
適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物
長谷川眞理子










