テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
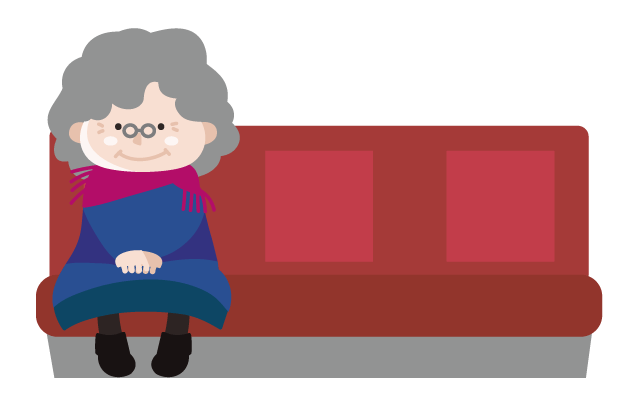
日本人が端の座席を好む理由
心理学者の渋谷昌三氏は、『人と人との快適距離』の中で「昼間のガラ空きの車両」の風景を、以下のように紹介しています。
「昼間のガラ空きの車両に乗り込んだとき、あちこち空いているにもかかわらず、それが習性であるかのように、他の乗客からできるだけ離れた隅空間を見つけて座ろうとする。これはできるだけ長い時間、できたら電車にのっている間中、自分の“パーソナル・スペース”に他人が入ってこないような場所を選ぼうとする行動であろう」
なお、「パーソナル・スペース」とは、「個人が心理的安心感を得る他者との距離」を指します。
(1)身を守るためには端の座席のほうが有利であり、安心できる。体の一部を壁に近づけることで外敵から身を守りやすくなるだけでなく、中間の座席では両側に気遣う必要がある(多少なりとも左右に緊張を強いられる)が、端の座席では片側だけでも気遣う必要がなくなる(片側の緊張は強いられない)。つまり、端の座席は中間の座席に比較して居心地がよく、安心できる場所といえる。
(2)着席行動は、空間への“期待”や“予期”が大きな役割を果たしている。たとえば、座席を選ぶ際に座席全体が空いていても、混雑した事態を想定して端の座席に座ることで、混雑した場合でも他者との干渉を少しでも(片側だけでも)防ぐことが可能になる。つまり、端の座席は他者と関わりを持たなくてすむ可能性が高い、戦略的に好ましい場所といえる。
以上より、「端の座席が好まれる理由」は、(1)“端の座席は安心できる場所”に加え、(2)“端の座席は戦略的に好ましい場所”――であると考えられます。
そして、日本人は端や境界を気にしてきちんと押さえておかなければならないという意識が強く、そこから「○○の端くれ」といった謙譲語が生まれ、「はしたない」という感覚が育まれ、さらには一様に「端の座席が落ち着く」ようになったのではないかと述べています。
大森氏の仮説は、空間行動の一般的法則として端の座席を好む以上に、「日本人が端の座席を好む理由」として興味深い仮説の一つといえます。
いかがでしたでしょうか。日常風景にも、多様な理由や行動背景が潜んでいます。ちょっと気になった際には、ぜひ理由を探してみてください。
「昼間のガラ空きの車両に乗り込んだとき、あちこち空いているにもかかわらず、それが習性であるかのように、他の乗客からできるだけ離れた隅空間を見つけて座ろうとする。これはできるだけ長い時間、できたら電車にのっている間中、自分の“パーソナル・スペース”に他人が入ってこないような場所を選ぼうとする行動であろう」
なお、「パーソナル・スペース」とは、「個人が心理的安心感を得る他者との距離」を指します。
心理学的視点・「安心」と「戦略」の空間行動
また、心理学者の小西啓史氏は、端の座席が好まれる背景を「空間行動の一般的法則」としたうえで、さらに「端の座席が好まれる理由」として、以下の2点を挙げています。(1)身を守るためには端の座席のほうが有利であり、安心できる。体の一部を壁に近づけることで外敵から身を守りやすくなるだけでなく、中間の座席では両側に気遣う必要がある(多少なりとも左右に緊張を強いられる)が、端の座席では片側だけでも気遣う必要がなくなる(片側の緊張は強いられない)。つまり、端の座席は中間の座席に比較して居心地がよく、安心できる場所といえる。
(2)着席行動は、空間への“期待”や“予期”が大きな役割を果たしている。たとえば、座席を選ぶ際に座席全体が空いていても、混雑した事態を想定して端の座席に座ることで、混雑した場合でも他者との干渉を少しでも(片側だけでも)防ぐことが可能になる。つまり、端の座席は他者と関わりを持たなくてすむ可能性が高い、戦略的に好ましい場所といえる。
以上より、「端の座席が好まれる理由」は、(1)“端の座席は安心できる場所”に加え、(2)“端の座席は戦略的に好ましい場所”――であると考えられます。
民俗学的視点・「端に控える」という感覚
他方、古代民俗研究所代表の大森亮尚氏は、『知ってるようで知らない日本人の謎20』の中で「日本人が端の座席を好む理由」を民俗学的視点から考察し、「端に控える日本人のたしなみ」からの行動であるのではないかと述べています。そして、日本人は端や境界を気にしてきちんと押さえておかなければならないという意識が強く、そこから「○○の端くれ」といった謙譲語が生まれ、「はしたない」という感覚が育まれ、さらには一様に「端の座席が落ち着く」ようになったのではないかと述べています。
大森氏の仮説は、空間行動の一般的法則として端の座席を好む以上に、「日本人が端の座席を好む理由」として興味深い仮説の一つといえます。
いかがでしたでしょうか。日常風景にも、多様な理由や行動背景が潜んでいます。ちょっと気になった際には、ぜひ理由を探してみてください。
<参考文献・参考サイト>
・『人と人との快適距離』(渋谷昌三著、日本放送出版協会)
・『知ってるようで知らない日本人の謎20』(大森亮尚著、PHP研究所)
・「パーソナル・スペース」『イミダス2018』(松田英子著、集英社)
・喫茶店やレストランで壁際の席からうまっていくのはなぜ? | 日本心理学会
https://psych.or.jp/interest/ff-16/
・『人と人との快適距離』(渋谷昌三著、日本放送出版協会)
・『知ってるようで知らない日本人の謎20』(大森亮尚著、PHP研究所)
・「パーソナル・スペース」『イミダス2018』(松田英子著、集英社)
・喫茶店やレストランで壁際の席からうまっていくのはなぜ? | 日本心理学会
https://psych.or.jp/interest/ff-16/
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










