テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
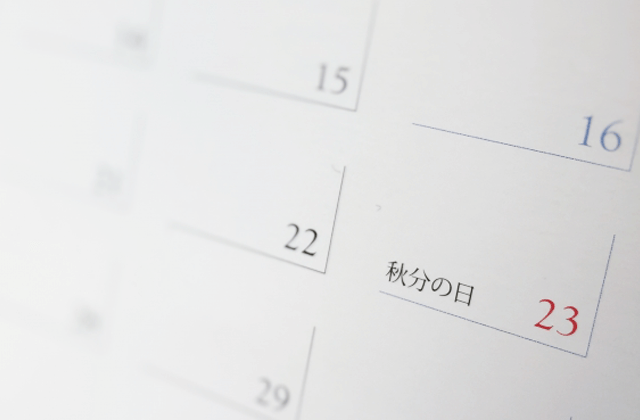
土曜日の祝日はなぜ振替休日がないのか
土日と祝日が重なっている!じゃあ次の週末は3連休だ!!……とワクワクしていたら、祝日が土曜日と重なっていると気づいてぬか喜び……なんて経験、ありますよね。土曜は振替休日にならないと知っていても、やっぱりつい勘違いしちゃいませんか。筆者はそうです。
土曜日と祝日が重なっても振替休日にならないのはなぜでしょうか。調べてみました。
“「国民の祝日」は、休日とする。(第3条)”
祝日=休日と、法律できちんと定められているのですね。
同じく第3条には、以下のように振替休日についての規定があります。
“「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。(第3条2項)”
しかし、条文に記載されているのは上記の通り「日曜日」だけで、土曜日については触れられていません。つまり土曜日は、ごく普通の平日ということになります。これが土曜日の祝日が振替休日にならない理由です。
そもそもこの祝日法が制定された当初、振替休日というものはありませんでした。振替休日が導入されたのは、1973年の法改正の時。このころ、学校も会社も、休日といえば日曜日のみの週休1日制がほとんどだったため、必然的に日曜日のみ振替休日にできる日となったのです。
1980年ごろから徐々に週休2日制が浸透し始め、現在は土日とも休みとなっているところが多いですが、この法律の規定そのものは変わっていないので現行通りとなっています。
先ほどの祝日法の第2条には、「国民の祝日」とは1月1日の元日から11月23日の勤労感謝の日までの全16日(2022年3月現在)で、その日は休日である、と定めています。そしてその意義は、こうあります。
“自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。(第1条)”
どうしても私たち現代人は忙しさにかまけて祝日の意味を忘れがちですが、ここで改めて祝日の意義を振り返ってもいいかもしれませんね。振替休日だけに……(?)
実はこの祝日法、民間企業に対して労働者への休日付与義務を課すものではなく、強制力はありません。休日については「労働者には毎週1日、または4週4日の休日を与えること」と労働基準法(労基法)で定められていて、休日をどこにするか、また祝日に休業するか否かは各企業の判断に委ねられているのです。つまり労基法に則っていさえすれば、祝日に労働すること(させること)自体は問題ないということ。業界によっては休日、祝日こそ稼ぎ時だという場合もありますし、そこは柔軟であるべきだという考えなのでしょう。
このように、基本的には労基法の規定内であれば休日をどこにするかは自由に決めることができますが、特定の業界では法律で休日が定められている場合があります。たとえば公務員(国の行政機関、地方自治体、学校)はそれぞれの法規定によって土日が休日と定められ、銀行は『銀行法』という法律から日曜が休日と定められています。
いかがでしたか。週休2日制が浸透している現代においても、未だに法律上の土曜日が休日に当たらないのは少々残念ではありますが、企業が自由に休日を設定できるからこそ、今の便利な世の中が成り立っているとも言えますね。
土曜日と祝日が重なっても振替休日にならないのはなぜでしょうか。調べてみました。
なぜ土曜の祝日は振替休日にならないのか
日本の祝日や休日については『国民の祝日に関する法律(祝日法)』という法律があり、その第3条に、こうあります。“「国民の祝日」は、休日とする。(第3条)”
祝日=休日と、法律できちんと定められているのですね。
同じく第3条には、以下のように振替休日についての規定があります。
“「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。(第3条2項)”
しかし、条文に記載されているのは上記の通り「日曜日」だけで、土曜日については触れられていません。つまり土曜日は、ごく普通の平日ということになります。これが土曜日の祝日が振替休日にならない理由です。
そもそもこの祝日法が制定された当初、振替休日というものはありませんでした。振替休日が導入されたのは、1973年の法改正の時。このころ、学校も会社も、休日といえば日曜日のみの週休1日制がほとんどだったため、必然的に日曜日のみ振替休日にできる日となったのです。
1980年ごろから徐々に週休2日制が浸透し始め、現在は土日とも休みとなっているところが多いですが、この法律の規定そのものは変わっていないので現行通りとなっています。
祝日の定義とは?
ではそもそも、祝日の定義とは何なのでしょうか。先ほどの祝日法の第2条には、「国民の祝日」とは1月1日の元日から11月23日の勤労感謝の日までの全16日(2022年3月現在)で、その日は休日である、と定めています。そしてその意義は、こうあります。
“自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。(第1条)”
どうしても私たち現代人は忙しさにかまけて祝日の意味を忘れがちですが、ここで改めて祝日の意義を振り返ってもいいかもしれませんね。振替休日だけに……(?)
企業によっては「休日=休業」にならない理由
ここでひとつ疑問が浮かびます。上記の通り、祝日法で「祝日は休日である」と定められているのに、企業によっては祝日でも休日にならず、出勤日となる場合がありますよね。休日なのに休めないなんて、実は法律違反じゃないかなと思われる人も多いのではないでしょうか。実はこの祝日法、民間企業に対して労働者への休日付与義務を課すものではなく、強制力はありません。休日については「労働者には毎週1日、または4週4日の休日を与えること」と労働基準法(労基法)で定められていて、休日をどこにするか、また祝日に休業するか否かは各企業の判断に委ねられているのです。つまり労基法に則っていさえすれば、祝日に労働すること(させること)自体は問題ないということ。業界によっては休日、祝日こそ稼ぎ時だという場合もありますし、そこは柔軟であるべきだという考えなのでしょう。
このように、基本的には労基法の規定内であれば休日をどこにするかは自由に決めることができますが、特定の業界では法律で休日が定められている場合があります。たとえば公務員(国の行政機関、地方自治体、学校)はそれぞれの法規定によって土日が休日と定められ、銀行は『銀行法』という法律から日曜が休日と定められています。
いかがでしたか。週休2日制が浸透している現代においても、未だに法律上の土曜日が休日に当たらないのは少々残念ではありますが、企業が自由に休日を設定できるからこそ、今の便利な世の中が成り立っているとも言えますね。
<参考サイト>
・国民の祝日に関する法律(e-Gov)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000178_20200101_430AC0000000057
・国民の祝日に社員を休ませる必要はあるか(ロア・ユナイテッド法律事務所)
https://www.loi.gr.jp/law/syokuba-40/
・法律で「休日とする」とされた日(参議院法制局)
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column086.htm
・国民の祝日に関する法律(e-Gov)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000178_20200101_430AC0000000057
・国民の祝日に社員を休ませる必要はあるか(ロア・ユナイテッド法律事務所)
https://www.loi.gr.jp/law/syokuba-40/
・法律で「休日とする」とされた日(参議院法制局)
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column086.htm
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










