テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
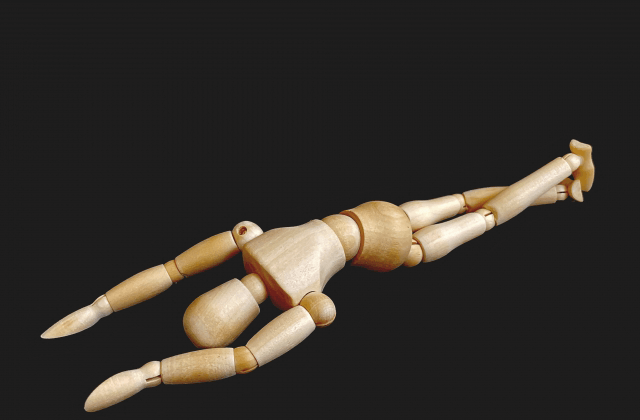
なぜ「死んだふり」をする?『生き物たちの奇妙な戦略』
実は、地球上にはたくさんの「死んだふり」をする生き物がいます。クマを目の前にしたウサギがその場でコロリ。蛇ににらまれたカエルがフリーズ。こうした動物たちの「死んだふり」は、捕食者から逃れるための術と考えられています。わたしたち人間にも、「山でクマに出会ったら死んだふりをするといい」などという俗説を、誰しも一度は耳にしたことがあるはずです(実際にクマ相手に死んだふりは危険だそうです)。
しかし、本当に「死んだふり」は「捕食者から逃れるため」だけに行われるのでしょうか。また、どんな理由があって生き物は「死んだふり」を手に入れたのでしょうか。
そんな「死んだふり」についての研究をまとめたのが、岡山大学学術研究院環境生命科学学域教授である宮竹貴久先生の著書『「死んだふり」で生きのびる: 生き物たちの奇妙な戦略』 (岩波科学ライブラリー)です。
しかし、この「死んだふり」は捕食者側にも観られる行動で、ときには「狩る・狩られる」といった状況でないときにも発動します。たとえば、トンボのメスは交尾を回避するために「死んだふり」をして水中に落下し、ミツバチのメスは、女王バチが死んだ際に、オスからの攻撃を回避するため「死んだふり」をして身を守るのです。
このように、生き物が「死んだふり」をする理由はさまざまで、一口に「死んだふり」といっても、それぞれの特性において異なる利点があります。しかし、そこは意外と奥が深いかもしれないと思っても、1つの研究テーマになり得るものなのか。宮竹先生は、「果たして死んだふりが科学になるのか?」という地点から研究をスタートしたのです。
「失望とともに、僕はある確信を得た。死んだふりが生きのびる上で役に立っているのかは、世界の誰もわかっていない謎なのだ。世界の誰もやっていないなら、自分がやろう」と。
地球上の生物の多くが「死んだふり」をする。しかし、その謎は「捕食者から逃れるためだろう」という憶測の段階でストップしていたのです。宮竹先生は、この一見地味なテーマを“科学”として確立させることに魂を燃やしていきます。
研究の過程のなかで、先生は「死んだふり」について新事実を次々と発見して行きます。たとえば「死んだふり」をするにも、ベストなコンディションがあり、苛酷な状況下やより優先される本能が働いているときは「死んだふり」ができないこと。捕食者を相手にした場合、捕食者の意識を他の生物に向けるため「死んだふり」は有効であること。一種の甲虫でも、長時間死んだふりをする系統と、短い系統があり、その違いは体内物質にまで影響があることなど、その内容は多岐に渡ります。
そうしてさまざまな視点から研究を進めるなか、周囲の科学の進歩も目覚ましく、「死んだふり」の長さの違いをゲノムレベルで解析するという領域に到達するのです。さらに驚くべきことに、「死んだふり」の時間が長い系統には、ドーパミンが少ないことがわかり、そこにパーキンソン病とのつながりを見いだしていきます。
「25年ものあいだ死んだふりの研究を続けていると、実際に人間の行動や医療の発展につながるかもしれないというところまで、死んだふりの研究は来た。(中略)なぜ飽きもせず続けられたのか? それは僕が本当に面白がって死んだふりの研究に取り組んできたからだと今になって思う」
本書を読んでいると、生物の生態に対する興味がわくと同時に、子どものころ採取した昆虫を観察していたときのような、一途な好奇心がよみがえってくるのです。「なぜ?」「どうして?」と感じていたおさなごころが、大人になるにつれて薄れていき、そうした興味さえ示さなくなることは人生には多々ありますが、その小さな「なぜ?」を突き詰めていくことの尊さを本書から感じ取ることができるのです。
現在も「死んだふり」の研究は続いています。もしかすると、「“死んだふり”の研究から新薬開発へ!」といった見だしが新聞やネットに躍る日が来るのかもしれません。本書を読んで、謎だらけの「死んだふり」の世界へ、みなさんも足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。
しかし、本当に「死んだふり」は「捕食者から逃れるため」だけに行われるのでしょうか。また、どんな理由があって生き物は「死んだふり」を手に入れたのでしょうか。
そんな「死んだふり」についての研究をまとめたのが、岡山大学学術研究院環境生命科学学域教授である宮竹貴久先生の著書『「死んだふり」で生きのびる: 生き物たちの奇妙な戦略』 (岩波科学ライブラリー)です。
「死んだふり」は本当に科学になるのか
実は「死んだふり」には「捕食者から逃れるため」とは違う理由があるのですが、生きのびるため「捕食者から逃れる」という認識も間違っているわけではありません。実際、進化論で有名なダーウィン、昆虫の研究で知られるファーブルといった、誰もが知る研究者たちも、「死んだふり」は生存のための行動と考えていました。しかし、この「死んだふり」は捕食者側にも観られる行動で、ときには「狩る・狩られる」といった状況でないときにも発動します。たとえば、トンボのメスは交尾を回避するために「死んだふり」をして水中に落下し、ミツバチのメスは、女王バチが死んだ際に、オスからの攻撃を回避するため「死んだふり」をして身を守るのです。
このように、生き物が「死んだふり」をする理由はさまざまで、一口に「死んだふり」といっても、それぞれの特性において異なる利点があります。しかし、そこは意外と奥が深いかもしれないと思っても、1つの研究テーマになり得るものなのか。宮竹先生は、「果たして死んだふりが科学になるのか?」という地点から研究をスタートしたのです。
世界で誰も知らない「死んだふり」の理由
本書は研究書であると同時に、宮竹先生の研究エッセイ的なエッセンスがふんだんに盛り込まれています。ふつう「死んだふりの研究」と聞いたときに、多くの人は「どんなことをするのだろう?」と疑問に思うでしょう。実際、宮竹先生は研究をはじめる前に、「死んだふり」についてどんな文献があるのかを調べたそうです。ところが、結果は芳しくなく、先人のいない研究分野であることがわかりました。この結果に失望したと言います。しかし、そこで先生は「なんだ」と諦めてしまうのではなく、こう思いました。「失望とともに、僕はある確信を得た。死んだふりが生きのびる上で役に立っているのかは、世界の誰もわかっていない謎なのだ。世界の誰もやっていないなら、自分がやろう」と。
地球上の生物の多くが「死んだふり」をする。しかし、その謎は「捕食者から逃れるためだろう」という憶測の段階でストップしていたのです。宮竹先生は、この一見地味なテーマを“科学”として確立させることに魂を燃やしていきます。
小さな甲虫の生態が不治の病の原因究明につながるかも
宮竹先生は、さまざまな昆虫を使って「死んだふり」の研究を進めていきます。どんなときに「死んだふり」をするのか、「死んだふり」の5W1Hを調べ、大量の甲虫を飼育し、交配させ、「死んだふり」が長くできる系統と、短い系統に分けるなど、地道な調査・研究を続けていきます。その研究期間は実に25年!研究の過程のなかで、先生は「死んだふり」について新事実を次々と発見して行きます。たとえば「死んだふり」をするにも、ベストなコンディションがあり、苛酷な状況下やより優先される本能が働いているときは「死んだふり」ができないこと。捕食者を相手にした場合、捕食者の意識を他の生物に向けるため「死んだふり」は有効であること。一種の甲虫でも、長時間死んだふりをする系統と、短い系統があり、その違いは体内物質にまで影響があることなど、その内容は多岐に渡ります。
そうしてさまざまな視点から研究を進めるなか、周囲の科学の進歩も目覚ましく、「死んだふり」の長さの違いをゲノムレベルで解析するという領域に到達するのです。さらに驚くべきことに、「死んだふり」の時間が長い系統には、ドーパミンが少ないことがわかり、そこにパーキンソン病とのつながりを見いだしていきます。
いつの日か画期的な成果が!?…これからも続く「死んだふり」の研究
本書のなかで宮竹先生はこう書いています。「25年ものあいだ死んだふりの研究を続けていると、実際に人間の行動や医療の発展につながるかもしれないというところまで、死んだふりの研究は来た。(中略)なぜ飽きもせず続けられたのか? それは僕が本当に面白がって死んだふりの研究に取り組んできたからだと今になって思う」
本書を読んでいると、生物の生態に対する興味がわくと同時に、子どものころ採取した昆虫を観察していたときのような、一途な好奇心がよみがえってくるのです。「なぜ?」「どうして?」と感じていたおさなごころが、大人になるにつれて薄れていき、そうした興味さえ示さなくなることは人生には多々ありますが、その小さな「なぜ?」を突き詰めていくことの尊さを本書から感じ取ることができるのです。
現在も「死んだふり」の研究は続いています。もしかすると、「“死んだふり”の研究から新薬開発へ!」といった見だしが新聞やネットに躍る日が来るのかもしれません。本書を読んで、謎だらけの「死んだふり」の世界へ、みなさんも足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。
<参考文献>
『「死んだふり」で生きのびる: 生き物たちの奇妙な戦略』 (宮竹貴久著、岩波科学ライブラリー)
https://www.iwanami.co.jp/book/b611101.html
<参考サイト>
宮竹貴久先生のホームページ
https://sites.google.com/view/miyatake/home
『「死んだふり」で生きのびる: 生き物たちの奇妙な戦略』 (宮竹貴久著、岩波科学ライブラリー)
https://www.iwanami.co.jp/book/b611101.html
<参考サイト>
宮竹貴久先生のホームページ
https://sites.google.com/view/miyatake/home
人気の講義ランキングTOP20










