テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
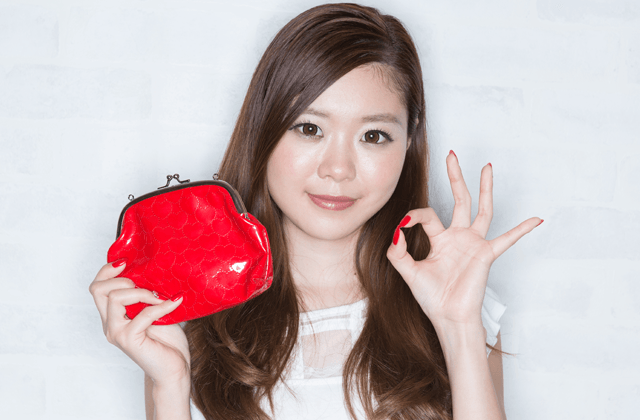
モノもサービスも「タダ」になる未来がやってくる?~「限界費用ゼロ社会」とは
信じられないかもしれないが、数十年後には、世界中で多くのモノやサービスがほぼタダになるという「予言」が、いま世界で注目を集めています。予言したのは、ジェレミー・リフキン氏。彼はそれを「限界費用ゼロ社会」と呼んでいます。
実は、すでに限界費用ゼロ社会は、現代にも一部、現れ始めています。たとえば、「Skype」は無料で電話やテレビ電話ができるサービスです。インターネットでは、ニュースなども無料で読むことができます。もちろん、どちらも現実的には通信費がかかっていますが、一時代前から考えれば、明らかにコストは下がっています。そして通信費はさらに安くなっていく。こうした進化や変化が、今後あらゆる分野で起こっていくというのです。
IoTとは「モノのインターネット」と訳されるもので、簡単に言うと、あらゆるモノにセンサーとソフトウェアが組み込まれ、インターネットと結びつく技術です。2030年には100兆個のセンサーがIoTにつながると予想されています。それによって、私たちは何でも「シェア」するようになるのです。
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、技術の発達によってどんどん安価になっていくと言われています。リフキン氏は、2040年よりはだいぶ前に再生可能エネルギーによる電力がほぼ8割に達するだろうと見ています。
3Dプリンターの進化も急速で、すでに部品のすべてを3Dプリンターで作った「建物」ができつつあり、3Dプリンターで「人間の臓器」を作るプロジェクトも順調に進んでいるといいます。3Dプリンターが発展すれば、それほど遠くないうちに、自宅や近所で、自ら多くのものを気軽に作れる時代が到来するでしょう。
MOOCは、大学の講義がどこでも無料で受けられる大規模公開オンライン講座です。いまやモチベーションさえあれば、レベルの高い教育をタダで受けられるようになりつつあるのです。
実は、すでに限界費用ゼロ社会は、現代にも一部、現れ始めています。たとえば、「Skype」は無料で電話やテレビ電話ができるサービスです。インターネットでは、ニュースなども無料で読むことができます。もちろん、どちらも現実的には通信費がかかっていますが、一時代前から考えれば、明らかにコストは下がっています。そして通信費はさらに安くなっていく。こうした進化や変化が、今後あらゆる分野で起こっていくというのです。
IoTや3Dプリンターが世界を変える
具体的には、限界費用ゼロ社会は「IoT」「再生可能エネルギー」「3Dプリンター」「MOOC」などによってもたらされます。IoTとは「モノのインターネット」と訳されるもので、簡単に言うと、あらゆるモノにセンサーとソフトウェアが組み込まれ、インターネットと結びつく技術です。2030年には100兆個のセンサーがIoTにつながると予想されています。それによって、私たちは何でも「シェア」するようになるのです。
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、技術の発達によってどんどん安価になっていくと言われています。リフキン氏は、2040年よりはだいぶ前に再生可能エネルギーによる電力がほぼ8割に達するだろうと見ています。
3Dプリンターの進化も急速で、すでに部品のすべてを3Dプリンターで作った「建物」ができつつあり、3Dプリンターで「人間の臓器」を作るプロジェクトも順調に進んでいるといいます。3Dプリンターが発展すれば、それほど遠くないうちに、自宅や近所で、自ら多くのものを気軽に作れる時代が到来するでしょう。
MOOCは、大学の講義がどこでも無料で受けられる大規模公開オンライン講座です。いまやモチベーションさえあれば、レベルの高い教育をタダで受けられるようになりつつあるのです。
資本主義の終着点は、コストゼロの世界
なぜこのような社会が到来しようとしているのでしょうか。実は、資本主義そのものに大きな原因があるのです。資本主義では、企業は新たな価値を生むか、あるいは「生産性」を高めることで利潤を上げます。生産性が高まれば、コストは下がります。行きつく先は、コストゼロの世界なのです。つまり限界費用ゼロ社会は、資本主義の終着点であり、必然なのです。所有の時代から「アクセスの時代」へ
限界費用ゼロ社会が来たら、いったいどうなるのでしょうか。リフキン氏は大きく2つのことが起こるといっています。1つは、所有の時代から「アクセスの時代」になるということです。私たちはあらゆるモノを「共有」し、必要なときだけ、アクセスして使うようになります。今注目を浴びているカーシェアリングやAirbnb、Uberなどは、その潮流に乗ったサービスです。さまざまな分野で、同様のサービスが次々に生まれてくることになるでしょう。お金より「関係」や「信頼」が重要に
もう1つの大きな変化は、お金があまり役に立たなくなるということです。モノがタダに近づいていくので当然です。資本主義や利潤を追求する企業などは、緩やかに終わりに向かっていくというのです。代わりに力を持つのが「協働型コモンズ」、つまりは協同組合などの組織です。協働型コモンズが、社会関係をベースにした共有経済を展開するのです。簡単に言えば、お金よりも、関係や信頼が大事になる社会がやって来るというわけです。
<参考文献>
・『限界費用ゼロ社会 〈モノのインターネット〉と共有型経済の台頭』(ジェレミー・リフキン著、柴田裕之訳 NHK出版)
・『限界費用ゼロ社会 〈モノのインターネット〉と共有型経済の台頭』(ジェレミー・リフキン著、柴田裕之訳 NHK出版)
人気の講義ランキングTOP20
オオカミはいつイヌになったか…犬の起源と家畜化の歴史
長谷川眞理子










