テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
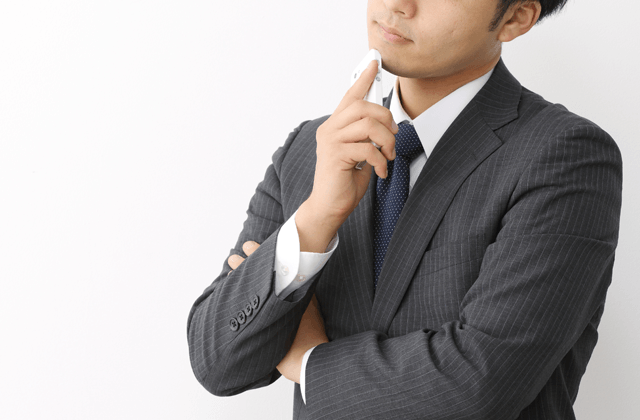
年功序列はなくなる?成果主義で生き残る方法
現在、「同一労働同一賃金」のスローガンのもと、日本型労働慣行にメスが入れられようとしている。主に問題となっているのは、正規雇用と非正規雇用の賃金格差だ。これは諸外国と比べあまりに差が大きく、格差助長の原因となっていることから批判が相次いでいた。
当然、賃金体系もそれに合わせ設計されていた。同じ仕事をしていても、より会社との関わりが深い(と考えられている)正社員の方が給料を多くもらえ、より長く勤めている人が短い人よりも多く給料をもらえるという仕組みだ。いわゆる「年功序列」である。
つまり、「若年層が先輩たちに貢ぐ」という年金のような構造といえる。今のように新卒の多くが3年で会社を辞めるといわれる状態を前提とはしていない。かつては、「若いうちは損をして、年をとってから得をする」という形でも、若者は我慢したわけだ。
しかし現在は、「忠誠」よりも「成果」がより多く求められる時代である。勤続年数が短いからという理由で多く成果を出す社員に低い給料しか払わず、あまり稼ぎのない古参に多く給料を払うということをやっていては、優秀な社員は能力主義の企業へ流出してしまう。
年功序列が廃止されるということは即ち定期昇給が廃止されるということであり、定期昇給が廃止されるということは即ち成果主義が導入されるということである。
となると、まず得をする人は、能力の高い若者ということになるだろう。次に能力の高い中高年も給料はたくさんもらえるということなので、悪くはない。
損な役回りは、能力の高くない中高年である。若いうちは年功序列で低い給料に甘んじ、年をとってからは能力に応じた低い給料に甘んじるということになる。
そういう部門の、特に経理などは、長年働いて、会社のことをよく知っていること自体が会社にとって役に立つということもあるだろう。そういうケースにおいては、定期昇給は非常に合理的だというわけだ。
誰の目にも明らかな成果を上げることが高収入の王道であることは間違いないが、1の成果を上げたプレゼン巧者が、10の成果を上げたプレゼンの不得手な者よりも評価されてしまうこともあり得る。
年功序列廃止、成果主義の導入が能力に応じた給料をもらえる社会を実現するかというと、必ずしもそういうわけではなさそうだ。
さて、あなたは定期昇給廃止で得するか、損するか、どちらの人だろう?
そもそも賃金格差があるのはなぜか
なぜ正規雇用と非正規雇用でそのような賃金格差が生まれるのか。その理由の一つとして挙げられるのが、「日本型経営」の結果によるものだ。日本型経営は、新卒から定年まで長期で勤務する社員を前提としている。ひとつの会社に生涯尽くし、人生をともにすることが推奨される。そういった封建制にも似た奇妙な労働慣行は、日本人の高い労働倫理と意欲を支え、高度経済成長の原動力になった。当然、賃金体系もそれに合わせ設計されていた。同じ仕事をしていても、より会社との関わりが深い(と考えられている)正社員の方が給料を多くもらえ、より長く勤めている人が短い人よりも多く給料をもらえるという仕組みだ。いわゆる「年功序列」である。
年功序列は若者からの搾取?
年功序列は、勤続年数が長ければ長いほど得する仕組みだ…というと、少し語弊がある。若いうちは働きに応じた給料がもらえず、年をとってから若いときにもらえなかった分を余計にもらうというのが、その実態だろう。つまり、「若年層が先輩たちに貢ぐ」という年金のような構造といえる。今のように新卒の多くが3年で会社を辞めるといわれる状態を前提とはしていない。かつては、「若いうちは損をして、年をとってから得をする」という形でも、若者は我慢したわけだ。
しかし現在は、「忠誠」よりも「成果」がより多く求められる時代である。勤続年数が短いからという理由で多く成果を出す社員に低い給料しか払わず、あまり稼ぎのない古参に多く給料を払うということをやっていては、優秀な社員は能力主義の企業へ流出してしまう。
年功序列が廃止されるとどうなる?
年功序列は主に「定期昇給」によって成り立っている。定期昇給は仕事の成果やスキルとは別に、定期的に少しずつ上がっていく給料のことだ。成果を出しても出さなくても、資格をとってもとらなくても、勤続年数が上がると同時に積み重なっていく月収、それが定期昇給だ。年功序列が廃止されるということは即ち定期昇給が廃止されるということであり、定期昇給が廃止されるということは即ち成果主義が導入されるということである。
となると、まず得をする人は、能力の高い若者ということになるだろう。次に能力の高い中高年も給料はたくさんもらえるということなので、悪くはない。
損な役回りは、能力の高くない中高年である。若いうちは年功序列で低い給料に甘んじ、年をとってからは能力に応じた低い給料に甘んじるということになる。
定期昇給が完全廃止も考えづらい
とはいえ、完全に定期昇給がなくなることも考えづらい。例えば、セールスのような仕事は売り上げがそのまま成果だから、給料の査定もしやすいが、総務や広報、経理といった間接部門はどうだろう?何をもって成果とするか、その判断は非常に難しい。そういう部門の、特に経理などは、長年働いて、会社のことをよく知っていること自体が会社にとって役に立つということもあるだろう。そういうケースにおいては、定期昇給は非常に合理的だというわけだ。
個人のプレゼン能力も重要に
成果がはかりづらいということは、プレゼンが上手な人間が得をするということでもある。つまり、自分の成果を分かりやすく伝えられた者が得をするということだ。誰の目にも明らかな成果を上げることが高収入の王道であることは間違いないが、1の成果を上げたプレゼン巧者が、10の成果を上げたプレゼンの不得手な者よりも評価されてしまうこともあり得る。
年功序列廃止、成果主義の導入が能力に応じた給料をもらえる社会を実現するかというと、必ずしもそういうわけではなさそうだ。
さて、あなたは定期昇給廃止で得するか、損するか、どちらの人だろう?
人気の講義ランキングTOP20










