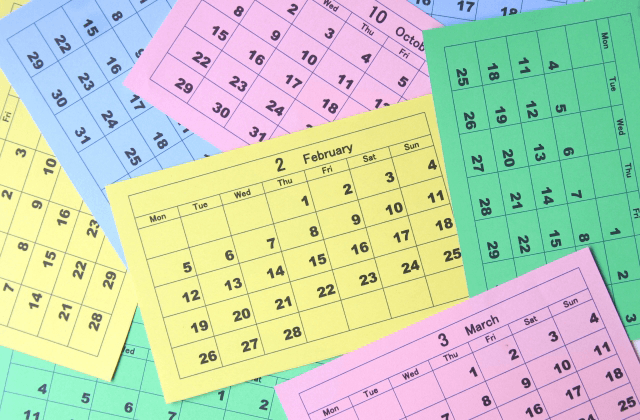
28年間の調査で判明!誕生月でなりやすい病気
これからお伝えすることは、星座占いの類ではありません。コロンビア大学(アメリカ)の科学者たちによるれっきとした研究成果です。元となったのは、1985年から2013年までの28年間にコロンビア大学医療センターとニューヨークのプレスビテリアン病院を受診した170万人の患者データ。誕生月と病気の間で相関関係があると考えられるのは、1688もの疾患のうちの55種類という結果が出ています。
「なりやすい」病気が最も多いのは10月生まれ。55種のうち15の病気で最高リスクが指摘されています。「風邪(急性上気道炎)」をはじめとして、「急性咽頭炎」「急性細気管支炎」「胃の機能障害」「視覚不良」「近視」「遠視」「性的感染症」「出産時・産後の会陰裂傷」など、多岐にわたるのが気にかかります。ただ、「なりにくい」病気が多いのも10月生まれの特徴で、特に心疾患や高血圧リスクが低いのは幸いといえるでしょう。
最も病気リスクが低いのは5月生まれです。「なりやすい病気」は一つもなく、「風邪(急性上気道炎)」もひきにくい。最も健康に恵まれた誕生月です。
例えば心疾患については、妊娠期間中の日照時間不足。「太陽の光を浴びないと人間はビタミンD不足になります。胎内にいるときに母体にビタミンDが欠けていると、血中の鉄分濃度が低くなり、胎児に栄養が行き渡らない」とボーランド博士。3月、4月生まれの人は、日照時間が短い季節に母親のお腹の中にいたことで、心臓や心血管系の病気にかかりやすい体になったと考えられるのだそうです。
アレルゲン量との関係が高いのは「ぜんそく」です。最もリスクが高い9月生まれを中心に、7月~10月生まれにぜんそく患者が集中する傾向があり、ダニの繁殖期が発病と関わっているのではないかとみられています。
<なりやすい病気>
1月:高血圧、心筋症
2月:肺がん・気管支がん、喉の異物感
3月:心疾患(心房細動、冠状動脈硬化症、うっ血性心不全、僧帽弁疾患)、前立腺がん
4月:狭心症、急性心臓病、慢性心筋虚血症
5月:特になし(病気の発症リスクは最も低い)
6月:心筋梗塞前症候群、ぜんそく増悪(発作)
7月:特になし(病気の発症リスクは二番目に低い)
8月:結膜炎
9月:急性細気管支炎、ぜんそく、中耳炎、適応障害、嘔吐しやすい
10月:風邪(急性上気道炎)、急性咽頭炎、近視、胃の機能障害、月経痛
11月:ADHD(注意欠陥・多動性障害)、急性扁桃炎、非感染性腸炎、下痢、非炎症性膣疾患
12月:アザが残りやすい
<なりにくい病気>
1月:中耳炎、喘息、嘔吐しやすい
2月:急性細気管支炎、視覚不良、胃の機能障害、発熱、ぜんそく増悪(発作)
3月:ADHD(注意欠陥・多動性障害)、月経痛、急性扁桃炎
4月:急性咽頭炎、非感染性腸炎、近視、遠視、アザが残りやすい
5月:風邪(急性上気道炎)、結膜炎、社会性の未発達
6月:性的感染症
7月:下痢、非炎症性膣疾患、妊娠・出産・産褥期の合併症
8月:特になし
9月:狭心症、心筋症、急性の心臓病
10月:心房細動、冠状動脈硬化症、高血圧、前立腺がん、喉の異物感
11月:肺がん・気管支がん、慢性心筋虚血、僧帽弁疾患
12月:特になし
いずれにしても、今回ある意味残念ともいうべき情報に関係のある方、ともかく気になるパーツを中心とした体調管理を万全に。また、冬に向けて妊娠中の女性の方には、未来のお子さんのため、UV対策以上にしっかりとした日光浴を心がけていただきたいところです。
「がん」になりやすい2月3月生まれ、病気リスクの高い10月生まれ
例えば、厚生労働省発表(2014年度)の日本人の死因第1位は「がん」(30.1パーセント)ですが、肺・気管支がんは2月生まれに多く、前立腺がんは3月生まれに多いという指摘。肺・気管支がんは死亡者数の多いがんなので、咳やタンなどの自覚がある2月生まれは軽い症状でも病院へ行きたいところです。また死因第2位の「心疾患」(15.8パーセント)についても、3月生まれのリスクが高く、次に4月生まれが多いことがわかりました。「なりやすい」病気が最も多いのは10月生まれ。55種のうち15の病気で最高リスクが指摘されています。「風邪(急性上気道炎)」をはじめとして、「急性咽頭炎」「急性細気管支炎」「胃の機能障害」「視覚不良」「近視」「遠視」「性的感染症」「出産時・産後の会陰裂傷」など、多岐にわたるのが気にかかります。ただ、「なりにくい」病気が多いのも10月生まれの特徴で、特に心疾患や高血圧リスクが低いのは幸いといえるでしょう。
最も病気リスクが低いのは5月生まれです。「なりやすい病気」は一つもなく、「風邪(急性上気道炎)」もひきにくい。最も健康に恵まれた誕生月です。
なぜ誕生月と病気は関係があるの?
でも、そもそもなぜ誕生月によって「なりやすい病気」リスクがあるのでしょうか? 一つ目に妊婦の健康状態が季節によって変わること、次に新生児の体内に入るアレルゲン量の季節差が原因になり得ると、コロンビア大学医療センターのメアリー・レジーナ・ボーランド博士は解説しています。例えば心疾患については、妊娠期間中の日照時間不足。「太陽の光を浴びないと人間はビタミンD不足になります。胎内にいるときに母体にビタミンDが欠けていると、血中の鉄分濃度が低くなり、胎児に栄養が行き渡らない」とボーランド博士。3月、4月生まれの人は、日照時間が短い季節に母親のお腹の中にいたことで、心臓や心血管系の病気にかかりやすい体になったと考えられるのだそうです。
アレルゲン量との関係が高いのは「ぜんそく」です。最もリスクが高い9月生まれを中心に、7月~10月生まれにぜんそく患者が集中する傾向があり、ダニの繁殖期が発病と関わっているのではないかとみられています。
なりやすい病気となりにくい病気を一目でチェック!
では、なりやすい病気・なりにくい病気を一覧で見ていきましょう。<なりやすい病気>
1月:高血圧、心筋症
2月:肺がん・気管支がん、喉の異物感
3月:心疾患(心房細動、冠状動脈硬化症、うっ血性心不全、僧帽弁疾患)、前立腺がん
4月:狭心症、急性心臓病、慢性心筋虚血症
5月:特になし(病気の発症リスクは最も低い)
6月:心筋梗塞前症候群、ぜんそく増悪(発作)
7月:特になし(病気の発症リスクは二番目に低い)
8月:結膜炎
9月:急性細気管支炎、ぜんそく、中耳炎、適応障害、嘔吐しやすい
10月:風邪(急性上気道炎)、急性咽頭炎、近視、胃の機能障害、月経痛
11月:ADHD(注意欠陥・多動性障害)、急性扁桃炎、非感染性腸炎、下痢、非炎症性膣疾患
12月:アザが残りやすい
<なりにくい病気>
1月:中耳炎、喘息、嘔吐しやすい
2月:急性細気管支炎、視覚不良、胃の機能障害、発熱、ぜんそく増悪(発作)
3月:ADHD(注意欠陥・多動性障害)、月経痛、急性扁桃炎
4月:急性咽頭炎、非感染性腸炎、近視、遠視、アザが残りやすい
5月:風邪(急性上気道炎)、結膜炎、社会性の未発達
6月:性的感染症
7月:下痢、非炎症性膣疾患、妊娠・出産・産褥期の合併症
8月:特になし
9月:狭心症、心筋症、急性の心臓病
10月:心房細動、冠状動脈硬化症、高血圧、前立腺がん、喉の異物感
11月:肺がん・気管支がん、慢性心筋虚血、僧帽弁疾患
12月:特になし
3月4月に出産予定の女性は、頑張って日光浴を
今回のデータはニューヨークの病院から集められたものなので、日本人にとって参考になる部分と異なる部分が含まれているはずだと言われます。よって、日本でも同様の研究が、進められている最中なのではないでしょうか。いずれにしても、今回ある意味残念ともいうべき情報に関係のある方、ともかく気になるパーツを中心とした体調管理を万全に。また、冬に向けて妊娠中の女性の方には、未来のお子さんのため、UV対策以上にしっかりとした日光浴を心がけていただきたいところです。
人気の講義ランキングTOP20
ラマルクの進化論…使えば器官が発達し、それが子に伝わる
長谷川眞理子
明日はわが身?水道管破損と道路陥没~水から考える未来
テンミニッツ・アカデミー編集部







