テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
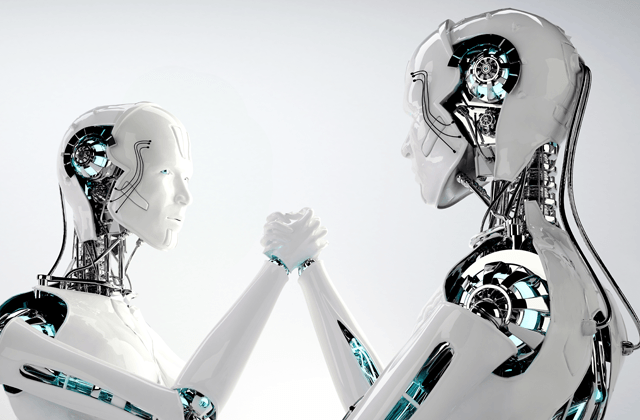
解いておくべき「人工知能」に対する誤解とは?
人工知能はこれからの世界を大きく変えていく存在です。しかし、人工知能をめぐる話題には、誤解もたくさん含まれています。ビジネスの世界でもAI問題が身近になってきた現在、解いておいたほうがいい誤解について、東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授の柳川範之氏が、ビジネスの視点も交えて語っています。
まず、「人間の能力を超えたコンピュータ」はずっと前から存在してきたということです。それは計算スピードです。「なんだ。当たり前じゃない」と思われるかもしれません。しかし、演算速度の面で機械が人間を凌駕しているのは既成事実。囲碁という勝負の場面で負けたからといって、今さら新しく「人間が人工知能に追い越された」と、驚いてみせる必要はないのです。
AlphaGoには、これも当然のことながらプログラマーがいて、囲碁戦の裏で必死にプログラムの工夫を行いました。そのために参照した棋譜は、これまで人間対人間によって行われてきた結果の集積だったことは言うまでもありません。裏で動かす人間の存在を無視して、「人工知能が人間に勝った」というのは、誤解を招くための言い方だということです。
実際に「きまぐれ人工知能プロジェクト作家ですのよ」を牽引する松原仁教授(公立はこだて未来大学)は、「現在公開している小説については、“コンピュータの力が2割、人間の力が8割”と説明させてもらっています。つまり、人間がストーリーを与え、AIがそれに対応する日本語を選んで文章を生成する仕組みです」と「フォーブスジャパン」の取材に答えています。
彼らが取り組んでいるのは「感性型AI開発」と呼ばれるジャンルで、一人の作家の作品を分析し、その作品性を抽出することをも目指しています。「人工知能が小説を書く」は、現段階では単純なる誤解ということです。
また人工知能には、囲碁をやっている最中に突然碁盤に背を向け、「俺は絵を描くことなら負けない」と絵を描きだす人間のような真似は決してできません(そうしたことが意味があるかどうかは別です)。一方、ビジネスでは、戦うフイールドを臨機応変に変えていくことがよく求められます。そして、そこにこそ経営の意味があるはずだということを、柳川氏の話は感じさせてくれます。
限定された中でしか勝負が出来ない人工知能。枠の外側に新たに自分のフィールドを築くことのできる人間。この違いを頭に入れておかないと、「人工知能が人間を凌駕する」という誤解に悩まされることになるのです。
これも当たり前の話ですが、人工知能を実際に役立てていくには、デジタル化が必須だという点です。まだまだ古い技術、紙ベースでの仕事を進めているお役所などでは、「人工知能に仕事を奪われる」ことを心配する前に、やるべき仕事は山ほどあるということではないでしょうか。
囲碁対決の誤解1:「人間が人工知能に追い越された」
2015年10月、Googleの関連会社が開発した「AlphaGo(アルファ碁)」がプロ囲碁棋士にハンディキャップなしで勝ったというニュースが大きく報道されました。これにより、「人工知能が人間に勝った」「Googleの人工知能はやがて人類の知能を凌駕するにちがいない」という論調がマスコミには多く見られます。しかし、ここには複数の誤解が含まれている、と柳川氏は言うのです。まず、「人間の能力を超えたコンピュータ」はずっと前から存在してきたということです。それは計算スピードです。「なんだ。当たり前じゃない」と思われるかもしれません。しかし、演算速度の面で機械が人間を凌駕しているのは既成事実。囲碁という勝負の場面で負けたからといって、今さら新しく「人間が人工知能に追い越された」と、驚いてみせる必要はないのです。
囲碁対決の誤解2:「人間に人工知能が勝った」
続いて、囲碁対決において「勝ったのが人工知能だ」というのも誤解だ、と柳川氏は言います。勝ったのは、あくまでも「Googleの人工知能を使った人間」だ、というのです。AlphaGoには、これも当然のことながらプログラマーがいて、囲碁戦の裏で必死にプログラムの工夫を行いました。そのために参照した棋譜は、これまで人間対人間によって行われてきた結果の集積だったことは言うまでもありません。裏で動かす人間の存在を無視して、「人工知能が人間に勝った」というのは、誤解を招くための言い方だということです。
「小説を書く人工知能」という誤解
そうなると、最近話題の「小説を書く人工知能」の誤解もお分かりでしょう。こちらも、やはり「人工知能を使って、人間が小説を書いている」といったほうが正しい。実際に「きまぐれ人工知能プロジェクト作家ですのよ」を牽引する松原仁教授(公立はこだて未来大学)は、「現在公開している小説については、“コンピュータの力が2割、人間の力が8割”と説明させてもらっています。つまり、人間がストーリーを与え、AIがそれに対応する日本語を選んで文章を生成する仕組みです」と「フォーブスジャパン」の取材に答えています。
彼らが取り組んでいるのは「感性型AI開発」と呼ばれるジャンルで、一人の作家の作品を分析し、その作品性を抽出することをも目指しています。「人工知能が小説を書く」は、現段階では単純なる誤解ということです。
「囲碁」が人工知能の得意ジャンルである理由
囲碁は、19×19の格子が描かれた盤上だけが勝負のフィールドであり、他のところに石は置けません。つまり「選択肢の次元が低い」と柳川氏は指摘します。もちろん選択肢の数は無限です。しかし、戦うのはあくまで盤上だけです。よって、「囲碁は難しいから、人工知能では処理できない」というのも、複雑さをはき違えた誤解です。また人工知能には、囲碁をやっている最中に突然碁盤に背を向け、「俺は絵を描くことなら負けない」と絵を描きだす人間のような真似は決してできません(そうしたことが意味があるかどうかは別です)。一方、ビジネスでは、戦うフイールドを臨機応変に変えていくことがよく求められます。そして、そこにこそ経営の意味があるはずだということを、柳川氏の話は感じさせてくれます。
限定された中でしか勝負が出来ない人工知能。枠の外側に新たに自分のフィールドを築くことのできる人間。この違いを頭に入れておかないと、「人工知能が人間を凌駕する」という誤解に悩まされることになるのです。
人工知能を「使える」環境整備こそ必要
しかし、柳川氏は、人工知能が驚異的な発達を遂げたディープラーニングの中身については、人間が追跡不能な部分もあり、そこには注意が必要だ、とも語っています。ただ、本当の落とし穴はもっと近いところに潜んでいます。これも当たり前の話ですが、人工知能を実際に役立てていくには、デジタル化が必須だという点です。まだまだ古い技術、紙ベースでの仕事を進めているお役所などでは、「人工知能に仕事を奪われる」ことを心配する前に、やるべき仕事は山ほどあるということではないでしょうか。
<参考サイト>
・フォーブスジャパン:AIが小説を書く、その仕組みと未来
http://forbesjapan.com/articles/detail/14581
・フォーブスジャパン:AIが小説を書く、その仕組みと未来
http://forbesjapan.com/articles/detail/14581
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










