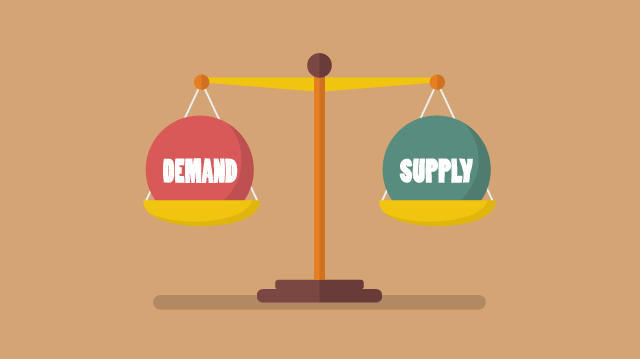●日本の経済は需要が強いが、供給がついてこない
私は、マクロ経済の状況について、一つ重要なキーワードがあると思っています。それは需要と供給ということです。全ての経済現象には需要と供給の両面があり、そこをしっかりと見ていくということが重要なのですが、マクロ経済についても同じことが言えます。結論からいえば、日本の経済は需要が強いということです。それが景気を支えているのですが、供給がついてこないという大問題があります。
経済学を勉強した方はよくご存じと思いますが、マクロの需要は専門用語で「総需要」といいます。非常に単純化すれば、消費や投資、あるいは公共投資のようや政府支出や輸出から輸入を引いた純輸出などの、内需や外需がどのように動いていくかという需要サイドのことです。
●十分に拡大してこなかった日本の供給サイド
もちろん、景気が堅調に展開していくためには需要が十分になければいけません。消費が強いとか、投資が経済を刺激するとか、あるいは外需が良好であるといったことが必要で、経済が少し厳しい時には、公的需要の公共投資や政府支出が増えていくということになります。日本は安倍内閣が発足してから5年、もうすぐ6年目になりますが、この間、需要はある意味で非常に成功してきたといえます。
ただ、マクロ経済には供給という面があります。実際に消費や投資、あるいは公共投資のような財やサービスの需要に対応するためには、それに応じたモノやサービスの供給が行われなければなりません。そのモノやサービスが供給されるためには、労働力だとか資本、さらに言えばそういうことを支えている技術革新や生産性の上昇、こういったものの裏付けがないといけないわけで、これが供給サイドです。
残念ながら、日本の供給サイドはやはり十分に拡大してこなかったといえます。象徴的なことを一ついえば、これだけ経済を刺激してきたにもかかわらず、潜在成長率はまだ1パーセントいくかいかないかという非常に低い水準が続いているのです。潜在成長率というのは、今お話しした資本や労働や、あるいは生産性の上昇から推計される日本の中長期の成長の実力のようなことを表しています。これが非常に低いということは、今後いくら需要の刺激を続けたとしても潜在成長率が上がらないということで、経済がなかなか伸びていかないことを意味します。